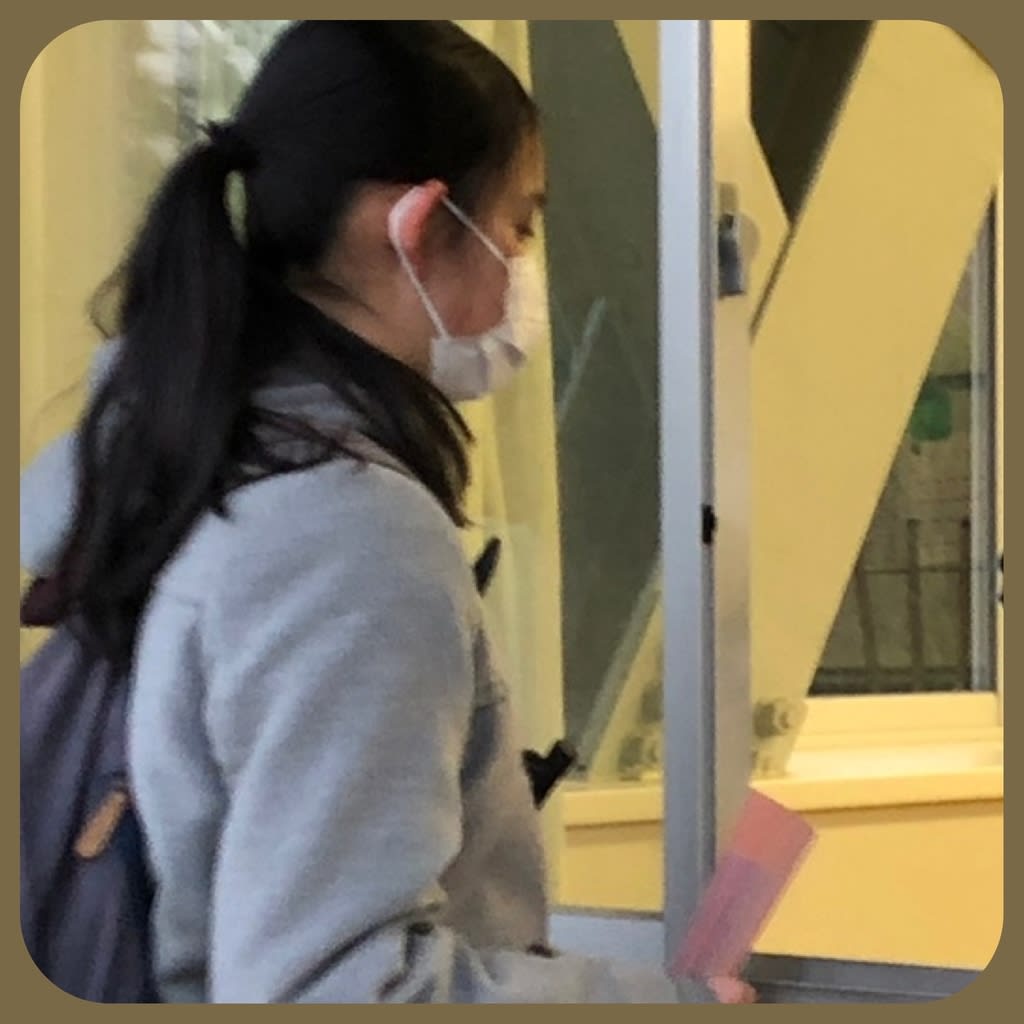「杖言葉」というものがあるのをご存じでしょうか。
これは作家の五木寛之さんが著書のなかで触れられています。
その人の行動や生活の仕方の支えになっている言葉のことです。
わたしは、その杖言葉は、人がつねに意識している場合もあれば、無意識のうちに支えになっていることもあると考えています。
私が学級担任をした生徒のなかにも、卒業前に伝えた言葉を、今でも支えにしている人がいます。
波瀾万丈で、悩みの中学校生活をくぐってきた男子生徒に、わたしが卒業前に言ったことばがあります。
それは、「苦労した分だけ強くなった」でした。
彼は、卒業後も仕事でうまくいかないときには、この言葉を思い出していたそうです。
こうなると、教師は自分が放つ言葉の大切さを自覚すべきなのですが、ずっと支えになるか、ならないかは、生徒次第だと思います。
ふだん意識していなくても、ふと思い出して「あのときの、あの先生の言葉に支えられてきた」と、思い出すこともあるでしょう。
今年は新型コロナウイルスは、私たちに人と引き離すように仕向けました。
「日常」だと思い込んでいたことが、当たり前でないことを、私たちに思い知らせました。
そのぶん、同時にそれまでの自分がさまざまなものごとに対して、いかに無自覚でいたかに気づくのです。
そのとき、ふだんは意識していないけれど、自分を支えてくれている言葉があることに気づくのです。
先ほどの言葉が杖言葉であるとするなら、いま苦労してでも、その苦労に意味があると思い、人は困難なことにも取り組もうとするのです。
こうなると、新型コロナウイルスは、思索して、自分を見つめる時間を、私たちに与えてくれていると考えることができます。
こんな想いとともに、令和2年(2020年)が過ぎていこうとしています。