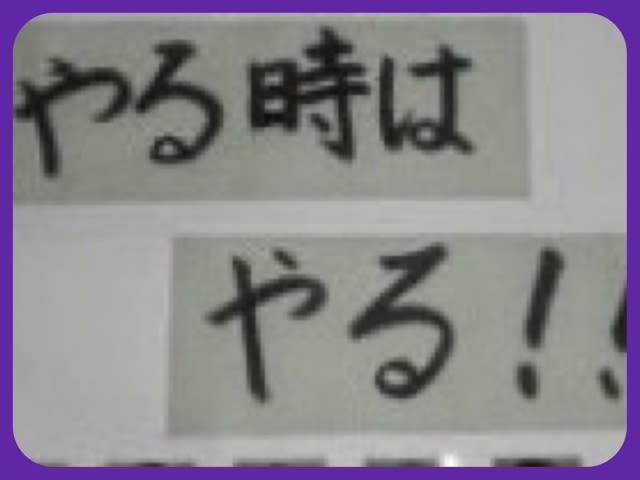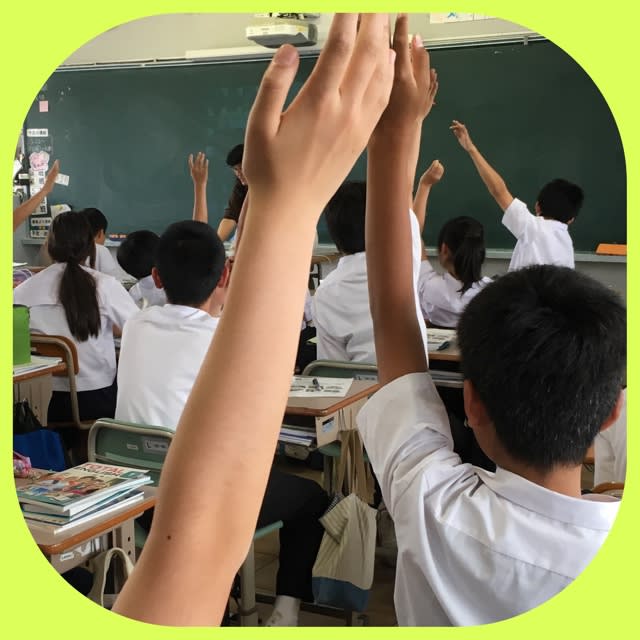箕面市の中学校では、2学期に職場体験を行っています。今時分はどこの学校も終了しています。
中学生は、職場体験を通してどんなことを学んでくるのでしょうか。
たんにどんな仕事であるかがわかった、というものでなく、もっと深いことを学んで帰ってくる生徒も多くいます。
下記の感想は、今年、箕面市立中学校の2年生が書いてくれました。人として生きる上で大切な体験を得ました。
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🔹 職場体験で、人が働く意味や働くことで得るものがわかった気がする。
店長さんの「人の仕事には意味がある。働く仕事一つひとつに理由がある」という言葉を聞いて、僕は働いて人の役に立ちたいなと思った。
職場体験で良い経験をすることができた。
🔹 ホテルは、表では完璧だけど、裏では汗をかきながら仕事をしていることがわかり、とてもすごいなと思いました。
やってみると想像以上にしんどくて、ものすごい体力が必要です。でもやっている方に訊いてみると、とても楽しいとおっしゃっていました。
この仕事に誇りを持っている方々に感動しました。
自分もやりたいことに向かって楽しくやっていきたいと思いました。自分が何かをして相手の方が喜んでもらえるような仕事をしていきたいです。
決して笑顔を忘れてはいけないことがわかりました。
🔹 いちばん難しいと思ったのは、歳の離れた大人の方と会話すること、質問することでした。
できるのかなと思っていたけど、先生方はいつも忙しく、なかなか話しかけるタイミングをつかむこともできませんでした。敬語もカタコトになってしまいました。
幼稚園の先生方は、一人ひとりにしっかりとついて目を離さず、安全第一に動かれていて、常に他の先生方と情報を共有されているところがすごく良いと思いました。
これは学校生活と部活の中でしっかりと活かせることなので、次につなげたいと思いました。
🔹 今回、以前から興味があった動物の保護施設の現状や厳しさを知りたいと思い、この職場を選びました。
「殺処分ゼロ」という言葉を見聞きすることがあり、実際はどうなのかを知りたいと考えて行きました。
副会長の方からきいた話では、いろいろと法律が変わったり殺処分のカウントの仕方が変わったことで、一見ゼロにみえても、殺処分されている犬猫は依然としていることがわかりました。
この現実と、「ハッピーハウス」(能勢町 注:捨てられた犬や猫を預かり、訓練をして、里親を探してつなげるNPO)で過ごす犬猫を見て、このことを世の中に発信していきたいと思いました。
もっとこういう活動に協力しやすい世の中、雰囲気になればいいな、したいなと思いました。
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
このように、中学生であっても、
「働く」ということで、社会とかかわることができる。
このことを学んで、学校に帰ってきます。