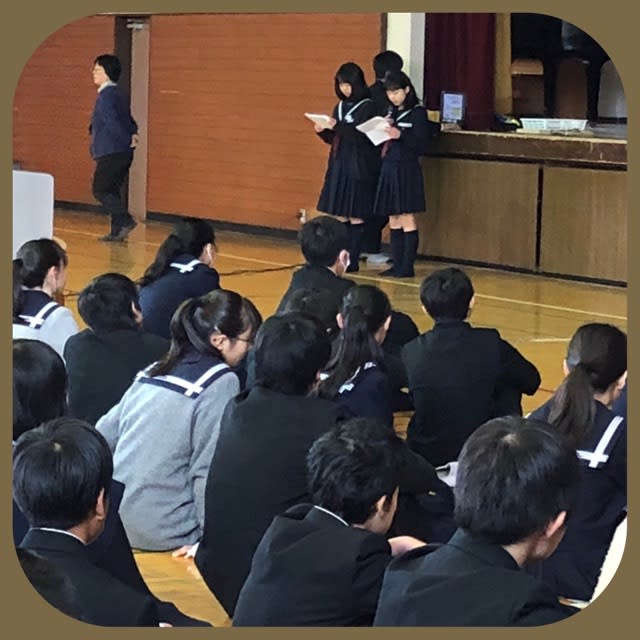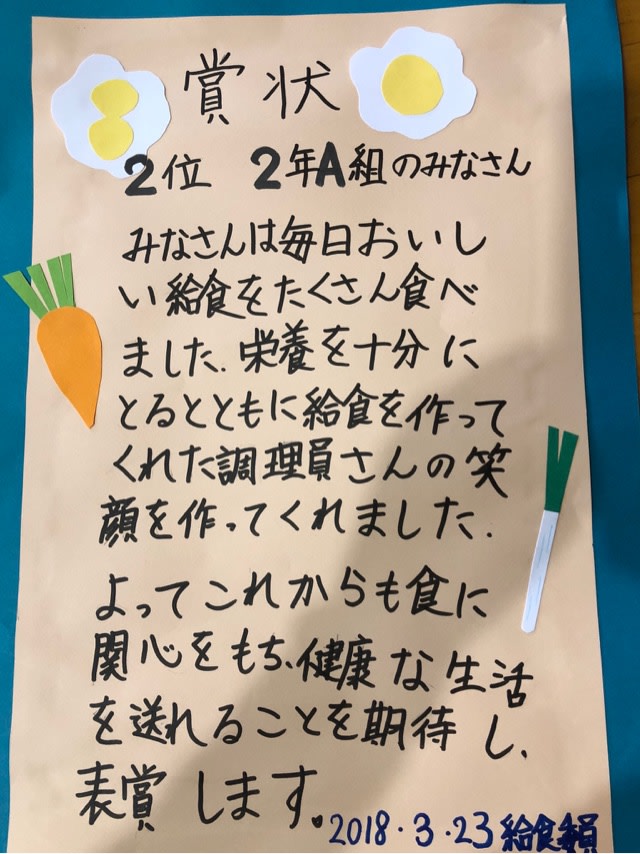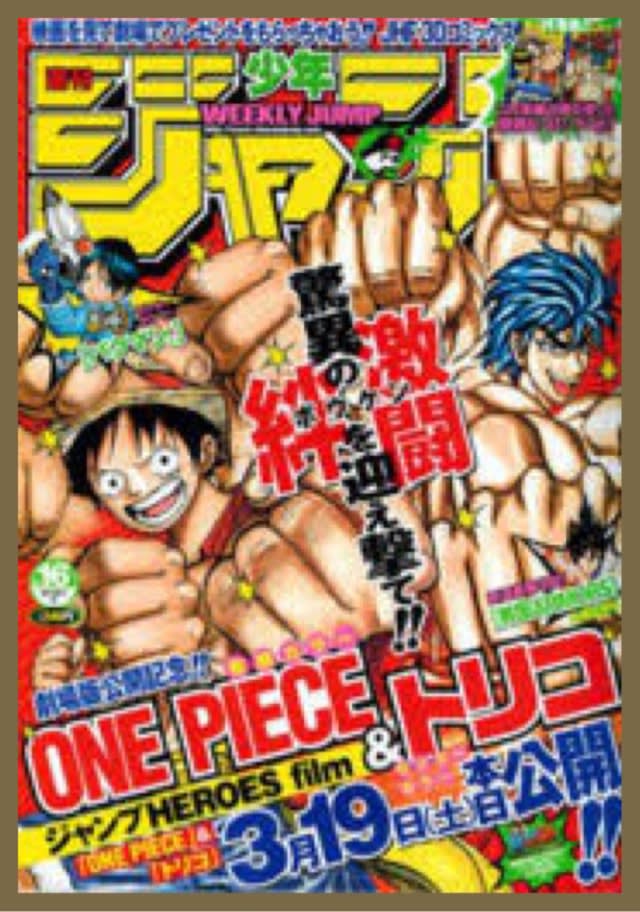今日で3月も終わりです。3年生は卒業式こそ終わりましたが、在籍は3月31日までは三中にありますので、今日までは三中生です。
明日からは、高校生になります。
そして、三中では、入学式こそまだですが、新1年生が在籍することになります。
さて、3学期をふりかえると、さまざまなことがありました。
今回は、中学生のプライドについて、考えます。
1月に、中学生の吹奏楽ソロコンテストがあり、三中吹奏楽部からも出場しました。
大阪府下出場者78名中、7名が2月下旬の関西大会に出場しました。
三中から2名の生徒が関西大会に出場しました。
いまからのお話は、仮定で次のような会話が、母親となされたとします。
「7名に選ばれた子はうまかったとは思うけど、ゼッタイ、私の方がうまかった。審査員がちゃんと審査していない。どんなに練習しても、審査員がちゃんとみてくれないなら、もう演奏しても仕方がない!」
自信を失い、「次も選ばれなかったら・・・」と不安になり、その前にやめてしまったらいいのでは。
こんな気持ちで言っていると考えます。
もし、みなさんがこの母親なら、どう子どもに言いますか。
「次に、またがんばればいいのよ」
「うまい子の上には、上がいるわね」
この言葉は、「自分はうまい」と思っている子に対して、「あなたの演奏が劣っていた」ということを言っているので、自分のことを「うまい」と思うプライドを傷つけます。
(本当は、そんなプライドは、あまりもたない方がいいのですが、)
そうかといって、「審査員の好みかましれないね」と、わが子の言い分を認めてしまうと、プライドは保てるでしょうが、審査員への信頼を下げてしまうので、好ましくないです。
そこで、演奏することへの自信をなくさせないように、「あなたはプライドを持っているけど、プライドはあまり役にたたないよ」ということをわからせる言い方をします。
「別の子がうまいか、うまくないかは、演奏を聴いてみないとわからない。
でも、あなたがうまいことは、お母さんが知っているよ。だから、あなたが自信をもつのは当然よ。
今回の結果で、その自身をなくしているかもしれない。
でも、やめてしまって、あなたの素晴らしい演奏をみんなが聴けなくなるのは残念よ。
来年、選ばれてみんなから拍手を受けているのと、やめて後悔しているのと、どちらがいい?」
このような言い方は、演奏への自信もなくさせないし、プライドよりも聴く人を喜ばせることの大切さに気づかせることになるでしょう。
中学生の心情は微妙なもの。ここまで気を遣うのはたいへんかもしれませんが、一方ではやる気を出した中学生の力強さには感心することも多くあります。
[写真と本文の内容は、関係ありません]