イタリアブックフェア初日に『バザーリア講演録 自由こそ治療だ! イタリア精神保健ことはじめ』の本の紹介セミナーを聞いてきました(2018.4.7)@イタリアブックフェア2018
まずは行ってきました初日のイタリアブックフェア2018!!
この日は友人と待ち合わせて与 勇輝展 創作人形の軌跡等をはしごしてからイタリアブックフェアへと足を運びました 私は今年は4回程通う予定です(笑)
会場では例年のように 社会 文学 児童図書 料理 音楽 美術 建築 デザイン 地理紀行等 様々なカテゴリーのイタリアに関する書籍が紹介されており 須賀敦子没後20年の展示や 「マルチレイヤ― 名画ナビゲーションシステム」の紹介等もありました
* * *
この日の本の紹介セミナーは 『バザーリア講演録自由こそ治療だ! イタリア精神保健ことはじめ』という本です
登壇者はこの本を翻訳された大内氏と鈴木氏の2名で セミナーのコーナーは立見も出る程でした
まずは 精神医療やバザーリア法について イタリア映画の中で取り上げられたものをざっと:
「むかしMattoの町があった」「人生、ここにあり!」「輝ける青春」「歓びのトスカーナ」「ふたつめの影」その他10本
私はこの時 イタリア文化会館のステージで 障がい者たちが演じたテアトロ・パトロジコの「王女メディア」の舞台での感動を思い出しました
そして映画「愛の勝利を・ムッソリーニを愛した女」での檻の中の精神病院のシーン 「ボローニャの夕暮れ」等を思い浮かべました あの当時は檻がありベッドに拘束されていたりしていたイタリアの精神病院が いったいどうやって廃止に向かっていったのか...
フランコ・バザーリア(1924~1980)はヴェネツィアで生まれ パドヴァ大学医学部時代に反ファシスト運動で半年間投獄された経験が元となり のちに刑務所のような精神病院を改革するようになります
 ← バザーリア
← バザーリア
精神医学の学部でトップクラスで学者を目指していたのですが 37才で左遷のようにしてゴリツィアの精神病院の院長に就任し 病院内部の改革に着手することになります
この時に背中を押したのが 妻でありフェミニスト第一人者であったフランカ・オンガロでした
著書『否定された施設』を刊行 46才でミケーレ・ザネッティと出合います 彼はトリエステの県知事で 国境の町で多文化が入り混じるトリエステとの精神病院の院長にとバザーリアに乞いますが この時ばかりは子供たちのこともあり妻が反対するも バザーリアはトリエステに赴くのです
彼がすすめたのは精神病院の窓の鉄格子の除去 拘束衣の使用禁止 白衣の着用の廃止です
彼が身につけてきた精神医学の知識は役に立たない欠陥だらけのものだと自ら気づくのです
そして1978年に「バザーリア法(Legge Basaglia)」とよばれる180号法が成立します
この法律によって「新たな公立精神病院の建設の禁止」「既存の公立精神病院への新たな入院の禁止」「公立精神病院の段階的な閉鎖」が定められました
1980年に彼は56才でヴェネツィアで亡くなります そして1999年 イタリア全国の公立精神病院が閉鎖され 2017年にイタリアの司法精神病院が閉鎖され ヨーロッパで初の公立精神病院の完全閉鎖と 地域精神保健サービスの開設にいたるわけです
イタリアの精神保健改革は社会全体を巻き込んだ運動で 市民の説得 (退院後のフォロー 施設と地域の間の壁を壊す) 精神病院の内実を社会に告発(「アベルの園」というドキュメンタリー番組を1968年1月3日土曜夜に放映) 人的ネットワークの活用(アーティストや作家 ミュージシャン等) 政党や政治家との連携をすすめて ようやく1978年に180号法が成立したとのこと
イタリアは法律ができても実効があやふやな面があり 地域の精神保健サービス網の構築を進める必要がありますが 日本に比べて生活圏が小さいため 顔見知りが適度にいる圏内で暮らせるのが強みとのこと 障がい者は "同じではないが危険ではない"とのくくり
「自由こそ治療だ!」が改革のモットーで トリエステの病院の院長室にはその落書きが30年も残されていたそうです
「退院しても頭は入院状態」つまり精神病院をなくすだけではダメで 自分の意志で行動する力を失ってしまうという「蛇に自由を奪われた男の寓話」をご紹介いただきました
これは他の組織等でも同じですね 自由になっても何をしたらよいかわからなくなってしまうのです そして「~からの自由」だけではなく「~への自由」も取り返すために何ができるか...
ここで紹介されたのがイタリアの「社会的共同組合」の試みです これは昨年のブックフェアで「イタリアの社会的協同組合」という本を買って読んでいたのですぐに頭に浮かびました 様々な種類の仕事があり 個人ではなく集団で社会(マーケット)に勝負していきます
また 「入院モデル(ospialisazione)」と「歓待モデル(ospitalità)」の2つの治療文化をご紹介いただきました 実際に病院の壁を患者たちが壊すシーンもありました 患者本人の意思決定を重要視するとのこと
 ← 2つの治療文化
← 2つの治療文化
そして最後に衝撃だったのは 日本では精神病院の数が増加し OECD諸国は減っているというグラフです 日本は明らかに逆行していますね
ちなみにイタリアでは日本のような養護学校はなく 地域の普通校で受け入れているとのこと 70年代に転換したのだそうで インクルージョンというそうです 日本の状況は こちら
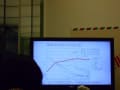 ← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)
← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)
色々な揺り戻しがある中で 日本も多くを学ぶことがあるのではないかと感じました
『イタリア精神保健改革と『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』は こちら
日本からのスタディツアー(2018年5月)も 満席となったようです
本の紹介セミナーは こちら
イタリアブックフェア2018は こちら
翻訳者の方々の運営するサイト「自由こそ治療だ」はこちら
「Freedom is Therapeutic」は こちら
当日使用したファイル・データは こちら
* この記事の作成にあたり 翻訳者の大内氏にご協力いただきました 心よりお礼申し上げます
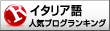 イタリア語ランキング
イタリア語ランキング
 にほんブログ村
にほんブログ村
まずは行ってきました初日のイタリアブックフェア2018!!
この日は友人と待ち合わせて与 勇輝展 創作人形の軌跡等をはしごしてからイタリアブックフェアへと足を運びました 私は今年は4回程通う予定です(笑)
会場では例年のように 社会 文学 児童図書 料理 音楽 美術 建築 デザイン 地理紀行等 様々なカテゴリーのイタリアに関する書籍が紹介されており 須賀敦子没後20年の展示や 「マルチレイヤ― 名画ナビゲーションシステム」の紹介等もありました
* * *
この日の本の紹介セミナーは 『バザーリア講演録自由こそ治療だ! イタリア精神保健ことはじめ』という本です
登壇者はこの本を翻訳された大内氏と鈴木氏の2名で セミナーのコーナーは立見も出る程でした
まずは 精神医療やバザーリア法について イタリア映画の中で取り上げられたものをざっと:
「むかしMattoの町があった」「人生、ここにあり!」「輝ける青春」「歓びのトスカーナ」「ふたつめの影」その他10本
私はこの時 イタリア文化会館のステージで 障がい者たちが演じたテアトロ・パトロジコの「王女メディア」の舞台での感動を思い出しました
そして映画「愛の勝利を・ムッソリーニを愛した女」での檻の中の精神病院のシーン 「ボローニャの夕暮れ」等を思い浮かべました あの当時は檻がありベッドに拘束されていたりしていたイタリアの精神病院が いったいどうやって廃止に向かっていったのか...
フランコ・バザーリア(1924~1980)はヴェネツィアで生まれ パドヴァ大学医学部時代に反ファシスト運動で半年間投獄された経験が元となり のちに刑務所のような精神病院を改革するようになります
 ← バザーリア
← バザーリア精神医学の学部でトップクラスで学者を目指していたのですが 37才で左遷のようにしてゴリツィアの精神病院の院長に就任し 病院内部の改革に着手することになります
この時に背中を押したのが 妻でありフェミニスト第一人者であったフランカ・オンガロでした
著書『否定された施設』を刊行 46才でミケーレ・ザネッティと出合います 彼はトリエステの県知事で 国境の町で多文化が入り混じるトリエステとの精神病院の院長にとバザーリアに乞いますが この時ばかりは子供たちのこともあり妻が反対するも バザーリアはトリエステに赴くのです
彼がすすめたのは精神病院の窓の鉄格子の除去 拘束衣の使用禁止 白衣の着用の廃止です
彼が身につけてきた精神医学の知識は役に立たない欠陥だらけのものだと自ら気づくのです
そして1978年に「バザーリア法(Legge Basaglia)」とよばれる180号法が成立します
この法律によって「新たな公立精神病院の建設の禁止」「既存の公立精神病院への新たな入院の禁止」「公立精神病院の段階的な閉鎖」が定められました
1980年に彼は56才でヴェネツィアで亡くなります そして1999年 イタリア全国の公立精神病院が閉鎖され 2017年にイタリアの司法精神病院が閉鎖され ヨーロッパで初の公立精神病院の完全閉鎖と 地域精神保健サービスの開設にいたるわけです
イタリアの精神保健改革は社会全体を巻き込んだ運動で 市民の説得 (退院後のフォロー 施設と地域の間の壁を壊す) 精神病院の内実を社会に告発(「アベルの園」というドキュメンタリー番組を1968年1月3日土曜夜に放映) 人的ネットワークの活用(アーティストや作家 ミュージシャン等) 政党や政治家との連携をすすめて ようやく1978年に180号法が成立したとのこと
イタリアは法律ができても実効があやふやな面があり 地域の精神保健サービス網の構築を進める必要がありますが 日本に比べて生活圏が小さいため 顔見知りが適度にいる圏内で暮らせるのが強みとのこと 障がい者は "同じではないが危険ではない"とのくくり
「自由こそ治療だ!」が改革のモットーで トリエステの病院の院長室にはその落書きが30年も残されていたそうです
「退院しても頭は入院状態」つまり精神病院をなくすだけではダメで 自分の意志で行動する力を失ってしまうという「蛇に自由を奪われた男の寓話」をご紹介いただきました
これは他の組織等でも同じですね 自由になっても何をしたらよいかわからなくなってしまうのです そして「~からの自由」だけではなく「~への自由」も取り返すために何ができるか...
ここで紹介されたのがイタリアの「社会的共同組合」の試みです これは昨年のブックフェアで「イタリアの社会的協同組合」という本を買って読んでいたのですぐに頭に浮かびました 様々な種類の仕事があり 個人ではなく集団で社会(マーケット)に勝負していきます
また 「入院モデル(ospialisazione)」と「歓待モデル(ospitalità)」の2つの治療文化をご紹介いただきました 実際に病院の壁を患者たちが壊すシーンもありました 患者本人の意思決定を重要視するとのこと
 ← 2つの治療文化
← 2つの治療文化そして最後に衝撃だったのは 日本では精神病院の数が増加し OECD諸国は減っているというグラフです 日本は明らかに逆行していますね
ちなみにイタリアでは日本のような養護学校はなく 地域の普通校で受け入れているとのこと 70年代に転換したのだそうで インクルージョンというそうです 日本の状況は こちら
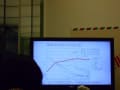 ← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)
← 精神病床数の各国比較(厚労省医療計画/H24)色々な揺り戻しがある中で 日本も多くを学ぶことがあるのではないかと感じました
『イタリア精神保健改革と『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』は こちら
日本からのスタディツアー(2018年5月)も 満席となったようです
本の紹介セミナーは こちら
イタリアブックフェア2018は こちら
翻訳者の方々の運営するサイト「自由こそ治療だ」はこちら
「Freedom is Therapeutic」は こちら
当日使用したファイル・データは こちら
* この記事の作成にあたり 翻訳者の大内氏にご協力いただきました 心よりお礼申し上げます
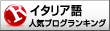 イタリア語ランキング
イタリア語ランキング















