24日月曜日,ふらっと加古川市の鶴林寺に行ってきました。
目的は雰囲気を感じてくること。
そして,
歴博にある太子堂の10分の1模型の実物を見てくること。
歴博の「県立歴史博物館がいざなう ひょうご歴史の旅」によると,
兵庫県に11件の国宝建築があり,そのうち5件は姫路城に関わるもの,
そして,残り6件が平安・鎌倉・室町の寺院建築です。すべて,旧播磨国内にあります。
そのうち2件は鶴林寺。
本堂も国宝ですが,
太子堂は,兵庫県最古の寺院建築で,平安時代後期の天永3(1112年)に建てられたと考えられています。
さて,実物は,模型よりも木の色がちょっとくすんでいます。
「靴を脱いでおあがりください。」ということは,靴を脱いだら上がっていいのだと思い,
靴を脱いで,建物の周囲をぐるっと回りました。
東西1か所ずつ段差があって,建物ばかり見て歩いていたので,降りる方でつまずきました。
上記の本によると,礼拝するための礼堂がつくられていて,身舎(もや)よりも1段低くなっているそうです。
隙間から中をのぞきました。
暗くてよく見えません。
仏像のようなものが少しあったと思います。
その後,いくつかの建物を見て回り
宝物館へ
ここで仰天!!!
太子堂内陣の太子堂壁画(復元模写)と
釈迦三尊像&四天王立像(こちらは本物)
壁画は,平安仏画ですが,煤けて肉眼では見えなくなっています。
昭和51年,赤外線写真によって確認され,重要文化財に指定されています。
それを芸大の人が復元模写し,展示しています。
涅槃図や九品来迎図だけでなく,柱やその他全面に彩色されていて,
何とも言えない・・・,ん・・・。
また,内陣内の仏像も,
仏の世界…って感じがして,
これをそのまま,太子堂内に置けば,さらにすごいだろうと思うのですが,
「警備が・・・」とのことでした。
(実際,ほかの絵画ですが,盗難にあっています。)
そういえば,
あいたた観音もこんな言い伝えがありますよね。
歴博にもレプリカがある
聖観音立像・・・泥棒が盗み出し,金を溶かして取ろうとしたが,失敗し,観音像の腰部を槌でたたくと,観音様の「あいたた」という声が聞こえ,自らの罪を懺悔し,像を返しの来たが,腰部は曲がったままに今に至る・・・という伝承。
それはさておき・・・
(でも,聖観音立像は,色っぽくて美人でした。と言ったら,不謹慎でしょうか。)
本堂や本堂の内陣を再現している新薬師堂も何ともよかったです。
1時間1本のバスをのがし,予定より1時間オーバーして,雰囲気を味わってきました。
さほど人がおらず,ゆっくりのんびり味わえました。
PS.蟇股については,また後日。
もちろん,見てきました。
目的は雰囲気を感じてくること。
そして,
歴博にある太子堂の10分の1模型の実物を見てくること。
歴博の「県立歴史博物館がいざなう ひょうご歴史の旅」によると,
兵庫県に11件の国宝建築があり,そのうち5件は姫路城に関わるもの,
そして,残り6件が平安・鎌倉・室町の寺院建築です。すべて,旧播磨国内にあります。
そのうち2件は鶴林寺。
本堂も国宝ですが,
太子堂は,兵庫県最古の寺院建築で,平安時代後期の天永3(1112年)に建てられたと考えられています。
さて,実物は,模型よりも木の色がちょっとくすんでいます。
「靴を脱いでおあがりください。」ということは,靴を脱いだら上がっていいのだと思い,
靴を脱いで,建物の周囲をぐるっと回りました。
東西1か所ずつ段差があって,建物ばかり見て歩いていたので,降りる方でつまずきました。
上記の本によると,礼拝するための礼堂がつくられていて,身舎(もや)よりも1段低くなっているそうです。
隙間から中をのぞきました。
暗くてよく見えません。
仏像のようなものが少しあったと思います。
その後,いくつかの建物を見て回り
宝物館へ
ここで仰天!!!
太子堂内陣の太子堂壁画(復元模写)と
釈迦三尊像&四天王立像(こちらは本物)
壁画は,平安仏画ですが,煤けて肉眼では見えなくなっています。
昭和51年,赤外線写真によって確認され,重要文化財に指定されています。
それを芸大の人が復元模写し,展示しています。
涅槃図や九品来迎図だけでなく,柱やその他全面に彩色されていて,
何とも言えない・・・,ん・・・。
また,内陣内の仏像も,
仏の世界…って感じがして,
これをそのまま,太子堂内に置けば,さらにすごいだろうと思うのですが,
「警備が・・・」とのことでした。
(実際,ほかの絵画ですが,盗難にあっています。)
そういえば,
あいたた観音もこんな言い伝えがありますよね。
歴博にもレプリカがある
聖観音立像・・・泥棒が盗み出し,金を溶かして取ろうとしたが,失敗し,観音像の腰部を槌でたたくと,観音様の「あいたた」という声が聞こえ,自らの罪を懺悔し,像を返しの来たが,腰部は曲がったままに今に至る・・・という伝承。
それはさておき・・・
(でも,聖観音立像は,色っぽくて美人でした。と言ったら,不謹慎でしょうか。)
本堂や本堂の内陣を再現している新薬師堂も何ともよかったです。
1時間1本のバスをのがし,予定より1時間オーバーして,雰囲気を味わってきました。
さほど人がおらず,ゆっくりのんびり味わえました。
PS.蟇股については,また後日。
もちろん,見てきました。










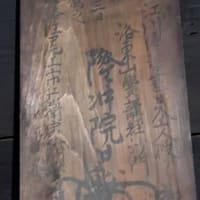














早速調べていただき,ありがとうございます。
よーく考えると,自分でネットで調べることもできるのに,すみません。でも,ひしひしと,地域性を感じます。
私が住む姫路市の網干地区ですが,
網干地区仏教会の資料によりますと,
40の寺のうち,
なんと,浄土真宗25!!
(うち,浄土真宗本願寺派(いわゆる西本願寺)が19,
真宗大谷派(こちらはお東さん)が5,真宗仏光寺派が1です。)
臨済宗妙心寺派は6寺ありますが,曹洞宗はゼロ!です。
姫路市で探せば,また違うのでしょうが,「網干は網干」です。というのは,大河ドラマの「軍師官兵衛」を見ていると,姫路は官兵衛・秀吉側とおもわれるでしょうが,我ら網干は秀吉側と対立した一向一揆側なのです。
さて,pepperpictureさまがおっしゃる了法寺をネットで調べました。
びっくりというか唖然というか・・・50代の私には・・・・です。
でも,以前,『寺院消滅 』鵜飼 秀徳 (著)を読んだのですが,若い人を取り込まないと,お寺は大変ですよね。
私の実家の寺は,たつの市御津町室津にあるのですが,(真宗大谷派)ご住職が最近亡くなられ,後を継ぐ人もなく,隣の相生市のご住職の兼任となりました。
(主人の実家はみなクリスチャンです。)
「守備範囲が広い」といえば,かっこいいですが,あっちもこっちもいい加減なATSUです。
今後ともよろしくお願いいたします。
お寺は実家が日蓮宗で市内にお寺があります。
主人の祖父母のお墓も同じお寺です。
主人とはお見合いなのですが、お見合いするまで会ったことはありませんでした。当時うちの父 は亡くなっていて、主人がお見合いの前に、うちの墓にお参りに行ったのですが、同じ名字もありどこだかわからなかったのです。そして、風もないのに塔婆がカタンと鳴って、そこがうちの墓だった、いうことがありました。
主人側の親戚も同じお寺の方が多いので、主人側の法事とうちの法事が同じ日になり、法事のダブルヘッダーをしたことがあります。
さて、検索して八王子市仏教会があり、お寺の一覧表がありました。
ざっと、数えて全部で130寺、内
曹洞宗38、真言宗30、臨済宗と日蓮宗が16、浄土真宗5でした。
浄土真宗、少なかったですね、
八王子で一番古いのは、ミシュランにも載った高尾山、薬王院。
都内では、浅草寺、628年~でした。
因みに、うちのお寺は「了法寺」といい、若いひとにもお寺に来てほしいとのことで萌え寺です。検索してみてください。ビックリしてしまいます。
古文書も頑張ろうという気持ちは一応あるものの、止まってしまっているATSUです。
pepperpictureさんは、「太子信仰に地域性を感じます。」と書いてくださっていますよね。
私が住んでいるのは、姫路市網干区というところです。お隣は揖保郡太子町などで、私の家から姫路の市役所に行くよりも、太子町役場に行く方がぐっと速いという、姫路市の南西外れです。
太子町は、中世には、鵤荘(いかるがのしょう)という法隆寺領の荘園がありました。だから、聖徳太子なんですね。
最近、「聖徳太子はいなかった。」的なことがよく言われますが、友達は「じゃあ、太子町はどうなるの?」と言っています。(笑)
地域性・・・で関東に住むpepperpictureさんにお聞きしたいのですが、
ある本(『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』)で、平成4年の『宗教年鑑』によると、信者数が一番多いのが曹洞宗、2番目が西本願寺(浄土真宗本願寺派)寺院数も、曹洞宗が一番多いとのことでした。
私が住む地域では、ダントツに多いのが浄土真宗本願寺派です。ブログのどこかに書いたことがあるかもしれませんが、この地域は蓮如たちによる布教の最西端です。
ですから、曹洞宗が多いと言われても、全く理解できません。関東は曹洞宗の信者が多いのですか?
古文書と関係ないことですみません。
古文書解読実践コース
テキストに書き下し文がありません!!
(テキスト文の一部が課題)
解説は詳しいのでそれをヒントに辞書をひきひき、取り組みました。今日こそポストに投函します。
そちらとテレビ番組が違うかも知れませんが、
今日、ニュースゼロ夜11時~
女優の杏さんが古文書?子育て奮闘とあり、気になります。
古文書すごいですね。私は「あと半年、応用コースⅡを頑張ります。」・・・と言いたいところですが、最近、進んでいません。でも、pepperpictureさんのお話を聞くたびに、「ファイト!」と思います。ありがとうございます。
ところで、先日の鳥取の地震の時、関東に住む息子が久しぶりに「大丈夫か?」と電話をくれました。むちゃくちゃうれしかったです。
でも、何も地震対策をしていない自分が恥ずかしいです。私が住む姫路市南西部は、阪神淡路大震災の時も、今回も、震度4という微妙なところで、へんに大丈夫感があるのかもしれません。反省しないといけません。
それにしても、こうして、関東の方とお話をしているということがとても不思議です。インターネットってすごいですね。
また、お越しください。
国文学資料館は米軍の基地が撤退した跡地に公園、裁判所、消防署、防災センター等の公共の建物が建っているところにあります。ここが、立川断層の近くなのです。(周期は三千年に一回)ちょっと心配。
息子さんが東京にいらしてるとは、離れていると何かと心配ですね。
3.11の時は電車が全て止まり、帰宅困難者が子供の通っていた小学校にやってきたそうです。
近所のコンビニやドラッグストアはお握り、パンなどは売り切れ。備蓄用毛布は三階の倉庫にあって高校生男子が運んでくれたそうです。
その後備蓄品は一階の保管になりました。
その時に備蓄用飲料は避難者用は用意しているが、児童の分は備蓄していないことが判明。PTA 会費でペットボトルの水を用意することになりました。
子供の通っていた高校は一年生の時に防災宿泊研修というのがあって、体操着で登校して防災のビデオみたり、炊き出しの練習して、体育館のマットに備蓄用毛布を掛けて就寝しました。
うちは、流行りのミニマリストの逆てすが、お米やレトルト食品、缶詰、ペットボトル飲料など常に多めにストックして、減ったらまた買っておくという、ローリングストック方式というのにしています。まぁ、実際どこにいるときに災害に遭遇するかはわかりませんものね。
国文学資料館は東京以外の博物館のポスターも展示されてます。たつの市博物館、ありましたよ。ATSU さんが見に行かれたのはこれかな?と思いました。
東京は美術館が沢山ありますが、時間とおサイフと相談しながらボチボチ行ってます。
上野で、仏像展とデトロイト美術館展やっているのが気になります。
NHK 学園の古文書をおサイフと相談して、今回は解読コースにしてしまいました。
これから数日内に、第一回の課題を送りますが、応用コースより、評価が厳しくなるのか、ドキドキです。「候」や「ニ」の点みたいのを見逃していないか見直ししました。
それではまた