私が住んでいるのは,兵庫県の瀬戸内海沿岸です。
「瀬戸内海は古くからヒトやモノが行き交い,知識と文化が交流する場であった。」と倉地克直氏は『江戸時代の瀬戸内海交通』(2021.吉川弘文館)の中で述べています。
昨年11月16日,姫路市立城郭研究室で市民セミナー「和船の歴史」を受講しました。
今回は「メモ;和船」と称して,江戸時代の和船について,
石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 (1995年 法政大学出版局)からまとめてみました。




2018年10月撮影 兵庫県立歴史博物館(常設展(現在は展示替えされています。)の大部分は写真撮影可)
和船 石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 1995年 法政大学出版局
18世紀前半期 領主と組んで特権的経営に依存していた初期豪商の衰退
合理的運営を行う廻船仲間組織・・全国各地に排出した小資本の廻船業者が勢力を伸ばす。
比較的低い運賃でも利益を上げる方法
乗組水主の減少
廻船の帆走専用化・・弁才船(べざいせん)が最良の船型・構造
操櫓用の水主(かこ)を不要とする→3割前後減らす
(千石船の場合水主約24人→弁才船は水主約15人)
廻船の大型化←商品流通の増大
安全性 根棚(かじき)・中棚・上棚・除棚などの外板を厚くする 船梁を太くする
上棚の上にハギツケとよぶ舷側(げんそく)板を付加する
太い帆柱
細い材を何本も寄せ集め,責込(せめこみ)と称する鉄のタガで締める,
いわゆる松明(たいまつ)柱が考案
帆と舵(かじ)の改良
筵(むしろ)帆から木綿帆→松右衛門帆(ただし高価なので小廻船や漁船には使わず)
廻船の乗組
船頭 船に乗らない船主を居船頭
船長役を沖船頭もしくは船乗船頭
(船主兼船長役を直乗船頭)
船頭は運行責任者→船鑑札・往来手形・積荷の送状などを持つ書類入れとして懸硯(かけすずり)という入れ物,いわゆる船箪子を持つ
船頭を補佐する三役
楫取(かんとり:航海長役),親仁(おやじ:水夫長),賄(まかない:事務長役)
三役のほかに,平水主,炊(かしき)
海難
浦証文(浦手形,浦状,浦切手)・・海難を証明する唯一の重要書類
海難が発生した際,その場所の浦役人が詳しく状況を調査し,それが不可抗力の海難だったことを確認したうえで船頭に与えるようにしていた。
宛先は損害を受けた荷主や船主
不可抗力であった場合,船頭の賠償責任は問われない。
海難証明のほか,船乗りの不正行為の防止にもなる。
→監視役として,荷主の代理人を乗船させることもある。(奉行,上乗(うわのり))
海難救助→幕府は全国の浦方に義務として課す。
船頭らは,大坂や江戸の廻船勘定書に出頭して,海難の届け出とともに浦証文を提出するとあとで吟味を受けることになっている。
引き続き,読書中
石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 1995年 法政大学出版局
倉地克直『江戸時代の瀬戸内海交通』2021年 吉川弘文館
水本邦彦『海辺を行き交うお触れ書き』2019年 吉川弘文館
「瀬戸内海は古くからヒトやモノが行き交い,知識と文化が交流する場であった。」と倉地克直氏は『江戸時代の瀬戸内海交通』(2021.吉川弘文館)の中で述べています。
昨年11月16日,姫路市立城郭研究室で市民セミナー「和船の歴史」を受講しました。
今回は「メモ;和船」と称して,江戸時代の和船について,
石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 (1995年 法政大学出版局)からまとめてみました。




2018年10月撮影 兵庫県立歴史博物館(常設展(現在は展示替えされています。)の大部分は写真撮影可)
和船 石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 1995年 法政大学出版局
18世紀前半期 領主と組んで特権的経営に依存していた初期豪商の衰退
合理的運営を行う廻船仲間組織・・全国各地に排出した小資本の廻船業者が勢力を伸ばす。
比較的低い運賃でも利益を上げる方法
乗組水主の減少
廻船の帆走専用化・・弁才船(べざいせん)が最良の船型・構造
操櫓用の水主(かこ)を不要とする→3割前後減らす
(千石船の場合水主約24人→弁才船は水主約15人)
廻船の大型化←商品流通の増大
安全性 根棚(かじき)・中棚・上棚・除棚などの外板を厚くする 船梁を太くする
上棚の上にハギツケとよぶ舷側(げんそく)板を付加する
太い帆柱
細い材を何本も寄せ集め,責込(せめこみ)と称する鉄のタガで締める,
いわゆる松明(たいまつ)柱が考案
帆と舵(かじ)の改良
筵(むしろ)帆から木綿帆→松右衛門帆(ただし高価なので小廻船や漁船には使わず)
廻船の乗組
船頭 船に乗らない船主を居船頭
船長役を沖船頭もしくは船乗船頭
(船主兼船長役を直乗船頭)
船頭は運行責任者→船鑑札・往来手形・積荷の送状などを持つ書類入れとして懸硯(かけすずり)という入れ物,いわゆる船箪子を持つ
船頭を補佐する三役
楫取(かんとり:航海長役),親仁(おやじ:水夫長),賄(まかない:事務長役)
三役のほかに,平水主,炊(かしき)
海難
浦証文(浦手形,浦状,浦切手)・・海難を証明する唯一の重要書類
海難が発生した際,その場所の浦役人が詳しく状況を調査し,それが不可抗力の海難だったことを確認したうえで船頭に与えるようにしていた。
宛先は損害を受けた荷主や船主
不可抗力であった場合,船頭の賠償責任は問われない。
海難証明のほか,船乗りの不正行為の防止にもなる。
→監視役として,荷主の代理人を乗船させることもある。(奉行,上乗(うわのり))
海難救助→幕府は全国の浦方に義務として課す。
船頭らは,大坂や江戸の廻船勘定書に出頭して,海難の届け出とともに浦証文を提出するとあとで吟味を受けることになっている。
引き続き,読書中
石井謙治 『ものと人間の文化史76‐Ⅰ 和船Ⅰ』 1995年 法政大学出版局
倉地克直『江戸時代の瀬戸内海交通』2021年 吉川弘文館
水本邦彦『海辺を行き交うお触れ書き』2019年 吉川弘文館













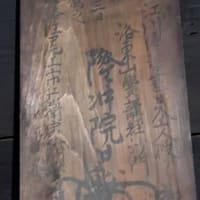











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます