世界遺産「二条城」シリーズ、5回目の今日は清流園と桜をご紹介します。
「清流園」
清流園は面積約5,000坪で池泉廻遊式山水園と、芝生の広場からなっています。
この庭園は高瀬川一之船入のところにあった約300年の歴史を持つ角倉了以(すみのくらりょうい:戦国期の京都の豪商)の屋敷から建物の一部と名園であった庭園の池石約800個をもとに、全国から集めた銘石300個をそれに加え、昭和40年(1965年)に完成したものです。
庭内にはお茶室「和楽庵」や「香雲亭」があります。
「香雲亭」
1965年(昭和40年)、角倉了以(すみのくらりょうい)邸から移築された茶室です。
この「香雲亭」は、茶室「和楽庵」と共に、市民大茶会や国賓公賓の接遇に利用されているようです。
・香雲亭前の伊勢ゴロタ石は洲浜を表現しているそうです。
・本丸庭園から西橋を出た所にある休憩所の前には「八重紅しだれ桜」が咲いていました。
・4月7日に訪れた時にはまだ5分咲き程度でしたが、御覧のように見事な「八重紅しだれ桜」でした。
「北大手門(重要文化財)」
清流園を過ぎると左手に北大手門があります。
二条城への出入り口はこの北大手門と東大手門の2箇所だけで、東大手門は一般の見学者用に使われ、北大手門は主に車輌の出入りに使われているようです。
「築城400年記念、展示・収蔵館」
昭和57年に重要文化財の指定を受けた二の丸御殿障壁画の原画を恒久的に保存するため、二条城築城400年を記念して平成16年3月に竣工し、平成17年10月10日に開館しました。
展示室では、二の丸御殿障壁画に関する資料や錺金具(かざりかなぐ)、城内から発掘された埋蔵文化財も展示されています。
・庭園のソメイヨシノやヤマザクラは丁度見ごろとなっていました。
9日からご紹介してきました京都御所と二条城シリーズは今日で最終となります。
明日からは家庭菜園や一般的な話題を取り上げる予定です。
世界遺産「二条城」の4回目は本丸御殿と天守閣跡をご紹介します。
「本丸御殿」
内堀に囲まれた部分の16,800㎡(約5,200坪)を本丸と呼び、創建当時の本丸御殿は、二の丸御殿に匹敵するくらいの規模を持っていたそうです。
しかし、天明8年(1788年)の市中の大火のため殿舎が焼失し、その後、永らく御殿の再建はされず、幕末になって第15代将軍徳川慶喜の住居として本丸御殿が建てられましたが、明治14年に撤去されました。
現在の本丸御殿は、京都御苑今出川御門内にあった旧桂宮御殿を明治26年(1893年)に移築したものです。
この旧桂宮御殿は京都御所にあった当時、仁孝天皇(にんこうてんのう)の皇女和宮が14代将軍徳川家茂に嫁がれる前に約1年8カ月住まわれた建物であり、孝明天皇(こうめいてんのう)の仮皇居に使用された由緒深い建物だそうです。
・本丸御殿です。
「天守台」
本丸の西南の隅に、本丸庭園を挟んで天守閣跡があります。
・高くなっている石垣が天守閣跡です。
天守台の石垣の高さは約21m、上敷地は445㎡あります。
・天守台への階段です。
ここにそびえていた天守閣は、1626年(寛永3年)に当時廃城だった伏見城の5層天守が移築されたものです。
しかし、1750年(寛延3年)落雷によって焼失し、その後は再建されることはありませんでした。
・445㎡ある天守台の敷地です。嘗てはここに5層の天守閣がそびえていました。
・天守台から眺める本丸御殿です。
・天守台からは「大文字山」も見えます。
「本丸庭園」
現在の本丸庭園は、明治28年(1895年)5月23日、明治天皇が本丸に行幸された時、枯山水風庭園の改造を命じて、明治29年(1896年)に完成した芝庭風築山式庭園となっています。
・天守台下り階段からの庭園の木々です。
世界遺産「二条城」の3回目は本丸の「櫓門」と「石垣」をご紹介しますが、その前に、昨日ご紹介した「二の丸庭園」の補足説明をしておきます。
「二の丸庭園」
二の丸庭園は大広間の西、黒書院の南に位置し、主として大広間からの観賞を想定して造られていますが、寛永3年の後水尾天皇の行幸の際、行幸御殿が庭園の南側に建造されたことから、南方からの観賞も配慮して庭園南部の石組に変更を加えたようであり、その形跡が見られるそうです。
・こちらは昨日の続き「二の丸庭園」です。
・庭園の外れにはこんな樹木がありました。人の顔のようにも見えますが、皆さんは何に見えますか?
・本丸を囲んでいる内堀です。
・本丸への入口、東橋と櫓門です。
・櫓門を入ると本丸の城石が迎えてくれます。
・本丸庭園側からの櫓門です。
世界遺産「二条城」の2回目は「唐門」と「二の丸庭園」をご紹介します。
「唐門(からもん)」
唐門は二の丸御殿への正門で、御殿の南側に位置しています。桃山時代末の慶長7年から8年(1602年~1603年)に建造され、寛永2年から3年(1625年~1626年)の改修で現在の姿となりました。
国の重要文化財に指定されており、前後は唐破風(からはふ)、側面が切妻造、桧皮葺(ひわだぶき)の四脚門です。
・彫刻には、牡丹に蝶、龍虎、唐獅子など極彩色の彫刻がふんだんに使われています。
「二の丸御殿」
二の丸御殿は二の丸の中心的な建造物で、周囲を築地塀(ついじべい)で囲まれており、南側の「唐門」が入口となっています。
唐門を入ると正面に二の丸御殿の玄関である車寄があります。
御殿に入ると、順に「遠侍の間」、「式台の間」、「大広間」、「蘇鉄の間」「黒書院」「白書院」と6つの建物が廊下で繋がり一体の建物になっています。
南西側には小堀遠州の代表作となっている日本庭園「二の丸庭園(八陣の庭)」があります。北東側には、「台所」と配膳のための「御清所」があります。
(参考)八陣とは、中国の兵法で8種類の陣立てのことです。
なお、これらの建物は撮影禁止なのでご紹介することができませんが、いずれも国宝や重要文化財に指定されている貴重な建造物です。
・国宝・・・・・・・・・・・・・・・・「車寄」「遠侍の間」「式台の間」「大広間」「蘇鉄の間」「黒書院」「白書院」
・国の重要文化財・・・・・・「唐門」「築地塀」「台所」「御清所」
・国の特別名勝・・・・・・・・「二の丸庭園」
・二の丸御殿と車寄です。 
二の丸御殿の玄関「車寄」です。
「二の丸庭園」
「二の丸庭園」は池を中心とした書院造り庭園です。
「二の丸庭園」には、三つの島を置き、四つの橋を架け、西北隅に滝を落とし、池の汀(みぎわ)に多くの岩石を配しており、その景観は秀麗で豪壮な趣がある庭園となっています。
美しい「二の丸庭園」です。
「二の丸御殿」の前の庭園です。
「釣鐘」
この鐘は幕末の政変時期、二条城と北側の所司代との連絡に使われたものです。
鐘は二条城と所司代に設置され、非常時に備え使用されたもので、幕末には薩摩・長州など朝廷側の動向に備え鳥羽伏見の開戦など、非常時の連絡を告げ、住民にも知らせるために鳴らされたそうです。
京都御所の参観を終えた私たちは、御所から1キロ余り南西の方向に位置する「二条城」を見学することにしました。
「二条城」は世界遺産に登録されている歴史的建造物の一つです。
今日から数回に分けて世界遺産「二条城」をご紹介します。
「旧二條城跡」
京都御所から徒歩で二条城へ向かう途中の、京都市上京区烏丸下立売(武衛陣町)に、「旧二条城跡」の石碑がありました。
ここには、遺構などは無く、「旧二條城跡」と書かれた石柱碑と説明板があるだけです。
説明文によれば、1569年(永禄12年)に織田信長が、室町幕府第15代将軍 足利義昭の将軍座所(居城)として、約390メートル四方の敷地に70日間で、四方に石垣が高く築かれ、二重の堀や三層の天守閣を備えた平城を築きました。
周辺からは金箔瓦も発掘されており、短期間での築城のわりに豪華な城郭であったと推測されています。
その後、織田信長はこの旧二条城から足利義昭を追放し、東宮 誠仁親王(さねひとしんのう)を迎え入れ、城は「二条御所」として利用されましたが、室町幕府の滅亡とともに廃城になりました。
1576年(天正4年)に旧二条城は解体され、安土城の築城のための建築資材として再利用されました。
「二条城」
「二条城」の正式名称は「元離宮二条城 」と言い、古都京都の文化財を構成する17の歴史的建造物の一つとして、1994年(平成6年)12月に世界文化遺産に登録されていますが、このお城は慶長8年(1603年)、徳川家康が京都御所の守護と将軍上洛の際の宿所として築城されたものです。
その後、伏見城の遺構を移すなどして、3代将軍徳川家光が寛永3年(1626年)に今の形に完成しました。
以来、大坂冬の陣、夏の陣ではここから出陣するなど、幕府の重要な拠点となり、家康と豊臣秀頼との会見場所にもなりました。
幕末の慶応3年(1867年)には最後の将軍となった15代将軍徳川慶喜が二の丸御殿大広間において大政奉還を宣言し、政権は朝廷に返され、265年にわたる江戸幕府はここで幕を閉じました。
その後、明治維新を迎え、二条城は宮内庁の所管となり、『二条離宮』と改称されたそうです。
・二条城全図です。
「東大手門」(国の重要文化財)
東大手門は、二条城の正門で、江戸時代前期の1662年(寛文2年)に造られました。
屋根は、本瓦葺、入母屋造りとなっており、形式は櫓門で石垣と石垣の間に渡櫓を渡し、その下を門としています。
・世界文化遺産への登録の証です。
・「旧二条離宮」の石碑が立っていました。

・西築地塀です。五筋の白線をつけた薄い泥色の壁で、これは塀として最高の格式を示すものだそうです。
「京都御所」春季一般公開の参観シリーズ6回目の今日は「御涼所」、「御三間」と庭園をご紹介します。
「御涼所(おすずみしょ)」
御涼所(おすずみしょ)は、天皇の夏季の納涼のための御座所として使われた建物です。
東からの風を受けるために東面が広く造られ、奥には茶室を備えています。
「御三間(おみま)」
「御三間」は、上段、中段、下段の三間よりなる建物で南と西に御縁座敷があります。
ここでは涅槃会(ねはんえ)、茅輪、七夕や盂蘭盆(うらぼん)などの内向きの行事が行われました。
・上段の間の襖絵で、住吉弘貫(すみよしひろつら)の朝賀図です。
・中段の間の襖絵で、駒井孝礼(こまいこうれい)の賀茂祭群参図(かもさいぐんさんず)です。
・下段の間の襖絵で、岸誠(がんせい)の駒引図です。
・出口付近の庭園です。参観した4月7日は桜が満開でした。
・同じく出口付近の庭園のしだれ桜です。
「清所門」
清所門(せいしょもん)は一般公開の出口になります。
この門は普段から皇宮警察が門番として常駐しています。
「京都御所」の一般公開参観シリーズは今日で最終となります。
明日からは世界遺産「二条城」をご紹介します。
「京都御所」参観シリーズ5回目は、御学問所と御常御殿、御内庭をご紹介します。
「御学問所」
御学問所は御読書始めの儀、和歌の会など学芸関係の他、臣下と対面される行事などにも用いられました。
建物は入母屋桧皮葺の書院造となっています。
・御学問所の中断の間にある襖絵です。筆者は岸岱(がんたい)で「蘭亭ノ図」です。
「御常御殿」
京都御所のなかで一番大きな建物が「御常御殿(おつねごてん)」です。
天皇の日常のお住まいとして使用された御殿で、古くは仁寿殿(じじゅでん)を常御殿とされ、その後、清涼殿が永く常御所となっていましたが、16世紀末以降、清涼殿から独立して建てられました。
御常御殿は、日常生活に便利なように書院造の様式になっており、内部は15室からなる書院造の建物だそうです。
・御常御殿です。前方は御三間です
・御常御殿の襖絵です。
・右は東御縁座敷の襖絵です。筆者は岡本亮彦(おかもとすけひこ)で「曲水の宴(えん)」です。
・「御常御殿」中段の間の襖絵です。筆者は鶴沢探真で「大禹戒酒防微図(だいうかいしゅぼうびず)」です。
・「御常御殿」下段の間の襖絵です。筆者は座田重就(さいだしげなり)で高宗夢賚良弼図(こうそうむらいりょうひつず)です。
・御内庭です。
「京都御所」参観シリーズ4回目は、清涼殿と小御所、御内庭をご紹介します。
「清涼殿」
清涼殿は平安時代には天皇が日常生活の場として使用された御殿です。
建築様式は、入母屋、桧皮葺(ひわだぶき)の寝殿造りとなっています。現在の建物は平安時代のものより小さくなっていますが、古生制に則って建てられているそうです。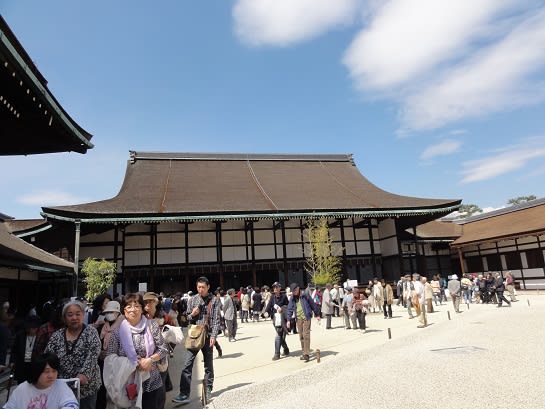
「清涼殿(滝口)」
この滝口には、昔、警護の武士が控えていた所で、それより清涼殿を警固する人を「滝口の武士」と言うようになりました。
「小御所」
小御所は御元服御殿ともいい、寝殿造りと書院造の両要素が混合した様式の建物です。
ここでは、東宮御元服、立太子の儀式、皇太子の儀式など、諸種の儀式が行われ、武家との対面にも用いられました。
1867年(慶応3年)12月9日の王政復古の大号令が発せられた日の夜、「小御所会議」がここで行われました。
・小御所の下段の間の襖絵です。
「小御所の南面」
「小御所の蹴鞠の庭」
小御所と御学問所の小庭を言います。
蹴鞠は鹿皮で出来た鞠を落とさずに蹴り渡す球戯で、一定の作法のもとに行われます。この場所で催される蹴鞠を天皇がご覧になったそうです。
「御池庭」
池を中心とした回廊式庭園です。
前面は州浜で、その中に舟着きへの飛び石を置いています。右に欅橋が架かり、対岸には樹木を配し、様々な景色を楽しむことが出来ます。
「御内庭」
曲折した遣り水を流して、土橋や石橋を架けた趣向を凝らした庭で、奥に茶室を構えています。
「京都御所」一般公開の参観記シリーズ3回目の今日は、「春興殿」から「紫宸殿」までを参観順路に沿ってご紹介します。
「春興殿」
「春興殿」は紫宸殿の東に位置しています。ここは天皇継承のしるしである三種の神器の内、御鏡を安置するところですが、現在は、御鏡は東京の賢所にあって、即位の大礼を行う時ここに移御し、奉安されます。
現在の建物は、大正天皇の即位の折りに造られたもので総檜造り、銅葺き入母屋屋根の御殿で、内部は外陣、内陣、内々陣の三つよりなっており、内陣は天皇御拝の位置となっています。
神鏡を奉安する所は内々陣だそうです。
「承明門(じょうめいもん)」
「承明門」は、紫宸殿の前面にあって、築地塀の諸門と異なり、朱色の円柱を用いた瓦葺の中国風の門です。大きさは、五間、三戸、十二脚門となっています。
この門は、天皇行幸、並びに上皇御譲位の後の出入りに用いられます。また、恒例、臨時の節会、その他、御即位、御元服、立后、立太子など厳儀の際この門を開きます。
写真では見えませんが、中央の正面に岡本保誠の「承明門」の額が掲げられています。
・朱色が鮮やかな「承明門」です。奥の御殿が紫宸殿です。
「日華門」
「日華門」は、紫宸殿の南庭の東側にあり、「承明門」と同様、朱色の円柱を用いた瓦葺の中国風の門です。内裏を構成する内閤門のうちの一つです。
「紫宸殿」
「紫宸殿」は、即位礼などの重要な儀式を行う最も格式の高い正殿です。大正天皇、昭和天皇の即位礼もここで行われました。
建築様式は入母屋、檜皮葺(ひわだぶき)の高床式宮殿建築で、南面して建てられており、中央に天皇の御座「高御座(たかみくら)」、その東に皇后の御座「御帳台(みちょうだい)」が置かれています。
現在の高御座と御帳台は、大正天皇の即位礼に際して造られたものです。
・天皇の御座「高御座(たかみくら)」です。不鮮明なので、下に参考画像を掲載します。
(参考)
・これは平城遷都1300年祭のときに大極殿に作られた実物大の「高御座(たかみくら)」です。
・皇后の御座「御帳台(みちょうだい)」です。
・「紫宸殿」と軒廊(こんろう)です。「紫宸殿」の前面には白砂の南庭が広がり、東側に「左近の桜」、西側に「右近の橘」が植えられています。
「左近の桜」と「右近の橘」の由来
「左近の桜」と「右近の橘」は、平安宮内裏の紫宸殿(南殿ともいう)の前庭に植えられている桜とタチバナのことで、左近・右近は左近衛府(さこんえふ)・右近衛府(うこんえふ)の略称です。
平安時代以降の儀式の時、左近衛府の官人は紫宸殿の東方に、右近衛府の官人は西方に列して陣をしき、ちょうどその陣頭の辺に植えられているのでこの名があるそうです。
「左近の桜」は、元は梅であって、794年の平安遷都のとき桓武天皇によって植えられましたが、960年の内裏焼亡の際に焼失し、内裏新造のとき、梅に代えて重明親王(しげあきらしんのう)の家の桜を植えたものだそうです。
また、「右近の橘」は平安遷都以前、そこに住んでいた橘大夫という人の家に生えていたものといわれています。
・「紫宸殿」の東側に植えられている「左近の桜」です。
・「紫宸殿」西側に植えられている「右近の橘」です。防霜のため覆屋が設置されていました。
今日予定していた「京都御所」参観記シリーズの3回目は、急遽明日に変更させていただきます。
代わって、私が住まいしている大阪南部・熊取町山の手台のボランティアグループ、 “フラワー山の手” が主催する「ふれあい喫茶」の模様をご紹介します。
“フラワー山の手”は、山の手台住宅地内の老人施設や公園、遊歩道などにお花を植栽して、住みよい環境を作ろうと活動している山の手台のボランティアグループです。
「ふれあい喫茶」の催しはこの“フラワー山の手”が主催して、地域住民とふれあい、親睦を図るものです。
・「フラワー山の手ふれあい喫茶」が催された山の手台5号公園です。今年は桜の満開と重なり、差し詰め「お花見喫茶」と言ったところでしょうか。
「ふれあい喫茶」ではメンバーの人達が手作りしたおにぎりやケーキ、飲み物、お花や手作り籠などを安価で提供しています。
今年はその売上金の全額を東日本大震災の義援金として寄付することにしています。
・桜の花の下で、手作りの食べ物、飲み物、ケーキ、蔓で編んだ籠やお花などを販売している売店風景です。
今年のイベントには、東日本大震災の義援活動に協賛して頂いた地元のフラダンスチームも特別に参加していただき、お歳に似合わぬ柔らかな踊りを披露していただきました。
好天に恵まれた昨日の日曜日は、ふれあいの場に相応しく、子供からお年寄りまでの大勢の住民の方達が参集され、過去最高の参加者となったようです。
参加された人たちは、満開の桜を愛でたり、色鮮やかなコスチュームを纏ったフラダンスの艶やかな踊りを堪能していました。
また、机上に置かれている義援金箱には、子供からお年寄りに至るまで進んでご寄付をされていました。
・並べられた手作りの籠やお花です。
・食べ物はこのようなメニューで販売していました。
・準備中のメンバーの方達です。
・おにぎりの詰め合わせです。
・美味しそうな手作りケーキです。
・販売風景です。
・イベントに協力して頂いたフラダンスの演奏を担当したカルテットです。
・お歳に似合わぬ柔らかな踊りを披露されたフラダンスチームです。
・見事なフラダンスでした。









