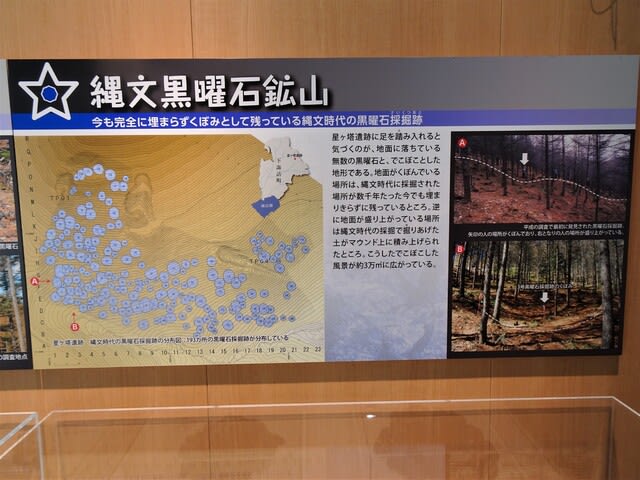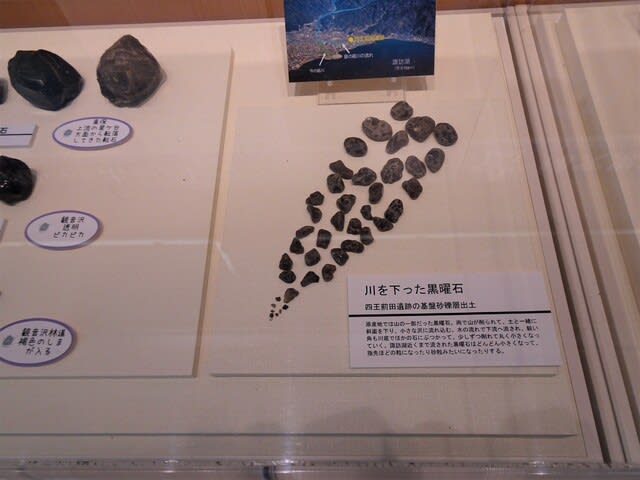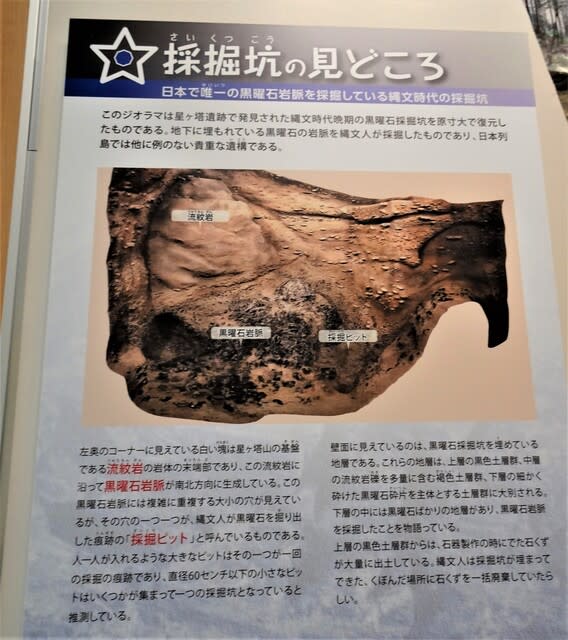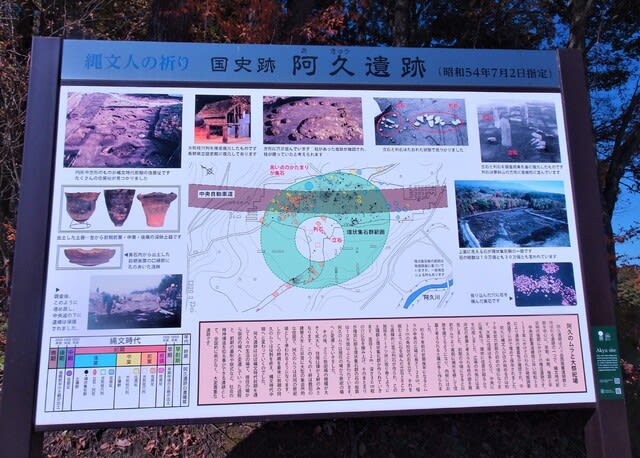辰野町の商店街は「トビチ商店街」と銘打っています。空き店舗があって、開いているお店がトビトビになっているからです。その商店街の空き店舗を使ってアート制作と展覧会が実施されていました。「信州アーツカウンシル」の運営で、この団体は地域の文化芸術活動の担い手を支援しています。



空き店舗の様子とそこに展示されていた作品たちです。この建物は元は洋装店だったようです。





飯田線の踏切の近くにあった空き店舗(元は文房具屋さん)にはタイルのオブジェがありました。






こちらのお店にはショーウインドーの中に何やら怪しい骸骨がいました。



こちらは古い住宅のようでした。畳敷きのお部屋に古道具を使った作品が展示されていました。





こちらは古い倉庫…中には古布などを題材にした作品が展示されていました。





こちらは懐かしい風情の建物…中ではミニチュアの部屋などが展示されていました。






こんな倉庫や辰野町のマンホールの蓋(蛍と福寿草)を見ながら歩きました。


こちらは元ミシン屋さんだったようです。デッサンや写真の作品の展示がありました。





古い商店街の建物とアートに触れたひと時でした。この日は実家で柿もぎをし、辰野美術館とクラフト市を訪れ、その後で街中の「トビチ美術館」を歩きました。歩数は5238歩でした。そして夕食後の夜なべ仕事に130個の柿の皮むきをしました…