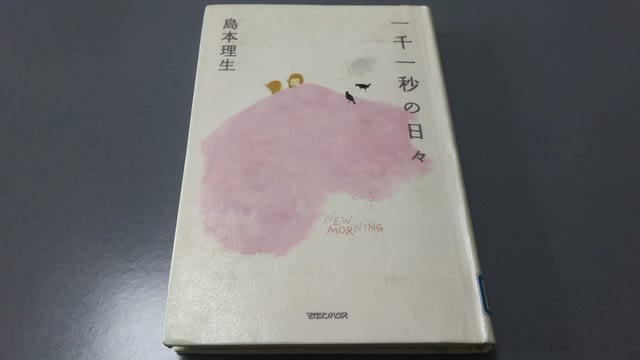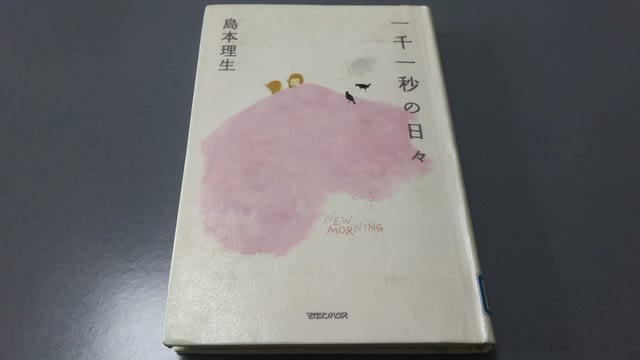
今回ご紹介するのは「一千一秒の日々」(著:島本理生)です。
-----内容-----
仲良しのまま破局してしまった真琴と哲、メタボな針谷にちょっかいを出す美少女の一紗、誰にも言えない思いを抱きしめる瑛子――。
不器用な彼らの、愛おしいラブストーリー集。
-----感想-----
この作品は最初にある人の話が描かれ、次にその人とつながりのある他の人の話が描かれるという形の連作恋愛小説です。
発売されたのは2005年で、島本理生さんが22歳になる年の作品です。
「風光る」
語り手は東京に住む大学生の真琴で、哲という人と付き合っています。
哲とは同い年で、高校生の時にバイト先で出会い4年付き合っています。
哲は高校を卒業してパソコン関係の会社に就職しました。
ある日哲から次の土曜日に遊園地に行こうと言われます。
翌日大学で友達の瑛子にそのことを言うと、「最近ずっと哲君が無気力だとか、まだ若いのに日曜日のお父さんみたいだとか文句を言っていたから、それは良いことなのでは」と言われます。
しかし真琴は不安を感じているようでした。
土曜日になり真琴はお弁当を作ります。
「お弁当を作るなど、さらにそれを持って出かけるなど本当にひさしぶりのことだった。」とあり、付き合っていても最近はそういったことがなくなっているのが分かりました。
遊園地に向かう電車の中で、真琴は向かい側に座っている赤ちゃん連れの夫婦が仲良く笑っているのを見ながら、旦那さんの左手を見て
「旦那さんまでちゃんと左手の薬指に結婚指輪をしているのは珍しい」と思います。
これは哲に愛されているのか不安になっている真琴と哲の関係との対比になっている気がしました。
二人は倦怠期に見えますが仲は良く、遊園地では楽しく話していました。
しかし哲がジーンズのポケットから携帯電話を取り出して誰かにメールをする場面で、「私はそちらを見なかったふりをして歩き出した。」とありました。
これは「私といる時は携帯より私を見ろ」ということだと思います。
ただし哲はそのくらい良いだろうと思っていて、ここに二人の意識のずれがあると思いました。
そして二人は破局します。
哲の気持ちが薄れたのが原因だと思いますが、真琴の気持ちも薄れていました。
遊園地で二人きりでいる真っ最中に、だれにメールを送っていたのかと責め立てたい気持ちもあふれ出す手前でどこかへ流れた。
あの場面は真琴の気持ちが薄れていることを表してもいたのだなと思いました。
「七月の通り雨」
真琴の友達の佐伯瑛子が語り手です。
瑛子は大学の劇団の千秋楽の演劇の後、観に来ていた三年の遠山宗一から付き合って下さいと言われます。
瑛子は断りますが遠山はめげず持ってきた花束を渡し、今度食堂で一緒にご飯でも食べましょうと言い去っていきます。
瑛子は真琴と大学のすぐ裏のビルの地下にある「蜂の巣」というダイニングバーに行きます。
瑛子が哲のことを聞くと、哲は真琴の部屋にある荷物を片付けに来ると言っていましたが音沙汰無しになっていました。
そして何と、哲の前に付き合っていた加納という人に頼んで荷物を運ばせていました。
加納とは別れた後もたまに連絡を取り合っているとのことですが、これは運ぶ加納も受け取る哲も気まずいのではと思います。
瑛子は子供の時から人付き合いが苦手でしたが、そんな中で高校のクラスメイトでもあった真琴とは唯一の親友になりました。
昼休みに真琴と食堂へ行くと、「今度、食堂で一緒にご飯でも食べましょう」と言っていたとおり、遠山が待っていました。
遠山は今度の日曜日に有名な劇団の演劇を見に行かないかと言います。
遠山はドイツ文学の翻訳家を目指していてヘルマン・ヘッセが好きとのことで、真琴がそれなら瑛子にぴったりだと言うと、瑛子は「べつにヘッセの話だったら真琴が相手でもできる。わざわざ彼とする必要はない」と投げつけるように言います。
この時真琴は笑っていましたが、これは真琴が瑛子の性格を知っているから大丈夫だったのだと思います。
他の人だと無愛想な言葉に気を悪くするかも知れず、子供の時から人付き合いが苦手だったというのが表れた場面だと思います。
瑛子は遠山と話している時、嬉しいのに仏頂面で愛想のないことを言ってしまいます。
とても不器用だと思いました。
しかし遠山はそれを真琴と同じように無愛想ではなく不器用と認識できる人なので、こういう人がそばにいてくれると良いのではと思いました。
ただ瑛子は同性の真琴のことが好きで愛情を持っています。
瑛子は足を怪我して遠山と演劇を観には行けませんでしたが、治った翌週に新宿に出掛けます。
途中で雨が降りビルに逃げ込んだ時の描写は興味深かったです。
エレベーターのドアの前で立ち尽くしたまま、次第に早送りされていくような路上の風景を見ていた。
これは雨が降って人が早足になるのと、雨自体が強くなって勢いよく降ると降り出した時より早送りのようになるということだと思います。
ここで瑛子は自身が同性にも愛情を抱くことがあるのを打ち明けます。
遠山はそれでもなお付き合いたいと言います。
この二人にはぜひ続いてほしいと思ったので最後良い雰囲気で終わって良かったです。
「青い夜、緑のフェンス」
真琴と瑛子が行くダイニングバー「蜂の巣」でアルバイトをする針谷という人が語り手です。
真琴、瑛子、遠山が三人で来る場面があり、瑛子と遠山が順調に続いているのが分かりました。
深夜3時近く、針谷がお店の片付けを終えて外に出ると、一紗(かずさ)という中学からの知り合いが待っていました。
大学の友達と飲んでいたら遅くなったから一緒に帰ろうと言われ、針谷は一紗をマンションまで送っていきます。
次の日一紗が今度は針谷のアパートに来ます。
別れた男がマンションの前で張っていて帰れないから寄らせてもらったと言っていて、何かと針谷を振り回す人だなと思いました。
一紗に連れ出されてプールに行った帰り、二人並んで歩いている時の描写は印象的でした。
濡れた髪をぬるい風にさらしながら、一紗はさきほどから無表情で歩いている。冷やされた体がふたたびぼうっと外側から暖められていくのを感じた。
二文目が印象的で読んでいてはっとしました。
こういう表現を見ると島本理生さんはやはり純文学系の作家さんだと思います。
一紗は横暴なようでいて針谷をとても気にかけています。
そしてある時、針谷のことが好きだと言いますが針谷は自身がとても太っていることに引け目を感じていて、こんな太っている奴と付き合うなと諭します。
その時一紗が流した涙はとても印象的で、自身の告白が針谷本人の口から「こんな太っている奴と付き合うな」と言わせてしまったことに愕然としているように見えました。
普段一紗が針谷に暴言ばかり言っているのとは言葉の重みが全く違うのを感じたのだと思います。
後日、一紗がお店にお客としてやってきます。
すると激怒した男が現れ一紗に突っかかります。
一紗が男を振ったのですが男は納得がいかないようで追いかけてきました。
針谷が割って入り、殴りかかろうとする男に凄いことを言います。
「いいけど僕、0.1トン以上ありますよ。失礼ですけどお客様の体重は見たところ70キロないですね。この体重の差だと、殴っても突き飛ばしても、おそらくこちらが倒れることはないでしょうね」
ここで体重を使っていたのはとても良かったです。
体重のことで気まずくなっていた雰囲気が一気に吹き飛び、楽しい雰囲気になって物語が終わりました

「夏の終わる部屋」
針谷の友達の長月が語り手です。
長月は大学生の飲み会で永原操(みさお)と知り合います。
長月が針谷の部屋に寄ると一紗も居て、操は一紗の大学の後輩だと分かります。
操は普段は朗らかに話しますが、腕に何か傷のようなものがあるのを聞かれた時に露骨に聞かれるのを嫌がる反応を見せます。
さらに飲み会で操と一緒に居た西島ちえみから電話が来て出ると操は「どうして西島さんと仲良くしてるの」と激怒します。
その直後には泣き出してしまい、かなり情緒不安定な印象を受けました。
ある日、長月の親戚が亡くなり、一度福岡に帰ることになります。
長月がふと「そういえば、操も夏休みが終わる前に一度くらい家に帰ってみたら」と言うと操は「帰る必要なんかないわよ」と露骨に嫌がります。
操は自身に何かと干渉する父親が嫌いで、家の話をしたことで操と長月は険悪な雰囲気になります。
操は西島ちえみから電話が来た時に激怒していたのに、自身は他の男とも付き合っています。
長月がそのことに気づき別れようと言うと操は待ってくれと言います。
言動が支離滅裂で、わけの分からない人でした。
たぶん自身の生きる場所を確保したくて必死だったのだと思います。
ただしその必死さは周りを振り回し過ぎで、同じ振り回すのでも自身が振り回していることをきちんと自覚していた一紗と大きな違いがあると思いました。
「屋根裏から海へ」
真琴が以前付き合っていた加納が語り手です。
加納は中学二年の弥生という子の家庭教師をしています。
ある日の家庭教師の帰り道、酒屋に買い物に行く弥生の姉の沙紀と一緒に歩いていて、真琴の話になります。
「まだ彼女のことが好きなの」と聞かれた時に「恋愛感情というよりは、家族的な愛情に近い」と言っていましたが、その時の答え方がとても理屈っぽいのが印象的でした。
沙紀の彼氏の秋人(あきひと)は他にも付き合っている人がいます。
沙紀が「相手の女の子が一人ならくじけたかもしれない。だけど複数だったら、結婚する自分が一番強いからなんとかなるんじゃないかって錯覚するでしょう」と言うと加納は「しません」と即答します。
その答え方を沙紀は「君って学校の先生みたい」と言っていて、これはそのとおりだと思いました。
加納と真琴は高校の同窓会に行きます。
瑛子は「会いたい人は特にいないから行かない」と言って欠席しました。
二人は二次会を早めに抜け出しダイニングバー「蜂の巣」に寄ります。
真琴が自身のことを「人前で格好悪い姿は見せたくない」と言うと、加納が「だから君はあの時も」と言っていて、何のことか気になりました。
付き合っていた時のある日、不仲になっていた両親の口論に気を取られて、家に来た真琴をろくに話も聞かずに帰してしまいます。
その日真琴は祖母が亡くなっていて、後からそれを知った加納はとても後悔します。
そこから上手くいかなくなり別れたとありました。
別れて以来久しぶりに真琴が加納の家に遊びにやってきます。
加納が自身の物の見方について「分かってるように見えて、本当は全然分かっていなかったり、それに分かっていても外側から見ようとするばかりで、自分の感情で動いたり衝動に任せたりすることはできない」と言うと、真琴が良いことを言います。
「べつにいいじゃない。だいたい衝動的で感情的なんて、そんなの加納君じゃないよ。もともとの性格っていうものがあるんだから、なにも感情を剥き出しにすることばかりが人間的なわけじゃないよ」
「もともとの性格っていうものがあるんだから」が印象的で、真琴が加納の性格を尊重してくれているのが分かりました。
「新しい旅の終わりに」
再び真琴が語り手です。
秋になり、真琴は旅行に行く加納と一緒に栃木の温泉に行くことになります。
栃木に向かう車の中で、加納に哲の荷物を運んでもらった時の話になります。
次の会話は特に印象的でした。
「まるで今でも哲君がすぐそばにいるような話し方をするんだね」
「気がつかなかった。たぶん、あまりに長く一緒にいたから、空気みたいな存在になっていたんだと思う」
空気みたいな存在とあり、真琴にとってはそばにいるのが当たり前の存在になっていたのだと思います。
失恋からしばらく経っても無意識のうちに哲の存在を感じていることを気にする真琴に、加納は「いくらでも話したいことを喋ってくれて良い」と言い、理屈っぽさだけではない包容力の大きさを感じました。
私はこの二人にまた付き合ってほしいと思いました。
鬼怒川の渓流沿いの旅館に到着して温泉に入った後、浴衣姿で二人並んで夕暮れの外を歩きます。
虫の鳴き声は二人の背丈を楽々と越えて夜空まで響いている。遠くの山のほうからさざ波のように押し寄せる葉の音。
これは良い表現だと思いました

秋の山沿いの地域はまさにこのような雰囲気になると思います。
都会の喧騒がなく、虫の鳴き声と風に揺れる葉の音の風情に心が澄みます

「夏めく日」
高校時代の瑛子が語り手です。
夏休みの少し前、遅くまで教室に残って数学の宿題をしていると石田という29歳の男性教師が現れます。
石田は同じ高校の片倉先生と結婚するため間もなく異動になります。
瑛子は「どうして先生のほうがいなくなるかなあ」と呟き、石田がいなくなるのを残念がっていました。
石田に付いていった図書室で瑛子が雨が降っているのを見て「なかなかやまないですね」と言うと、石田が「そういう他愛ないことを言うときでも、おまえはちゃんと敬語なんだよな」と言う場面があります。
さらに「最近は教師相手にみんな平気でタメ口だからなあ」と言い、「逆に言えば、そういうところがよそよそしいというか、教師と生徒の距離を感じてなんとなく淋しくもあるんだけどな」とも言います。
その後瑛子がいきなり「抱きついていいですか」と言い石田を驚かせます。
すると瑛子は「距離を縮めるために言った」と言い、どうやら石田に教師と生徒の距離を感じると言われたため縮めようとしたようです。
ただし縮め方がとても不器用で、いきなり抱きついて良いかと言われたら戸惑うと思います。
そして瑛子は実は石田のことが好きで、その思いをぶつけます。
石田は断りますが勇気を出した瑛子の気持ちは汲んであげていて、思いやりのある人だと思いました。
この作品は最後、瑛子の心の醜い部分も見えました。
こんなことをしているようでは石田の婚約者の片倉先生には到底勝ち目はなかったのだと思います。
作品タイトルにある「一千一秒」は大きい数に見えますが単位が秒なので長い時間ではないです。
後ろに「の日々」とあるので、日々過ぎていく時間は長いようで短いということかなと思います。
良い終わり方になった物語もそうではなかった物語も、その人の長い人生の中ではわずかな時間なので、その先の人生がぜひ明るくなることを願います。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方は
こちらをどうぞ。
※図書ランキングは
こちらをどうぞ。