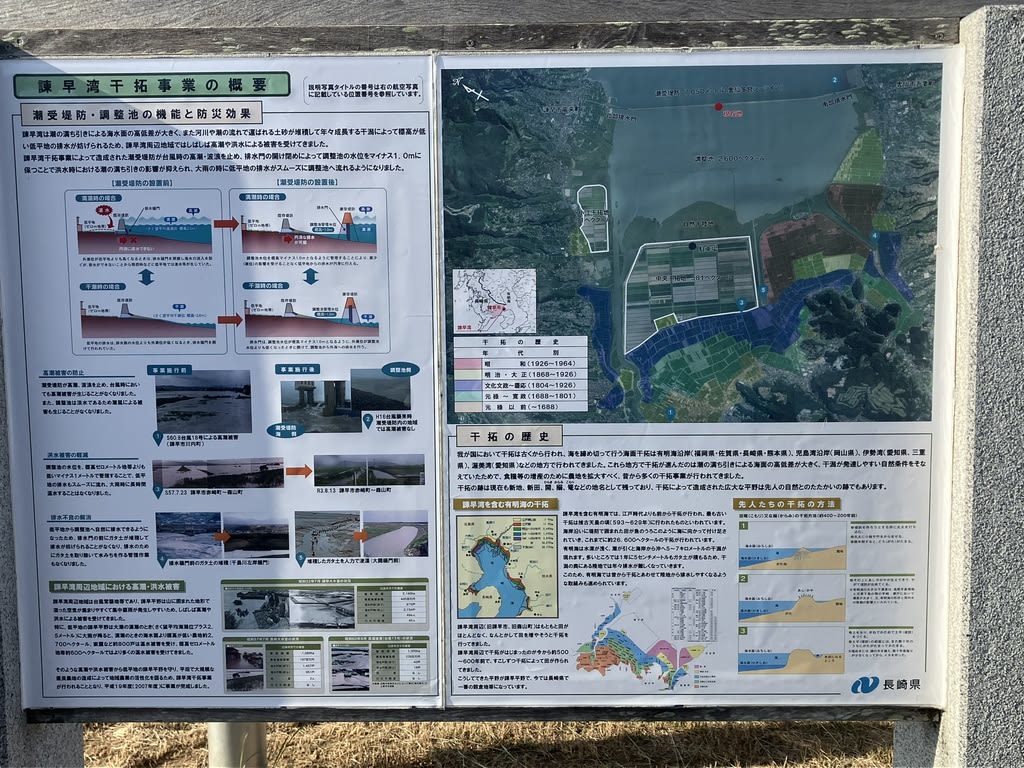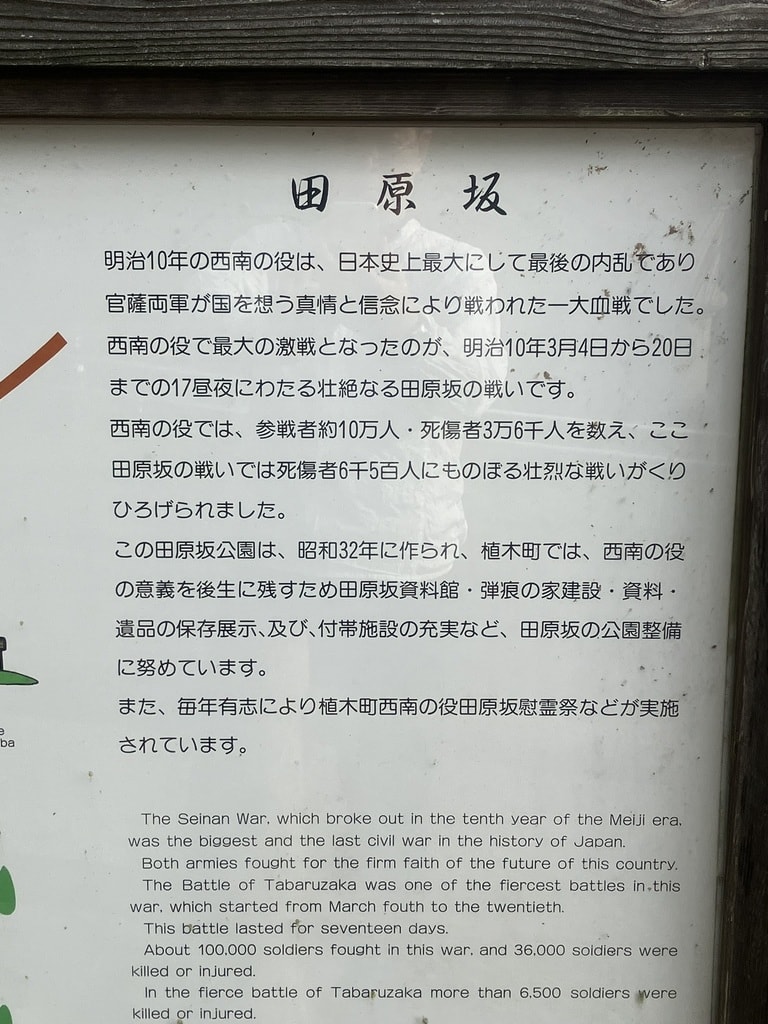天正19年(1591年)豊臣秀吉は明を征服する目的で朝鮮へ出兵するため、現在の佐賀県唐津市にある名護屋城を改築した。
名護屋城は巨大な前線の基地となった。各武将に陣地割を施し、徳川家康や伊達政宗の陣地もあった。
小田原の役
1590年(天正18年) 豊臣秀吉 天下統一
朝鮮出兵
文禄の役
1592年5月24日(天正20年4月13日) ~ 1593年8月5日(文禄2年7月9日)
慶長の役
1597年3月1日(慶長2年1月14日)~1598年12月22日(慶長3年11月25日)
豊臣秀吉61歳没 1598年9月18日(慶長3年8月18日)
関ヶ原合戦
1600年10月21日(慶長5年9月15日) 徳川家康 東軍勝利
たった10年の間に時代は激変した
文禄の役
名護屋滞在が10万、朝鮮出征が16万〜20万
慶長の役
日本軍陣立 再出征軍・総計141,500人
日本全国の総石高は約2000万石
一万石あたり250人の兵の動員、日本の総兵力は約50万人
文禄の役25万〜30万の兵数、日本の総兵力の約半分
豊臣秀吉の四国征伐時 約10万
九州征伐時、小田原征伐時は約20万 (Wikipedia)
名護屋城趾から九州電力玄海原子力発電所が見えた