以下は宮崎正弘と渡辺哲也の対談本、南北戦争か共産主義革命か!?迫りくるアメリカ 悪夢の選択、からである。
本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。
日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。
世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。
p128-p144
「2050年 脱炭素」という時代がほんとうに来るのか
宮崎
本章では、日本経済および日本企業にとってリスクと勝機を予測していきたいと思います。
コロナ禍による世界リセットで日本経済にとって大きなリスクは5つある。
電気自動車(EV)、半導体、中国依存、株暴落、円高。
まず、日本は2050年までに「脱二酸化炭素」を宣言しています。
「カーボン・ゼロ」が新しい日本の目標となったわけですね。
歴史的巨視から見ると、第一次革命は、農業分野の改革改良と飛躍的生産。
第二次革命は、蒸気機関の発明による産業革命。
第三はIT、通信の大変革による通信革命だったとすれば、カーボン・ゼロは「第四の革命」。
しかし、2050年までにカーボンーゼロを目指すという宣言は、本気なのかな?
渡邉
そもそもカーボン・ゼロの動きのはじまりは、アメリカ民主党のゴアがつくった環境利権です。
ゴア副大統領が大統領候補になったときに、環境利権ということで廃棄権をビジネスとして、新興国・先進国の間でそれを売買するという仕組みをつくった。
ある意味、これを動かすためのプラットフォームがパリ協定だったわけです。
トランプ政権になって、なぜ米国がパリ協定から離脱したかといえば、環境利権は民主党にとっての票田だったからです。
その一方で、採掘技術の発展によりシェールオイル、シェールガスが採れるようになって米国は産油国に変わった。
かつてエネルギー輸入国だった米国が、エネルギー輸出国に変わった。
カーボン・ゼロはその潮流に真っ向からぶつかります。
宮崎
そういう文脈ではアメリカは、EVに対していちばん懐疑的だったし、いまでもあまり乗り気じゃない。
ところが、バイデンになって環境がガラリと変わるやGMが2035年までに全車をEVにすると衝撃的な大ニュースが飛び込んできました。
トランプのせっかくの努力によって、米国がエネルギー輸出国になったということを外交的にみれば、中東・アラブの産油国の重要性、発言力の低下を示しました。
国際政治でいちばんの重要ポイントというのは、実はここにあって、米国がイスラエルを公然と支援できる立場を得た。
公然とイランを非難できるようになったのもそうした背景があってのことです。
渡邉
中東から石油を買わなくてもよくなった、ということですよね。
それと同時に、産油国の立場でみても、自らの価値を低下させるようなパリ協定はマイナスでしかない。
そもそも、ほんとうにCO2だけが地球温暖化の原因なのか、ということからして大きな疑問です。
ましてやもっともCO2を排出し、プラスチックゴミなど最大の環境汚染国家である中国を規制せずに、実際問題効果としてどれだけあるのか。
温暖化と言いながら今季の冬は、中国は大寒波に見舞われている。
宮崎
日本も襲われているよ(笑)。
去年からの豪雪、北日本から北陸にかけてマヒ状態でした。
私は金沢の出身なので、豪雪禍の経験があります。
陸の孤島になるのです。
渡邉
この寒波のせいで、中国にとっても大きな政策転換期がきてしまった。
しかし、そのはじまりは、実は制裁のためにオーストラリアからの石炭輸入を止めてしまったことが原因です。
豪州産の石炭は非常に良質で、不純物が少ない。
他の国や中国の国産石炭は、イオウ分だらけで品質がよくないんですね。
宮崎
モンゴルからも輸入していますね。
渡邉
結局、それでは問に合わないし、豪州産の石炭に合わせて調整された炉で、他国の不純物の多い石炭を燃やすと焦げてしまいます。
電気自動車とグリーンエネルギーの限界
渡邉
スキー場に携帯電話を持って行ったことのある人はわかると思いますが、スキー場だと、普通10時間もつ携帯電話が30分で電波が切れちゃったりする。
あまりに寒いと、電池が低温化で放電してしまい、ものすごく効率が悪くなるわけです。
テスラなどのEVも、フル充電で150㎞走れるはずのものが、30㎞ぐらいで止まってしまう。
宮崎
日本でも雪に閉ざされて止まった東北道では、最初にダメになったのが電気自動車でした。
2021年の1月に、北日本から北陸を襲った本雪、豪雪によって寸断された高速道路では、数千台のトラックが動かず物流が中断するという新しい危機が目のあたりに出現しました。
EVが各所で燃料切れを起こし、あれで、電気自動車の限界は見えてしまったわけですが、メディアはあまり大きく報道しませんでしたね。
電池技術が未完成のレベルにあり、充電スタンドが圧倒的に不足しているというのが現実なのです。
おそらくガソリン車全廃となっても、ハイブリッド車の優位が続くでしょう。
渡邉
中国は、シベリアからの偏西風があるので、風力発電に期待していたのだけれど、寒すぎるので、風車が凍りついてしまうし、それを溶かそうにも、初動の電源がないと風力発電が回らない。
それで、冬の間は機能しないのです。
宮崎
太陽光パネルも同じでしょう。
渡邉
天気が悪くなると使えない。
特に雪が降る地域はパネルの上に雪が積もっちゃうので発電しない。
宮崎
中国にはもうひとつ原因があって、大気汚染で、空気中のゴミがパネルの上に溜る。
それで効率が悪くなり、やっぱり太陽光パネルの発電ができなくなる(笑)。
渡邉
今回の寒波によって、問題点が噴出しました。
また日本でも、この4~5年の間に風水害が多発したことにより、太陽光発電の問題が露呈した。
たとえば、堤防に敷設した太陽光パネルのせいで土手の保水力が失われてしまい、土手が壊れたとか。
大規模な発電施設が水に浸かってしまって、全滅したとか。
太陽光パネルはタチが悪くて、一度燃えると、有毒ガスが出て、燃えつきるまで触れないのです。
また、大雨で流されたら、流されながらも発電し続けるから、感電の恐れがあって近づけない。
さらに、耐用年数が15年くらいと、ものすごく環境負荷も高いのです。
また、核のゴミを問題にする人がいますが、太陽光パネルにもその種類によって、鉛、ヤレン、カドミウムなどの有害物質が含まれている。
核のゴミ同様、大きな問題を抱えたものなのです。
この処理をどうするのか。
太陽光発電に関しては、これから処理の問題も噴出するでしょう。
処理コストだけをとっても、核の処理コストと同時に太陽光パネルの処理コストがいくらになるかわからないというのが現状です。
宮崎
パナソニックも21年度内に太陽電池からの撤退を発表しました。
グリーンエネルギーとか、ソフトエネルギーパスとかいわれて期待されたけれど、いま、気づくと一時期の夢に過ぎなかったわけだ。
渡邉
そうですね。
オーストラリアでは、太陽光パネルと既存の配電線の接続をやめる動きがあります。
なぜかというと、太陽光発電によって生み出された電気は、ノイズがすごい。
電力をワット数だけでみる人が多いですが、実はノイズの有無が非常に重要。
ノイズのない安定した電力でないと結局使いものにならないのです。
よく昔の蛍光灯がちらついていたのは、ノイズが理由です。
電力のクオリティの問題ですね。
フリッカーといって、ノイズがたくさん入ると、工業や精密機械に対応する現場では使えない。
また反対に、九州のように日照量が豊富で夏場の発電量が多すぎるという問題も生じている。
電気というのは多すぎても周波数が乱れてしまうので、夏場は受け入れ停止をしだしています。
だから、これ以上太陽光発電は増やせない。
宮崎
中国の場合は補助金つけたからブームが起きたんだけどね。
渡邉
日本もそうで、補助金だけじゃなく、固定価格買取制度という買取制度をつくって、初期の買取価格はものすごく高くて40円以上あったのが、どんどん下がって、2021年は10円もつかなくなっている。
結局、太陽光発電の設備投資をするだけで儲かるというモデルをつくってしまったのです。
これで儲けたい人たちがたくさんいて、その人たちが反原発に走った。
宮崎
みんな、浅はかなことをやるんだよなあ。
渡邉
グリーンニューディール、グリーンエネルギーはイメージはいいのかもしれないけれど、日本においては限界にきています。
結局、安定したエネルギー源として使えるグリーンエネルギーは、日本においては地熱以外には無理ではないかということになってきている。
宮崎
ところが、火山列島でもあるのに地熱発電に関しては、日本がいちばん遅れている。
渡邉
その遅れている理由には、温泉の問題が絡んでいる。
地熱があるのは温泉地なので、温泉業者などが、泉源が出なくなるとかね、お湯がとれなくなるとかいって反対するのですよ。
ですから、グリーンエネルギーといっても、どこまで再生化のエネルギーに組ませられるかという問題であって、結局、エネルギーミックスの限界なのですよ。
宮崎
地熱発電は私も2ヵ所ほど見学に行ったことがありますが、北海道、岩手、秋田、宮城、福島、東京の八丈島。
西のほうでは、大分、鹿児島などで行われているけれど、みんなすごく小規模でね。
全部あわせても、日本の電力需要の0.3%くらいを賄うにすぎない。
渡邉
大規模な実験施設までは到達していませんね。
宮崎
日本列島のような火山列島の国においては、アイスランドのように地熱利用をもう少し見直さなければいけないと思います。
この稿続く。


















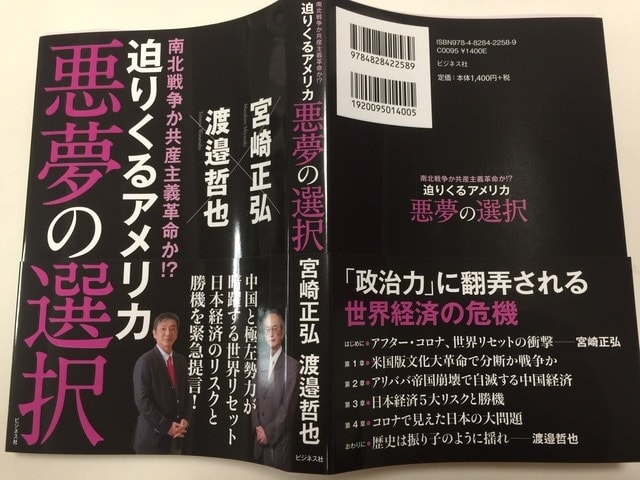




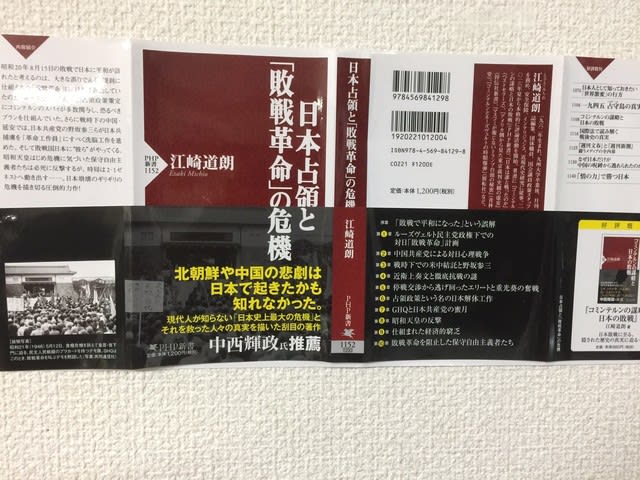
:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/8616487/abe.jpg)