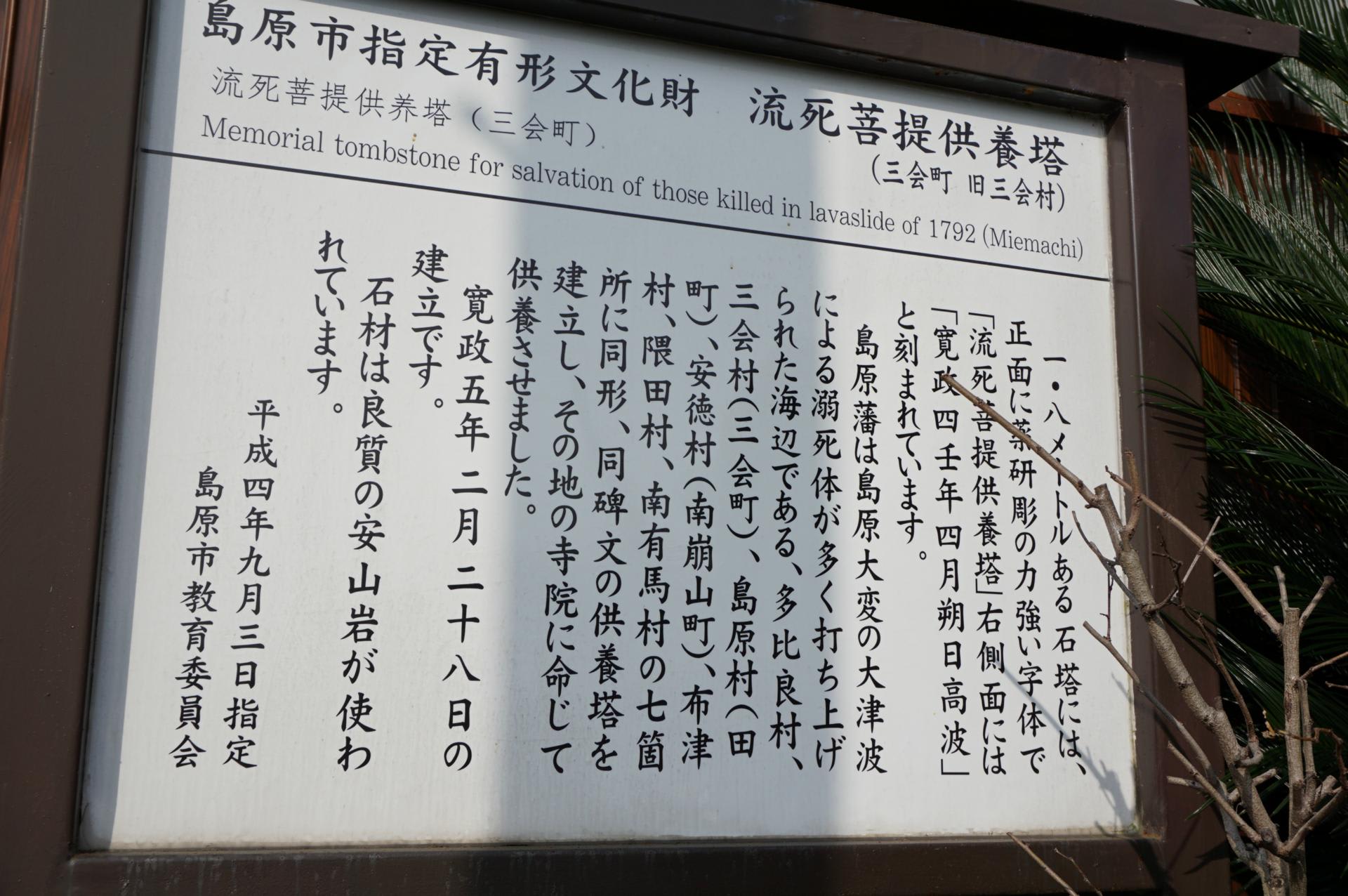「愛野町」は「あいのまち」と読みます。
愛野町は「愛」をテーマとした町づくりをしています。
2015年最後のブログは、愛野町を取材して見つけた「愛」へのこだわりを紹介して締めくくります。
(上山70回は残念ながら達成できませんでした。)
モニュメント

ときめきの像の台座にも「愛」

島鉄愛野駅

四つ葉のクローバー

駅舎のてっぺんの矢印は…

吾妻駅方向を指しています。前回も紹介しました「愛野から吾妻」、「愛しのわが妻」への思いは、一方通行で後戻ることはできない強い愛を表しているそうです。
ほほえみの像

ベンチ


愛野駅前には、上の写真のようなベンチが複数置かれていますが、中央を境に対称に色分けされています。そこに座る二人がどの色の部分に座るかで二人の愛情が度がわかるとか…。
以上、愛野町の「愛」へのこだわりの一例を紹介させてもらいました。
”TENNZANBOKKA78”を訪問していただき、ありがとうございました。
みなさまにとりまして、新しい年が愛に満ちたすばらしい年になりますように祈念申し上げます。
愛野町は「愛」をテーマとした町づくりをしています。
2015年最後のブログは、愛野町を取材して見つけた「愛」へのこだわりを紹介して締めくくります。
(上山70回は残念ながら達成できませんでした。)
モニュメント

ときめきの像の台座にも「愛」

島鉄愛野駅

四つ葉のクローバー

駅舎のてっぺんの矢印は…

吾妻駅方向を指しています。前回も紹介しました「愛野から吾妻」、「愛しのわが妻」への思いは、一方通行で後戻ることはできない強い愛を表しているそうです。
ほほえみの像

ベンチ


愛野駅前には、上の写真のようなベンチが複数置かれていますが、中央を境に対称に色分けされています。そこに座る二人がどの色の部分に座るかで二人の愛情が度がわかるとか…。
以上、愛野町の「愛」へのこだわりの一例を紹介させてもらいました。
”TENNZANBOKKA78”を訪問していただき、ありがとうございました。
みなさまにとりまして、新しい年が愛に満ちたすばらしい年になりますように祈念申し上げます。