今、1年生の授業では、『色の三要素』を学習している。
色の三要素とは、
1.色相(色合い・・・赤や黄色や緑などの色味のこと。
2.明度・・・色の明るさのこと。白に近づくほど明度が高く、黒に近づくほど明度は低い。
3.彩度・・・色の鮮やかさのこと。純色(赤・青・黄の3原色で作られる色)に近いほど彩度は高く、灰色に近いほど彩度は低い。
というようなことを、12色相環やグレスケールを見せながら説明するのだが、1年生は、『図工』から『美術』になったばかりで、『美術って難しいもの』とばかりに緊張している。
そこで、『捕色』の実験をしてみる。
いわゆる『残像現象』の実験だ。
白地に赤色の色紙を見せて、30秒後、その色紙をはずすと、何が見えるか・・・・。
集中力のない生徒や、まれに色を認識できない生徒には、何も見えない。
でも、みんなが、
「水色みたいな緑色のチカチカしたのが見える!」
と騒ぎ出すと、見えなかった生徒が
「先生、もう一回やって!」
と言い出す。
そこで、12色相環を使って、補色の説明をし、
「じゃあ、それがわかったら、今度赤の反対色の緑を見たら、何色が見えるか、自分の目で確かめてごらん」
そうして、みんなの目が慣れた頃、今度は、白地に緑の折り紙を見せる。
その30秒間は、水を打ったように静かになる。が、待ちきれない生徒が、
「おお!」と驚きの声を上げだす。
さっと緑の色紙を取り去ると・・・・!
そこから、生活の中で生かされている補色の効果の説明を、クイズ形式で生徒達に投げかけていくと、すごい集中力で説明を聞き、積極的に発言や解答をしてくれる。
あっという間に時間となり、最後に、
「自分の影をじっと見つめて、青い空を見上げると、自分の影と同じ形の入道雲が見えるよ」
と教えてやる。
鎌倉の大仏の前でそれを実験したときは、大騒ぎの大喜びで、周りの観光客を不思議がらせた。
『美術』に対して、『理科の実験みた~い!』『お父さんとお母さんに教えてあげたよ!』『今まで不思議だったことがわかってよかった』『もっといろんなことが知りたい』と意欲満々な1年生。
でも、楽しいことばかりじゃないんだな~、今週から『3原色で12色相環を作ろう』という実技に入った。
黄色と赤で橙、黄色と青で緑、青と赤で紫を色見本通りに自分で色作りをする。
これが結構難しいのだが、生徒達は、失敗しながらも、何とか仕上げようと頑張る。出来上がる頃にはコツもわかって、今度は、最初の頃のリベンジを図りに、
「先生もう1枚紙頂戴。もう一回、今度は前よりもきれいに色作ってぬるから」
と意欲的な子まで現れる。
「先生!今まで、黄緑色なくなったら、絵の具買いに行っていたけれど、今度から買わなくてすむね!」
色作りにみんながはまった頃、アニメの背景で散々やった「ぼかし」を教える。
ものの30秒で赤から黄色、黄色から青、青から赤のきれいな中間色の「ぼかし」ができるようになると、
「何でこんな簡単で楽な方法、最初から教えてくれなかったの!」
と抗議を受ける。
「最初から『楽』を覚えたらだめなんだよ。あれだけ苦労して色の微妙な違いを出せるようになってからじゃないと、このありがたみはわからないでしょ。みんなはもう、自分の作りたい色が自由自在に作れるようになっているんだよ。『苦あれば楽あり』『苦』を知らない人は本当の『楽』この場合、『楽しさ』のほうね。わからないんだよね。」
この授業で、半分ぐらいの生徒が、美術を嫌いな理由のダントツ1位『絵の具が嫌い。混色、色作りがめんどくさい』の苦手意識がぬけ、早く作品を作りたくなってくる。
でも、まだまだ作品は作らせない。
この後は15種類の『デザイン技法』~裏技~の伝授が待っている。
楽しみ~*(ハート)*
色の三要素とは、
1.色相(色合い・・・赤や黄色や緑などの色味のこと。
2.明度・・・色の明るさのこと。白に近づくほど明度が高く、黒に近づくほど明度は低い。
3.彩度・・・色の鮮やかさのこと。純色(赤・青・黄の3原色で作られる色)に近いほど彩度は高く、灰色に近いほど彩度は低い。
というようなことを、12色相環やグレスケールを見せながら説明するのだが、1年生は、『図工』から『美術』になったばかりで、『美術って難しいもの』とばかりに緊張している。
そこで、『捕色』の実験をしてみる。
いわゆる『残像現象』の実験だ。
白地に赤色の色紙を見せて、30秒後、その色紙をはずすと、何が見えるか・・・・。
集中力のない生徒や、まれに色を認識できない生徒には、何も見えない。
でも、みんなが、
「水色みたいな緑色のチカチカしたのが見える!」
と騒ぎ出すと、見えなかった生徒が
「先生、もう一回やって!」
と言い出す。
そこで、12色相環を使って、補色の説明をし、
「じゃあ、それがわかったら、今度赤の反対色の緑を見たら、何色が見えるか、自分の目で確かめてごらん」
そうして、みんなの目が慣れた頃、今度は、白地に緑の折り紙を見せる。
その30秒間は、水を打ったように静かになる。が、待ちきれない生徒が、
「おお!」と驚きの声を上げだす。
さっと緑の色紙を取り去ると・・・・!
そこから、生活の中で生かされている補色の効果の説明を、クイズ形式で生徒達に投げかけていくと、すごい集中力で説明を聞き、積極的に発言や解答をしてくれる。
あっという間に時間となり、最後に、
「自分の影をじっと見つめて、青い空を見上げると、自分の影と同じ形の入道雲が見えるよ」
と教えてやる。
鎌倉の大仏の前でそれを実験したときは、大騒ぎの大喜びで、周りの観光客を不思議がらせた。
『美術』に対して、『理科の実験みた~い!』『お父さんとお母さんに教えてあげたよ!』『今まで不思議だったことがわかってよかった』『もっといろんなことが知りたい』と意欲満々な1年生。
でも、楽しいことばかりじゃないんだな~、今週から『3原色で12色相環を作ろう』という実技に入った。
黄色と赤で橙、黄色と青で緑、青と赤で紫を色見本通りに自分で色作りをする。
これが結構難しいのだが、生徒達は、失敗しながらも、何とか仕上げようと頑張る。出来上がる頃にはコツもわかって、今度は、最初の頃のリベンジを図りに、
「先生もう1枚紙頂戴。もう一回、今度は前よりもきれいに色作ってぬるから」
と意欲的な子まで現れる。
「先生!今まで、黄緑色なくなったら、絵の具買いに行っていたけれど、今度から買わなくてすむね!」
色作りにみんながはまった頃、アニメの背景で散々やった「ぼかし」を教える。
ものの30秒で赤から黄色、黄色から青、青から赤のきれいな中間色の「ぼかし」ができるようになると、
「何でこんな簡単で楽な方法、最初から教えてくれなかったの!」
と抗議を受ける。
「最初から『楽』を覚えたらだめなんだよ。あれだけ苦労して色の微妙な違いを出せるようになってからじゃないと、このありがたみはわからないでしょ。みんなはもう、自分の作りたい色が自由自在に作れるようになっているんだよ。『苦あれば楽あり』『苦』を知らない人は本当の『楽』この場合、『楽しさ』のほうね。わからないんだよね。」
この授業で、半分ぐらいの生徒が、美術を嫌いな理由のダントツ1位『絵の具が嫌い。混色、色作りがめんどくさい』の苦手意識がぬけ、早く作品を作りたくなってくる。
でも、まだまだ作品は作らせない。
この後は15種類の『デザイン技法』~裏技~の伝授が待っている。
楽しみ~*(ハート)*












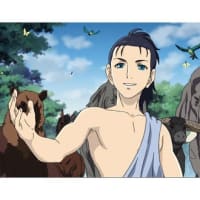







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます