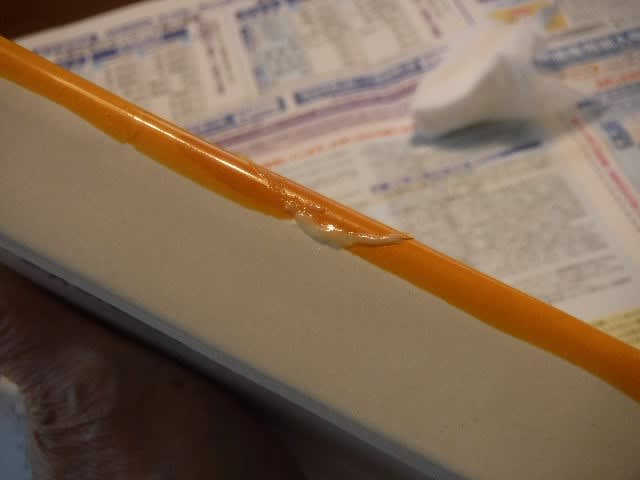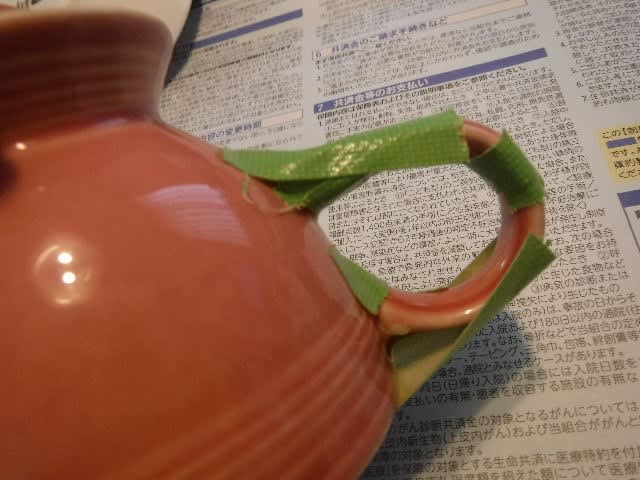阪急武庫之荘駅の北側にあるギャラリーのオーナーから、繕いの依頼がありました。
受け渡しが面倒なので、複数作品でとお願いしていたので、久しぶりの依頼でなんと5点も。
しかも、いつもそうですが、金の丸粉を使ってとの依頼です。
手間と金額、相当なものになりそうですね。
金繕いのPRポスターなどを一新しました。
私の陶芸のプレハブ工房の壁面です。
金繕いがとても人気が出ていると新聞などで報道されていますが、川西のパレットの教室はとても好評ですが、地元尼崎では、皆さんの反応はいまいちなんです。
最近、金繕いでいろいろと活躍してとても収入を得ている人が、脱税していて、億を超える金額を追徴されたとの新聞記事を読みました。
すごい人がおられるのですね。
私は、ほぼボランティアで、とても安価で修復してあげていますのですがね。
新しいポスターなどです。

右側のものは最近作り替えておいたものです。
陶板皿は、立杭の若手作家の丹文窯の大西雅文さんから頂いたものです。
「金繕いの例」の写真も相当傷んでいたので作り変えました。
ご近所の方からの繕いの依頼です。
これまでもいくつか繕ってあげています。
今回はこの2点です。
ビアカップは口のあたりが割れてしまっています。
小皿も1カ所欠けていて、破片も少し無くなっていますね。
さあ、スタートです。
ベースの修復は簡易法で接着剤を利用して。
今回は30分で硬化開始のもので。
地の子や強力粉を混ぜて。
硬化するまでの面倒見が大切です。
そして、翌日以降に水ペーパーなどで整形して。
こんな仕上がりです。
この後もしっかり乾燥させて。
そして、黒艶漆の処理です。
金属粉は、錫紛(金色っぽいもの)を蒔いて。
その後、しっかりと漆の乾燥です。
底に水を含ませた新聞紙をひいています。
ホットカーペットの上で、3、4日かけて漆を乾燥させて。
さあ、出来上がりました。
仕上げは真綿で磨いています。


生漆でベースを修復するのはとても時間がかかりますので、簡易法で。
そして、金粉はとても高価なので、錫粉で。
特別に希望があれば別ですが、これで、安く修復してあげられます。
2点の徳利の繕いの続きです。
弁柄漆に金の丸粉(3号)を蒔いて、湿気のある容器の中で2、3日かけて漆をしっかりと乾燥させます。
その後、生漆をテレビンでうんと薄めたもので粉固めの処理です。
消し粉などでは、この処理は必要ありません。
この操作を3回繰り返して。