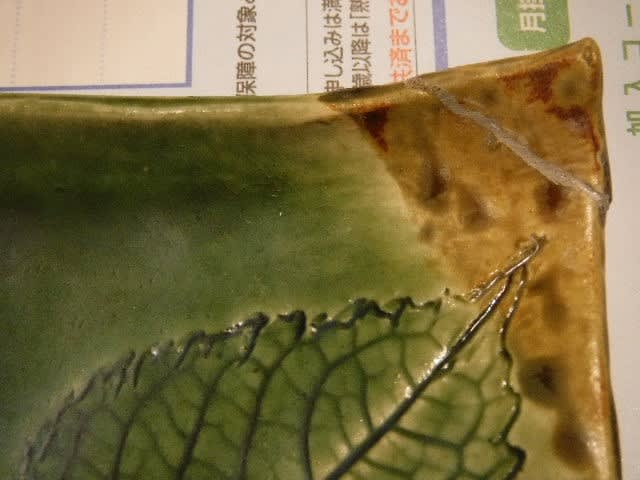先日の千代木園での陶芸教室で、繕い品を依頼されました。
この作品は高台部分に少し亀裂がありました。
器を温めてアラルダイトを注入します。
こちらの器は底の部分にひびが入っていました。
制作時に底の締め方が足らなかったのでしょうね。よくあることです。
同様に器を熱い位に温めて、アラルダイトを注入です。
器を温めるのには、ドライヤーやトーチ、それから電子レンジもとても便利です。
この後、綺麗に余分な接着剤をふき取って。
接着剤の乾燥後は全く水漏れが無くなりました。
もう一つの小皿。
何かの接着剤を使った後がありますので、鍋の中で強くボイルして接着剤を除去して。
アラルダイトと地の粉を使っての接着です。
接着後は、上から本漆の白を塗って。
白漆は象牙色に変色していきますので、この部分にはピッタリでしょうね。
そして、2、3日後に3点とも完成です。
この小皿の修復部分も白漆の色が濃くなりつつあって、いい感じですね。
陶芸の指導だけではなく、金繕いの手法にも少しずつ関心を持っていただくメンバーが出てきて、これからの展開も楽しみですね。
こういった簡単な手法だったら、陶芸の合間に教えてあげたいですね。