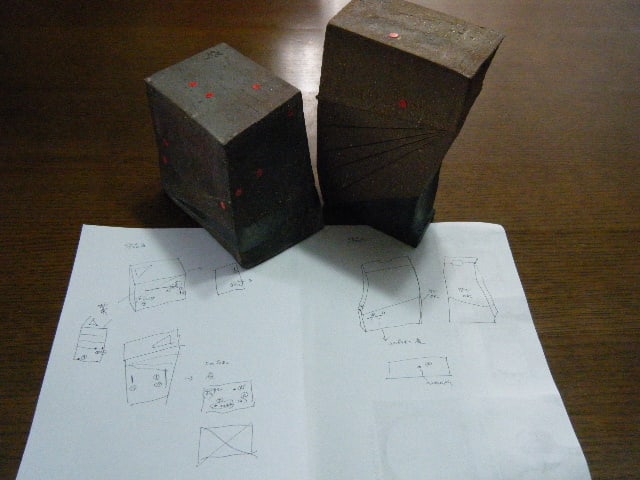日曜日の立杭での会議の時に、ボランティア仲間から依頼があった可愛い小物の繕い。
飾ってあったのをお孫さんが壊してしまったらしい。
お孫さんが、とても気にしているとのこと。
右側の2本の脚が割れていました。
「簡単ですので、ご自分でなおしたら」といいましたが、「細かい作業なんで」と預かりました。
この段階は、アラルダイトで接着を終えて半日経って、すでにくっついた状態のものです。
一番端の脚がやはりズレています。
なかなかビッタリとは合わさらず、これでもかと何枚ものセロテープで固定したのですが。

裏側です。

このあと、はみ出たアラルダイトを除いて、隙間を更に充填します。
今度は速乾性のアラルダイトにアクリル絵の具で色合わせをして。

すぐに完成です。
可愛い作品ですね。

裏側も充填して。
今度の会議でお渡ししましょう。
いつも私のブログを見てくれているらしいので、まずは安心してください。
お孫さんにもよろしく。

飾ってあったのをお孫さんが壊してしまったらしい。
お孫さんが、とても気にしているとのこと。
右側の2本の脚が割れていました。
「簡単ですので、ご自分でなおしたら」といいましたが、「細かい作業なんで」と預かりました。
この段階は、アラルダイトで接着を終えて半日経って、すでにくっついた状態のものです。
一番端の脚がやはりズレています。
なかなかビッタリとは合わさらず、これでもかと何枚ものセロテープで固定したのですが。

裏側です。

このあと、はみ出たアラルダイトを除いて、隙間を更に充填します。
今度は速乾性のアラルダイトにアクリル絵の具で色合わせをして。

すぐに完成です。
可愛い作品ですね。

裏側も充填して。
今度の会議でお渡ししましょう。
いつも私のブログを見てくれているらしいので、まずは安心してください。
お孫さんにもよろしく。