川西の「器再楽」の教室にわざわざ持ってきていただいた丹波焼のコップの繕いの続きです。
今回はロイロ漆を使って、それが翌日には黒くなっていたので、いつもの艶黒漆では塗り残しとかが予想されますので、赤い弁柄漆を塗って。
内側から。
続いて外側です。
この後、銀の丸粉(3号)をたっぷりと蒔いて。

さあ、蒔き終えました。
この後、簡易ムロに入れて3、4日の間漆の乾燥を待ちます。
次の工程は粉固めです。
生漆をテレピンで薄めたものを塗って、銀粉を蒔いた表面を固めるのですが、簡単な作業なので、今回は筆は使わず、綿棒で塗って。
このあと化学実験でおなじみのキムワイプという紙でしっかりと拭いて。
新しいやり方、筆も使わないので洗ったりする手入れが不要です。
容器もキムワイプでふくだけで。
とても便利なやり方、教室でもお勧めしましょう。
1、2日の乾燥で、これを3回ほど繰り返して。
いよいよ最後の工程です。
漆を蒔いた部分のラインをカッターナイフで整えた後、木綿でしっかりと磨いて。
今回は、超ミクロな水ペーパーも使って。
これは6000番ですね。
そして、鯛の牙(鯛牙・たいき)で磨きます。
銀粉が光り出します。
完了です。
銀粉は消粉ではなく丸粉をしっかりと漆の中に閉じ込めていますので、とても丈夫で、消粉のように銀粉が使っているうちに消えてしまうようなことはありません。
お待たせしましたね。
期待してくれているご主人のために、詳しい説明付きで、うんといい仕上がりになるように努めましたよ。




























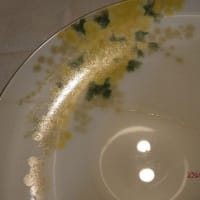


ブログ拝見して、主人にも見てもらいました。大変感動しており、是非直接お礼を言いたいとのことでした。
土日が休みになるので、日程や場所などご相談できればと思います。
この度は大変な作業を、誠にありがとうございました。
わざわざお礼はいいですので、次回の川西の教室でお渡ししたいと思っています。5/9(木)です。