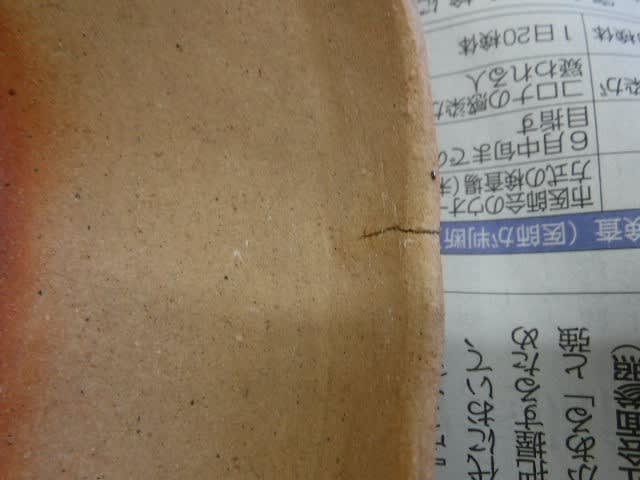川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子の続きです。
繕いの内容はまた全くいろいろですね。
磁器には強力粉、陶器には地の子をアラルダイトに混ぜて、ベース作りです。
初参加の方が持ってこられた繕い品。
欠けた部分が4か所ありますが、なかなかいい感じの品物ですね。
前回までにベースの修復を終えた抹茶茶碗。
釉薬の色と合っているので、艶黒漆を施すだけでいいですね。
そして、欠けた部分が1か所と亀裂がたくさん入った相当使い込まれた蕎麦猪口。
錫粉を蒔いて。
この徳利は、こんな風に漆を塗った後、金の丸粉(3号)を蒔きました。
この方も世話人のお一人で、金粉はお分けしてあげているもので。
こだわりの品物のようですね。
このきれいな小皿、2枚ありましたが、世話人をしてくださっている方のものですが、ほとんど器を壊すことがないそうで、わざわざ割って修復の体験をされています。
仕上げは錫粉で。
今回は2グループに分かれて、私は1時から5時半ころまでの長時間にわたる教室で、大変疲れました。
次回から、大きな部屋を確保してもらっています。