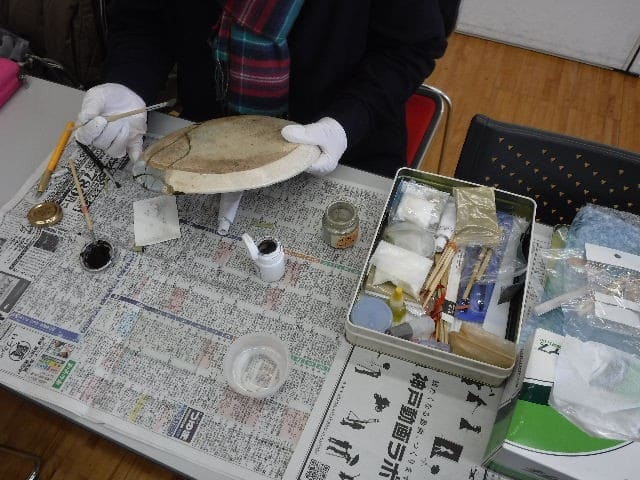土鍋蓋の繕いの続きです。
さあ、しっかりと接着できました。
木曜日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子の続きです。
皆さんの取り組んでいる様子です。
そろそろいろんな道具も用意されていますね。
さて、私も大急ぎで。
接着剤は急速硬化するものと普通のものとを用意して。
地の子と強力粉をまぜたものの2種類を用意して。
ガラス製のコップには、「新うるし」の本透明を塗って。
その上からゴールド色をした錫粉を蒔いて。
他のものもすべてこの錫粉ですね。漆は黒艶漆を塗っています。