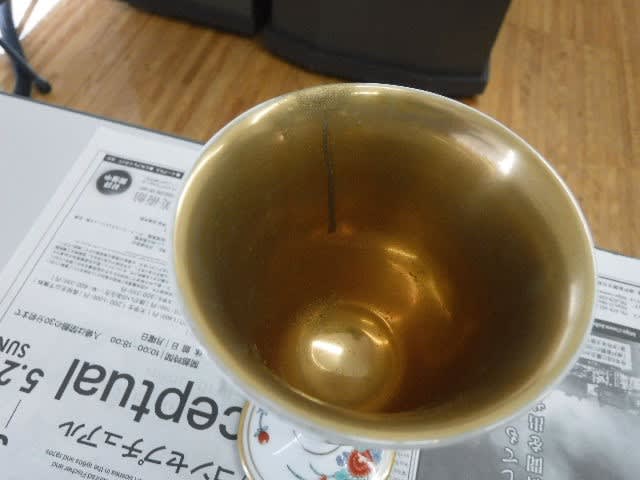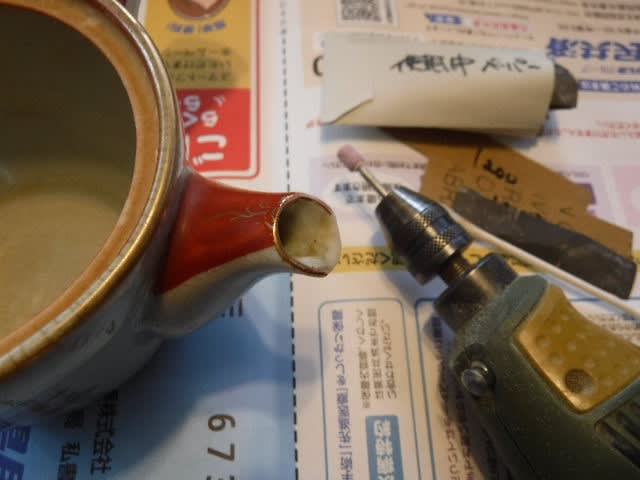先週の木曜日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の様子です。
さあ、スタートです。
この日の参加者は7名。
今回も繕うものがたくさんありますね。
先ずはルーターで整形するものから。
そして、次はひび(にゅう)の入った部分に接着剤を注入することから。
この日持ち込まれたもので、ちょっと難しいなと思案した品物。
ガラス製品で、葉っぱが1枚大きく割れてしまっています。
その破片がないので。「うーん」と。
参加者がその様子を熱心に観てくれています。
結局、薄いプラスチック板をうまく利用して、接着剤を流し込みました。
こんな形で接着剤が固まるまで、いい姿勢を保持してあげてもらって。
そして、前回までの品物の仕上げを。
口のあたりを磨きすぎたので、またゴールドの錫粉を蒔いて。
私は漆を面相筆で塗る作業で忙しくて。
参加メンバーに錫粉を蒔く作業をしていただいて。
この日もあっという間に3時間の教室が終わってしまいました。
参加されている皆さんの笑顔が、とても楽しそうでいいですね。
次回は、6月9日ですね。