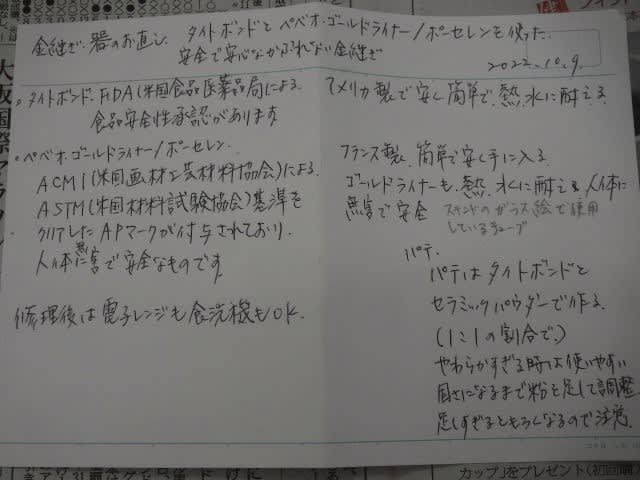木曜日の川西パレットでの金繕い教室「器再楽」の続きです。
この日久しぶりに参加された陶芸をされている男性が、繕い品を沢山持ってきてくれたようですが、私が気付いた時には、もうほとんど無くなっていて。
世話役のお一人がコーヒーカップの取っ手をタコ糸も使ってこんな風に仕上げましたと。
とても上手ですね。
さあ、今日もたくさんの繕い品があります。
でも、私のワンポイントアドバイスで、さっさとご自分で作業をされる人も増えています。
たくさんに割れてしまった蕎麦猪口、接着の手順が大切ですね。
ベースの修復部分の手入れをしてあげて。
すぐに固まる接着剤が便利ですね。
帰るころまでには固まって、仕上げを終えることができますので。
さあ、黒艶漆を使っての漆の処理の開始です。
画廊シャノワールのオーナーから4点。
ベースの修復はとても上手になっていますが、漆を使う以降は、ギャラリーの運営もありますので、すべて私任せですね。
オーナーの紹介で、前回から参加してくださっている新しい方、熱心に観てくださっています。
続きます。
次の繕いの依頼です。
さあ、接着開始です。
取っ手の部分、小さな欠片も入れると4片です。
裏側の欠損部粉も補填して。
カップの方は、トーチで熱くして接着剤を注入して。
接着した部分をきれいにして、翌日に次の工程です。
黒艶漆を塗って。
20から30分置いてから、金の丸粉(3号)を蒔きました。
丸粉は消し粉と違って、漆の中に沈んでいくので、しばらく様子を見ながら作業を続けます。
長皿の表側です。
裏側も。
漆を乾燥させるのに日数をかけて。
丸粉では、生漆をテレピンで薄めたもので、粉固めの処理をします。
これを3回繰り返して。
丸粉での作業には、日数がかかりますね。
そして、漆が完全に乾燥した後、鯛牙(たいき)で磨いて、完成です。
さあ、どうでしょうか。
骨董店で安く入手したという杯、ひびの手入れから。
新しく参加された方が持ってこられたお皿。
ご主人が割ってしまつて、すぐにご本人がアロンアルファで接着したそうです。
しっかりと接着されているようなので、そのまま次の処理に。
今後割れた部分が剥がれる場合には、接着剤をはがす作業からやり直せばいいですからねと。
ここの部屋、二部屋ですが、明るくていいですね。
皆さんの取り組んでいる様子です。
最近5分で硬化が始まる接着剤もよく使っています。
簡易法ですので、接着剤が5分、30分、90分から硬化と3種類ありますので、うまく使いこなせばいいですね。
生漆を使って接着する本格的な手法は、いろいろと教本も出てますので、とても日数がかかりますが、自宅で是非取り組んでほしいものです。
皆さん、上手になられて。
さて、私の作業です。
このカップも新しく参加された方が持参したもの。
5分で硬化し始める接着剤に強力粉を混ぜて、ベースを早速整えて、終了間際に金色の錫粉を蒔いてあげました。
このお皿も仕上げですね。
皆さん、熱心に作業を見てくださっています。
12月に入りましたので、これから忙しくなりますが、今月は22日も開催です。