
国鉄165系電車、165系は、国鉄の新性能電車初の直流急行形電車として開発された153系電車の構造を受け継ぎつつ、勾配・寒冷路線向けの急行形電車として開発され、1963年3月から営業運転に投入されました。
1960年代前半、信越本線長岡 - 新潟間と高崎 - 長野間、中央東線の電化により首都圏から直通する長距離連続電化区間が完成し、電車による急行列車を運転することが計画されました。しかしいずれも連続急勾配が介在し、寒冷・多雪な気候条件の路線であり、東海道本線などの平坦・温暖区間向けに設計された153系電車では、これらの路線には出力や耐寒能力不足で不適であったため勾配・寒冷路線での運用に耐える性能を備える直流急行形電車とされたのが165系です。
ただし後述のように、平坦・温暖路線用の高出力形の計画が系列の集約を進める立場から見送られたため、結局本系列が多くの路線で運用される標準型となった。
車体構造はほぼ153系を踏襲してはいるが、以下のような改良が行われている。
主電動機は、従来標準であったMT46形(端子電圧375V時定格出力100kW/1,860rpm(70%界磁)・最高回転数4,320rpm)に代えて、MT54形(端子電圧375V時定格出力120kW/定格回転数1,630rpm(全界磁)・定格電流360A・最高回転数4,320rpm)を採用した。20%の出力向上で、MT比1:1の編成を組んでも25‰程度の勾配を登坂できるようになり、経済性と輸送力を両立させました。MT54系電動機は、列車併結などによる混用を考慮して、MT46形と極力出力特性を揃えてあります。なお速度種別は、MT比1:1の編成でも営業最高速度と同じA10です。
主制御器に「自動ノッチ戻し機構」と山岳区間での走行も考慮した勾配抑速ブレーキを搭載したCS15形制御装置を採用し、主抵抗器の容量も153系などに比べ大きく増強されています。
寒冷地・積雪地での運用に備えて耐寒耐雪装備が施されてます。
ダイアフラム形空気バネの横剛性を生かして揺枕吊を廃止し、451系・471系以降の国鉄特急・急行形電車の標準となったインダイレクトマウント方式の空気ばね台車DT32(電動車)・TR69(付随車)系を装備し、高速安定性や乗心地が改善されました。
クモハ165形
モハ164形とユニットを組む2等制御電動車 (Mc) で、主制御器・主抵抗器を搭載。勾配線区で使用される特質上電動車比を高める必要から、基幹形式の一つとして1963年から1970年にかけて製造された。定員76名。外観上は、主電動機冷却風の取り入れのため、前部出入台(デッキ)屋根上部に設けられた大型の通風器、および床下ギ装の関係で他車の700リットルに対して本形式及びモハ165形は枕木と平行に設置された550リットルの水タンクが特徴である。また、451・471系では電動車ユニットを両方向に使用可能としていたが、本系列では奇数向き(東海道本線基準で上り東京方)に固定を原則とした。
1 - 141:当初は非冷房だったが、1968年の利用債増備車の123 - 125はAU13E形分散式冷房装置搭載の準備工事仕様で、1968年4次債務負担以降の増備車である126 - は新製時から冷房装置を装備して落成した
日本国有鉄道(国鉄)が設計・製造した直流急行形電車。
国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・西日本旅客鉄道(JR西日本)にそれぞれ承継された。
写真のクモハ165-108は2001年に神領車両区で廃車後、美濃太田車両区で保管後、リニア・鉄道館で展示されています。。










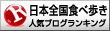


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます