

波根駅は、海辺に開けた小集落の駅です。元は波根湖という湖だったところで島根県大田市波根町中浜にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)山陰本線の駅です。駅前の松の木が印象的な駅で駅前のスペースは十分あります。

近くには波根海水浴場があります。 TBS「愛の劇場 砂時計」のロケ地となった駅です。劇中では「江田」となっていました。

砂時計は、芦原妃名子による少女漫画、及び、それを原作とするテレビドラマ・映画・小説です。『Betsucomi』(小学館)において2003年5月号から2006年7月号まで連載(本編は2005年11月号まで)。2007年にテレビドラマ化、2008年に小説化・映画化されました。主人公の植草杏(うえくさあん)は、12歳の冬に両親の離婚を機に母親 美和子の実家・島根に越してきた。田舎独特の雰囲気をなれなれしくプライバシーが無いと感じた杏。だが、近所に住む北村大悟(きたむらだいご)と知り合い、徐々にその田舎の雰囲気に慣れていくようになる。そんな中、彼女を支える母親が仕事中に倒れてしまい、自分が「がんばれ」と言って母親を追い込んでしまったと責任を感じた杏は、母親を少しでも助けようと仕事を探す。そして大悟と共にお手伝いに行った村の地主「月島家」で、杏は同い年の月島藤(つきしまふじ)と妹の椎香(しいか)に出会う。
4人はいつしか行動を共にするようになり、杏は嫌で嫌でたまらなかったこの村に居場所を見つける。しかしその後近くして、杏の母 美和子が生きることに疲れ、自殺をする。杏は葬式の席で、島根に来る途中に仁摩サンドミュージアムで美和子に買ってもらった砂時計を、悲しみのあまり美和子の遺影に投げつけ壊してしまう。そんな杏に大悟は、壊れた砂時計と同じものを杏に渡し、ずっと一緒にいることを約束する。杏も大悟とずっと一緒にいられるよう願う。やがて時が経つと、杏と大悟の間には恋心が芽生えていき、2人は付き合うようになる。しかし、杏の父親が杏を迎えに来た為、杏は高校の3年間は東京に住むことになり、2人は遠距離恋愛になってしまう。始めのころはうまくいっていた2人だったが、東京と島根という遠距離、藤のずっと募らせてきた杏への想い、椎香の大悟への想い、更に、杏の心の奥底にはいつも母親の影が存在していて……、2人の間はゆっくりと拗れていくようになった。そして、ある事件をきっかけに、杏は大悟と別れることを決意する。少女から大人へと成長する中で、様々な恋や別れを繰り返してゆく杏。しかし、杏の心の中は常に母親の存在で支配されたまま…でもそんな中に、ずっと心の支えとなっている大悟の姿も確かにあった。周囲が徐々に新たな幸せを見つけ出していく一方、独り、杏は幸せを求め奔走していく。

テレビドラマ版:原作が、あくまでも杏が自殺遺児であることに主眼を置いた物語であるのに対し、ドラマ版では杏の母親の自殺はひとつのエピソードでしかなく、恋愛に主眼を置いた内容となっている。そのためドラマ後半では原作とはほぼ類似点のないストーリーとなっています。原作では、26歳の杏が婚約者の海外転勤のための荷物の整理で、砂時計を発見するところから回想として物語が始まりそのまま時系列で進んでいく。しかしドラマ版では過去と現在を行き来するストーリーに改変されています。原作に比べ、登場人物が少ない。杏の母方の祖父や杏の東京での幼馴染の枝元、藤の従姉である最上茉莉子やその他、月島家の親族はドラマでは登場しません。彼らの役割を既存キャラクターが担うことで登場人物の関係に違いが出ています。ドラマ版では進藤あかねという人物が大悟の婚約者として登場いたします。彼女と彼女に関係するエピソードは全くのドラマオリジナルです。主要4人の登場人物は、性格や容姿の点で原作とは大きく開きがあり、原作者の芦原妃名子は「イメージ通りだったのは子供時代の大悟(泉澤祐希)と大人時代の藤(渋江譲二)だけ」とコメントしています。原作では杏の両親は協議離婚であるのに対し、ドラマ版では父親が離婚届を置いて失踪しています。そのためドラマ版では美和子の死から3年後にその事実を父親が知るが、原作版では美和子の訃報はすぐに伝わっており、毎年墓参りに訪れていました。大悟の実家は原作では普通の民家であるのに対し、ドラマ版では商店となっており登場人物の溜まり場となっている。

自治会館を併設した駅舎と、島式1面2線のホームがあり、行き違いが可能な古い木造駅をもつ地上駅です。駅舎は大田市寄り海側にあり、ホームへは構内踏切によって連絡しています。事務室跡は現在は公民館として利用されています。待合室にはFRP製の椅子が設置されていました。浜田鉄道部管理の無人駅であるが、駅舎内に乗車駅証明書発行機や自動券売機はありません。

波根駅プラットホーム
ホーム 路線 方向 行先
1・2 ■山陰本線 上り 出雲市・松江方面
下り 大田市・浜田方面

駅舎反対側の2番のりば側を上下本線、駅舎側の1番のりばを上下副本線とした一線スルー配線のため、通過列車及び行違いを行わない停車列車は上下線とも2番のりばを通る。
反対方向からの通過列車と行違いを行う停車列車は、上下線とも1番のりばに停車する。
停車列車同士の行違いの場合は、出雲市方面行(上り)が1番のりば、浜田方面行(下り)が2番のりばに入る。

ホームの中程には、木造の待合室が設置されています。

1915年(大正4年)7月11日 - 国有鉄道山陰本線の小田駅 - 石見大田駅(現・大田市駅)間延伸時に開業。客貨取扱を開始。
1962年(昭和37年)10月1日 - 貨物取扱を廃止。
1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。
1990年(平成2年)3月10日:無人駅になる。
電報略号 ハネ
駅構造 地上駅
ホーム 1面2線
乗車人員
-統計年度- 40人/日(降車客含まず)
-2009年-
開業年月日 1915年(大正4年)7月11日
備考 無人駅










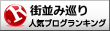


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます