

地元市民からは「しんしも」と呼ばれることが多い新下関駅は、山口県下関市秋根南町一丁目にあります。また、新下関駅が所在する下関市・勝山地区は、その駅名にちなんで新下関地区とも呼ばれる。西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅である。山陽新幹線と、在来線の山陽本線との接続駅です。

新幹線開業前は、あたりは一面水田が広がっていました。長門一ノ宮といわれる住吉神社の祭日のみ賑わっていたが、新幹線開業後は住宅地として発展しました。

現在は高層マンションや、団地、下関市立大学・東亜大学などの学生アパート、また郊外型の店舗,ショッピングセンターなどの施設が多い。

もとは旧豊浦郡に属する村 (勝山村) でしたが、1939年(昭和14年)に下関市へ編入しました。新下関駅はかつて「長門一の宮駅」と称し、長門一ノ宮とも称された住吉神社の近くにあったものが、「長門一ノ宮駅」に改称ののち1928年(昭和3年)に山陽本線の経路変更に伴って現在地に移転したものであり、戦後しばらくは広大な田園のなかに集落が散在している状態でした。

しかし、1973年(昭和48年)の関門橋と下関ICの開通、1975年(昭和50年)の山陽新幹線開業とそれにともなう長門一ノ宮駅の新下関駅への改称を機に、新下関駅を中心に区画整理がなされ、地区全体にわたって開発計画が進められることとなりました。また、1974年(昭和49年)には、東亜大学が長門一ノ宮駅(当時)の南側に開学しています。

域内中央を南北に走る幹線道路・県道下関長門線(建設当時は山口県道37号下関豊田油谷線)が整備され、その道に沿うように秋根から一の宮にかけて新下関地区の中心市街地が形成されていきました。

1976年(昭和51年)には下関市地方卸売市場の青果部門が山の谷交差点北側に移転して下関市中央卸売市場に改称する(2008年(平成20年)に地方卸売市場に再転換)など、下関における物流の拠点ともなっている。この他、幹線道路である県道下関長門線・国道2号は山の谷交差点に起因する渋滞が深刻であることから、国土交通省(中国地方整備局山口国道事務所)が交差点の改良(立体交差化)と前後区間の拡幅工事を実施中です。

1901年(明治34年)5月27日 - 山陽鉄道 厚狭駅 - 馬関駅(現在の下関駅)間延伸と同時に、一ノ宮駅として開業。旅客・貨物の取扱を開始。当時は住吉神社付近に位置していた。
1906年(明治39年)12月1日 - 山陽鉄道の国有化により国有鉄道の駅となる。
1909年(明治42年)10月12日 - 線路名称制定。山陽本線の所属となる。
1916年(大正5年)1月1日 - 長門一ノ宮駅に改称。
1928年(昭和3年)11月19日 - 経路変更にともない、現在地に移転。
1960年(昭和35年)9月1日 - 貨物の取扱を廃止。
1975年(昭和50年)3月10日 - 山陽新幹線が岡山駅 - 博多駅間延伸により当駅乗り入れ。同時に新下関駅に改称。
1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道の駅となる。
2000年(平成12年)12月1日 - 新下関新幹線乗務員訓練センター開設。
2005年(平成17年)2月26日 - 山陽新幹線改札に自動改札機を導入。
電報略号 シセ
イヤ(長門一ノ宮駅時代)
駅構造 高架駅(新幹線)
地上駅(在来線)
ホーム 2面3線(新幹線)
2面2線(在来線)
乗車人員
-統計年度- 4,967人/日(降車客含まず)
-2010年-
開業年月日 1901年(明治34年)5月27日
乗入路線 2 路線
所属路線 ■山陽新幹線
キロ程 536.1km(新大阪起点)
東京から1088.7km
◄厚狭 (26.6km)(19.0km) 小倉►
所属路線 ■山陽本線
キロ程 520.9km(神戸起点)
◄長府 (5.9km)(3.7km) 幡生►
備考 直営駅
みどりの窓口 有
* 改称経歴
- 1916年 一ノ宮駅→長門一ノ宮駅










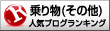


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます