
第1掃海隊の掃海艇みやじま いずしま あいしま です。Fバースでの護衛艦一般公開の時に整然と3艇メザシ係留されていました。
掃海隊群は、日本の海上自衛隊自衛艦隊隷下の掃海部隊。主に第二次世界大戦時に設置された機雷の撤去を任務です。

1952年(昭和27年)8月1日、保安庁(警備隊)発足に伴い、航路啓開業務は海上保安庁から保安庁に移され、海上保安庁から掃海船等76隻が移管された。これを受けて、同年11月1日、第二幕僚監部(後の海上幕僚監部)並びに横須賀及び舞鶴地方総監部に航路啓開部が置かれると共に、両地方隊に航路啓開隊が新編され、その下に第1ないし第10掃海隊が新編されました。昭和28年9月16日、地方隊の航路啓開隊は解隊されて、業務は新編された基地隊、基地警防隊等に移された。また、1953年(昭和28年)10月16日に地方総監部が改組されて航路啓開部が廃止。

1954年(昭和29年)10月1日に、長官直轄の部隊として第1掃海隊群(司令部、掃海艦「桑栄丸」、掃海艇「ゆうちどり」、第4掃海隊、第7掃海隊)が新編されました。この部隊は第2次世界大戦中に敷設された機雷の掃海業務が一段落ついた1969年(昭和44年)3月15日に、長官直轄から自衛艦隊に編入されました。

1961年(昭和36年)9月1日に第2掃海隊群(司令部、護衛艦「きり」、掃海艦「桑栄」、敷設艦「つがる」、敷設挺「えりも」、第32掃海隊、第33掃海隊、第34掃海隊)が新編され、自衛艦隊に編入されます。
1977年(昭和52年)4月から1978年(昭和55年)3月までのポスト4次防「基盤的防衛力構想」では、東西日本海域にそれぞれ1個ずつの、合計2個掃海隊群を維持するものとされ、それと同時に地方隊の任務達成上欠くことができない部隊として、各地方隊にも掃海隊が置かれます。

1982年(昭和57年)度末には、2個掃海隊群及び地方隊に計14個掃海隊を保有していた。03中期防衛力整備計画(平成3年度-平成7年度)では、ペルシャ湾派遣掃海部隊の成果を反映した新型の07MSC「すがしま」型(510トン)2隻等の建造が計画されました。
2000年(平成12年)3月に、08中期防衛力整備計画(平成8年度-平成13年度)を受けて、第1・第2掃海隊群を合併して1個掃海隊群とし、併せて掃海隊群の司令部機能を充実させるという機雷戦部隊にとって大きな改編となりました。
2004年(平成16年)3月に第3掃海隊が廃止になり、以後4個掃海隊編制になる。

掃海部隊は、旧日本海軍解体後も特別に存続が許され、苛酷な環境の下で黙々と掃海作業に従事し、朝鮮戦争では特別掃海隊を派遣し、また保安庁警備隊時代も相当数の掃海艇を擁してきた沿革があり、世界中の海軍の中でも海上自衛隊の実力が特に高い分野であるとされています。
掃海隊群の編成 08中期防衛力整備計画(平成8年度-平成13年度)以降は次の編成となっています。

掃海隊群
掃海隊群司令部(横須賀基地船越地区)
直轄艦艇
うらが(横須賀基地)
ぶんご(呉基地)
第1掃海隊(呉基地)
第2掃海隊(佐世保基地)
第51掃海隊(横須賀基地)
第101掃海隊(呉基地)
掃海業務支援隊(横須賀基地船越地区)
呉掃海業務支援分遣隊(呉基地)











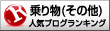


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます