
車両所公開で展示されていた、EF56の1次型を改造したEF59です。
EF56は、旅客列車牽引用に性能的にはEF53形をベースに、暖房用の蒸気発生装置(SG)を追加して冬季の暖房車の連結を不要とした画期的な形式です。川崎造船所(川崎重工業)・川崎車両、三菱電機、日立製作所で12両が製造されています。
パンタグラフは、機器(SGボイラー)配置の都合で中央に寄せて取り付けられており、形態上の特徴となっています。1937年製の1~7号機は丸みを帯びた車体で、1940年(昭和15年)に製造された8~12号機は角張った車体に変更されるとともに先台車が外側軸受方式に変更。13号機として製作されていた車両は、出力増強型の電動機を装備したため、EF57形(EF57 1)として落成しています。1969年(昭和44年)より、5両が山陽本線急勾配区間の「瀬野八」補機用のEF59形に改造され、残りの車両は引き続き荷物列車牽引に充当されました、EF58形の転入に伴い、1975年(昭和50年)に全車廃車。また、EF59形に改造されたものも、1987年(昭和62年)までに廃車されました。

山陽本線の瀬野 - 八本松間では、1962年に電化が実施されたあとも貨物列車用の補機としては従来のD52形蒸気機関車を使用していたが、1963年(昭和38年)度末に岡山 - 広島間の貨物列車を電気機関車に置き換える際、瀬野八の補機も全面的に電気機関車に置き換えることが決定されました。計画段階では、EF60形をベースに新形式機関車を製造する案や、EF10形あるいはEH10形を改造する案、ED60形を増備して使用する案なども出されたようですが、置き換えにかかる経費を考慮し、信越本線電化および東北本線・高崎線の客車列車の電車化により余剰となるEF53形を改造して補機とする案が採用されました。
当初、形式は最高運転速度85km/h以下のEF20形とする計画でしたが、特急列車は広島駅で補機を連結して広島 - 瀬野間で90km/hでの運転を行うため、最高運転速度85km/h以上のEF59形となりました。
1963年から瀬野機関区に配置され、蒸気機関車に代わり瀬野八の後補機運用に使用されましたが、運用区間や連結両数は列車によって異なっていました。基本的に貨物列車は重連で補機運用を行い、一部の荷の軽い(600t以下)貨物列車と荷物列車、旅客列車については単機で補機運用でした。また、貨物列車については瀬野駅に停車して後部に補機を連結するのが基本でしたが、速達性を要求される10000系貨車を使用した高速貨物列車については広島操車場にて補機の連結が行われ、瀬野駅は通過。寝台特急列車のように瀬野駅が通過設定となっている旅客列車については、広島駅から補機が連結されました。瀬野から八本松にかけての勾配区間での後押しの任を終えたEF59形は、八本松駅手前で走行開放を行っていたが、一部の列車については走行開放を行わず連結したまま西条まで走行し、そこで列車より開放されていました。瀬野八は上り方向への片勾配であるため、後補機の勤めを終えたEF59形は下り列車に連結されず、回送列車で瀬野に戻っていましたが、列車密度の高い山陽本線ゆえに単機で回送されることはなく、最低でも重連、最高で六重連を組成して回送を行っていたとのことです。

EF56は、旅客列車牽引用に性能的にはEF53形をベースに、暖房用の蒸気発生装置(SG)を追加して冬季の暖房車の連結を不要とした画期的な形式です。川崎造船所(川崎重工業)・川崎車両、三菱電機、日立製作所で12両が製造されています。
パンタグラフは、機器(SGボイラー)配置の都合で中央に寄せて取り付けられており、形態上の特徴となっています。1937年製の1~7号機は丸みを帯びた車体で、1940年(昭和15年)に製造された8~12号機は角張った車体に変更されるとともに先台車が外側軸受方式に変更。13号機として製作されていた車両は、出力増強型の電動機を装備したため、EF57形(EF57 1)として落成しています。1969年(昭和44年)より、5両が山陽本線急勾配区間の「瀬野八」補機用のEF59形に改造され、残りの車両は引き続き荷物列車牽引に充当されました、EF58形の転入に伴い、1975年(昭和50年)に全車廃車。また、EF59形に改造されたものも、1987年(昭和62年)までに廃車されました。

山陽本線の瀬野 - 八本松間では、1962年に電化が実施されたあとも貨物列車用の補機としては従来のD52形蒸気機関車を使用していたが、1963年(昭和38年)度末に岡山 - 広島間の貨物列車を電気機関車に置き換える際、瀬野八の補機も全面的に電気機関車に置き換えることが決定されました。計画段階では、EF60形をベースに新形式機関車を製造する案や、EF10形あるいはEH10形を改造する案、ED60形を増備して使用する案なども出されたようですが、置き換えにかかる経費を考慮し、信越本線電化および東北本線・高崎線の客車列車の電車化により余剰となるEF53形を改造して補機とする案が採用されました。
当初、形式は最高運転速度85km/h以下のEF20形とする計画でしたが、特急列車は広島駅で補機を連結して広島 - 瀬野間で90km/hでの運転を行うため、最高運転速度85km/h以上のEF59形となりました。
1963年から瀬野機関区に配置され、蒸気機関車に代わり瀬野八の後補機運用に使用されましたが、運用区間や連結両数は列車によって異なっていました。基本的に貨物列車は重連で補機運用を行い、一部の荷の軽い(600t以下)貨物列車と荷物列車、旅客列車については単機で補機運用でした。また、貨物列車については瀬野駅に停車して後部に補機を連結するのが基本でしたが、速達性を要求される10000系貨車を使用した高速貨物列車については広島操車場にて補機の連結が行われ、瀬野駅は通過。寝台特急列車のように瀬野駅が通過設定となっている旅客列車については、広島駅から補機が連結されました。瀬野から八本松にかけての勾配区間での後押しの任を終えたEF59形は、八本松駅手前で走行開放を行っていたが、一部の列車については走行開放を行わず連結したまま西条まで走行し、そこで列車より開放されていました。瀬野八は上り方向への片勾配であるため、後補機の勤めを終えたEF59形は下り列車に連結されず、回送列車で瀬野に戻っていましたが、列車密度の高い山陽本線ゆえに単機で回送されることはなく、最低でも重連、最高で六重連を組成して回送を行っていたとのことです。











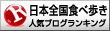


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます