
亀嵩駅は、松本清張原作の映画『砂の器』で一躍有名になり、この駅付近の温泉には多くの観光客が訪れる。

島根県仁多郡奥出雲町郡村にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)木次線の駅。亀嵩地区の主要施設・集落は駅から2kmほど安来側(東側)にある。

愛称は「少彦名命」(すくなひこなのみこと)。『古事記』では神皇産霊神(かみむすびのかみ)の子とされ、『日本書紀』では高皇産霊神(たかみむすびのかみ)の子とされる。大国主の国造りに際し、波の彼方より天乃羅摩船(アメノカガミノフネ)に乗って来訪した神。国造りの協力神・常世の神・医薬・温泉・禁厭(まじない)・穀物霊・知識・酒造・石など多様な姿を有する。『古事記』によれば、大国主の国土造成に際し、天乃羅摩船に乗って波間より来訪し、オホナムチ(大己貴)大神の命によって国造りに参加した。『日本書紀』にも同様の記述があり、『記』・『紀』以外の文献では多くは現れない神である。酒造に関しては、酒は古来薬の1つとされ、この神が酒造りの技術も広めた事と、神功皇后が角鹿(敦賀)より還った応神天皇を迎えた時の歌にも「少名御神」の名で登場する為、酒造の神であるといえる。ただし石に関しては記述よりそうした面が見られると想像されるだけであり、あくまで性質的なものである。創造における多様な面を持つ神ではあるが、悪童的な性格を有すると記述される(『日本書紀』八段一書六)。オホナムチ同様多くの山や丘の造物者であり、命名神として登場する。のちに常世国へと渡り去る。小さいと言われているが、「鵝(ひむし・蛾)の皮の服を着ている」と高御産巣日神の「わが子のうち、指の間から落ちた子」という記述からの後世の想像である。名前の由来について、『古事記伝』によれば「御名の須久那(スクナ)はただ大名持(オホナムチ)の大名と対であるため」とあり、名前が必ずしも体の大きさを表すわけではない。あるいは金井清一によれば「若き日の御子」の意とする説もある。また、この神が単独ではなく、必ずオホナムチと行動を共にすることから、二神の関係が古くから議論されている。

松本清張の小説『砂の器』にも登場した。ただし、映画『砂の器』(1974年)で撮影されたのは、同じ木次線だが、ホームは出雲八代駅、駅舎は八川駅だった。川又カメラマンによれば、亀嵩駅を使わなかった理由は「そばの看板が邪魔になったのと、崖が迫っていてカメラが引けなかったから」。但し、駅以外のシーンは亀嵩地区でもロケが行われた。また、2004年(平成16年)のテレビドラマ版では山口線の篠目駅、2011年(平成23年)のテレビドラマSP版では信楽高原鐵道雲井駅が亀嵩駅として使われた。
1970年代後半にはひらけ!ポンキッキでガチャピンが取材に来たこともある。

小さな木造駅舎をもった地上駅です。かつては相対式2面2線だったが、2番のりばの線路が撤去されて停留所構造となり、現在は駅舎側1番のりばのみの片側1面1線(備後落合方面に向かって左側)で運用されています。

かつての相対式ホームの跡が見られます。

駅舎には扇屋という蕎麦屋が入っており、乗車券の販売が同店の店主に委託された簡易委託駅(木次鉄道部管理)です。POS端末等の設置はなく、常備券のみを発券する。

木製の古い出札窓口が残っています。全国的に有名な名物の手打ち奥出雲そばは、前もって電話で予約すれば、列車到着に合わせてホームで受け取ることも可能。

1934年(昭和9年)11月20日 - 木次線の出雲三成駅 - 八川駅間延伸により開業。
1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道の駅となる。

電報略号 カタ
駅構造 地上駅
ホーム 1面1線

乗車人員
-統計年度- 35人/日(降車客含まず)
-2009年-
開業年月日 1934年(昭和9年)11月20日
備考 簡易委託駅












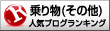


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます