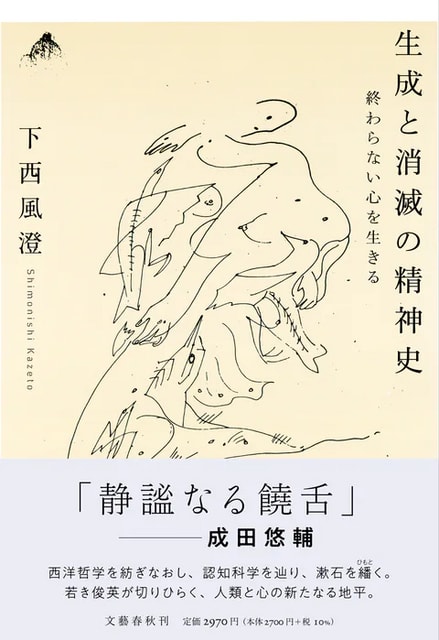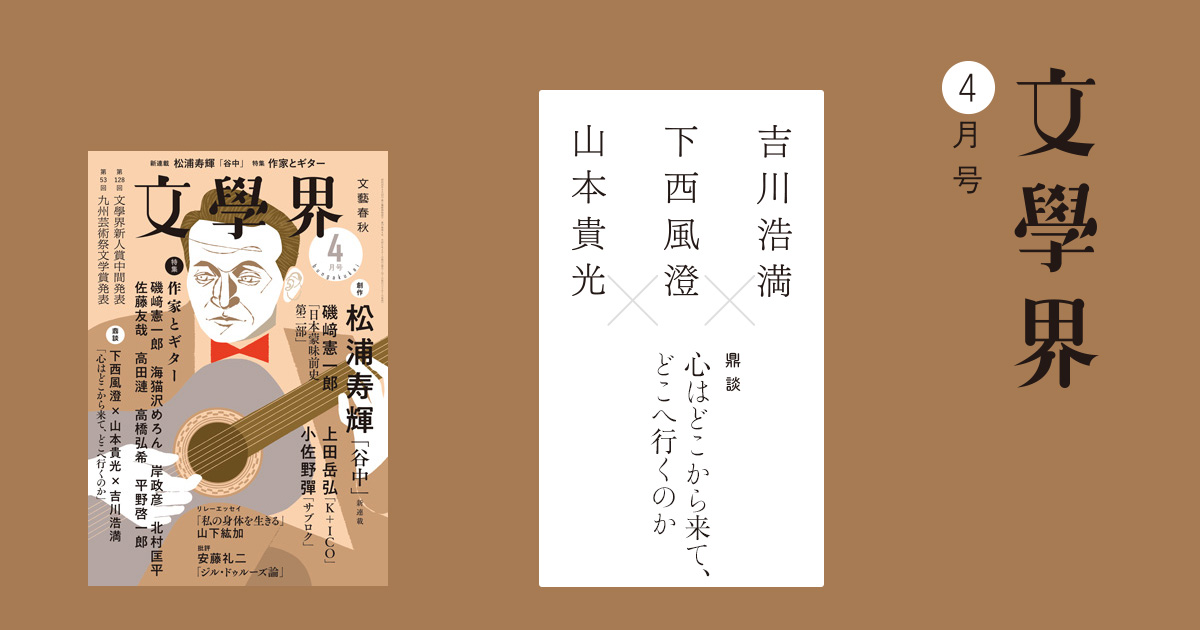本書は読売新聞で連載されていた小説が、単行本として出版されたものです。
最近よくいろいろな所で話題になる貧困に関することや、知的・精神的な偏りのことや毒親問題などを
盛り込んで、’90年代後半を舞台に書かれた小説です。
著者の川上未映子さんは容姿に恵まれた人ですが、大阪の北新地のクラブに勤めていたとのことです。
夜の世界に身を置いていたことで、学校に行っていたり昼間に働いていると目にしない様々な人を見たことも、
本作を書く上で役立っているのでしょう。
ここでは本書を「主体の生成」という観点から見て感じたことを書いてみたいと思います。
【あらすじ】(ネタバレあり)
主人公の花は、風呂なし、共同トイレという安アパートでスナックのホステスの母親と暮らしています。
母親は稼いだお金は箱に入れ、必要なときに出して使っていて、花もそこから必要なお金を出し使っています。
花は学校の成績は良くありませんが、不良グループとつるむこともなく、距離を置いていますが、
向こうからはからかわれたりします。
母親のアパートで出会った黃美子さんが、その不良たちと何かやり取りした後に、不良たちは
花をからかったりしなくなったことで、花は黃美子さんに一目置き、惹かれていきます。
高校に入った花は母親から離れるためのお金を貯めようと遮二無二にバイトを頑張りますが、
貯めたお金を母親の彼氏に盗まれます。
そのときに黃美子さんに再会し、花は母親の元を出て黃美子さん暮らしながら飲み屋を始め、嫌な思いもしますが、
それなりに楽しく暮らしていきます。
しかしながら火事で店が焼けたので、花は再び店を開店するためにカード詐欺などをして、
まとまったお金を得ようと頑張るのでした。
【あらすじに見られる主体の生成】
もともと花は普通にバイトをして、少しずつお金をためていますが、そのお金を盗まれたことで、
母親のもとを離れ、黃美子さんと暮らしながら飲み屋で働き出します。
母親の元を離れることを諦めるのではなく、黃美子さんと暮らすことで家を出るというかたちで、
主体的な動きをしますが、学校や普通のバイトでは出会うことのない黃美子さんと出会うことが無ければ、
そうはならなかったでしょう。
そこでそれなりに充実した暮らしをしたことで、店が焼けた際に、それまでの暮らしを取り戻そうと考えて、
黃美子さんとは別にカード詐欺を始めるところでも主体性を発揮します。
そして知り合った蘭や桃子なども使いカード詐欺でもっと稼ぎはじめますが、その二人はそれほど当てにならないので、
花が計画を考え、中心となり詐欺を続けるほど花はしっかりとしていくのでした。
そのあたりで花は、黃美子さんの認知能力の偏りを考え、彼女には詐欺に参加させないということも決め、
他の3人で詐欺を続けていきます。
他の二人は警戒心も薄いので、家の中の規則も花が決め、仕切っていくと言うところにも、
花に主体性が生成してきたことが伺えます。
本書を読んで考えるに、高校や大学などは学力の近い生徒が集まるので、自分とは違うタイプの人と出会うことが少ないことも、
高校生や大学生の主体が生成しにくいことに、繋がっているのでしょう。
日本では他の先進国よりも発達障害と診断される人が多いとのことですが、
学力で輪切りにする入試制度などが、大きな影響を与えているのでしょう。
「お金は生死のルールを超越していると見せかける」──作家・川上未映子の死生観と「お金」への思い
最新作『黄色い家』は「黄色」と「お金」を巡る物語だ。世界的にも今、最も注目を浴びる作家の一人である川上未映子が、 資本主義と分かち難いという死生観や、 今作で拓け...
Vogue Japan