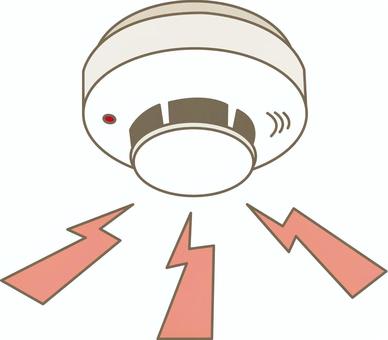東京都は5月22日、顧客らから理不尽な要求を突きつけられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止条例制定に向けた基本方針を取りまとめた。民間事業所だけでなく、役所や学校などあらゆる職場でカスハラを禁じ、防止に向けた都や顧客、事業者の責務を明示し、この方針を基に条例案を策定し、今年秋の都議会での成立を目指すという。
最近よく「カスハラ」という言葉を耳にするが、これはあくまで顧客が理不尽な要求を突きつける場合に限定していると思うが、サービス業においては、顧客からのサービス向上に資する改善提案や建設的な意見がなされることが多々あるので、その線引きが大変難しいと思われる。自分の現役時代の会社では、お客様からの苦情、要望、意見を賜る組織があり、当初は、「顧客サービス業務室」とかいっていたが、後に、「サービス推進部」さらに「お客さま相談室」とか「お客さまサポート室」とかの名称に変わっていったと記憶する。要するに、お客さまの声を大事にして、ご要望や、ご意見を聞く組織を整備し、お客さまの視点で発想、行動し、サービスの改善や向上を目指そうという趣旨である。お客さまからクレイムを受ける組織でもあるが、ネガティブではなく、前向きにポジティブのとらえ、サービスの向上に結び付けようとするものである。
よく利用してくれている常顧客の場合は、線引きが極めて微妙である。業界内の隠語で、今は、死語になっているかも知れないが、昔「UUU」という言葉があった。「うるさい、うるさい、うるさい」の頭文字を取ったものであるが、頻繁に利用してくれている「常顧客」でもあることから、サービスの内情をよく知っていて、いろいろな要望や改善提案をあげてくることも多い。お客さまの声を形にして、サービス向上を図った事例も少なくない。
個人的には、ドイツに勤務中、よく利用してくれていたあるUUUというか常顧客と親しくさせてもらっていた。フリークエント・トラベラーであるがゆえに、いろいろなサービスについて、いろいろ注文や要望や意見を述べてくるが、理不尽というより、建設的なものが多かったような気がする。本人は、過去に会社側の対応が悪かった時、土下座させたことがあるとかの武勇伝を語ることもあったが、我々には、そういう振る舞いはほとんどなかった。
昔は、機内に新聞が搭載されていて、機内で新聞が読めるという新聞サービスがあった。日本発については、最新の新聞の搭載が可能であったが、帰路便については、日本から搭載していった新聞を提供するので、どうしても2~3日遅れの古い新聞となってしまう。1985年頃、ヨーロッパで衛星版の新聞が現地で発行されるようになり、現地でも日本と同じ日付の新聞が読めるようになったが、暫くの間、欧州発便の機内では日本からの相変わらず古い日付の新聞だけがサービスされていた。親しくしていたUUUは、それに気づき、最新の新聞を搭載すべきと強い要望を本社に上げ、それに基づき、古い新聞に加え、最新の衛星版の新聞も搭載されるようになったことがある。古い新聞しか載せていないとクレイムをつけるだけなら、カスハラかも知れないが、衛星版の新聞も載せるべきと要望をあげるのは、サービスへの改善提案であるから、なんとも難しいところである。
また、1996年、成田発フランクフルト行の飛行機が離陸滑走中にトラブルを起こし、成田で乗客がシューターを使って機外に緊急脱出するという事故があり、シューターで機外に滑り降りた乗客の何人かが降りた時に尻もちをついて怪我をするという出来事が発生した。当時、緊急脱出のデモ用ビデオでは、シューターの下で客室乗務員が待機していて、尻もちをつかないように補助していたのである。ところが、安全規程に従い、乗務員は最後に降りなければならないので、 現実には、シューターの下には誰もいないのである。下に乗務員が待機して補助してくれると思って、思い切って滑り降りたが、誰もおらず尻もちをついて怪我をしてしまったわけである。その場にいた彼は、機内の安全ビデオの内容がおかしいとクレイムを付けたが、これがきっかけで、緊急脱出規定が変更され、機内のデモビデオも変更(下での補助要員が客室乗務員から一般の乗客に変更)されたのである。理不尽な要求だけに終始する「カスハラ」ついては、対策が必要かも知れないが、クレイムはネガティブな処理だけととらえず、前向きにポジティブな形で対応していくことも必要ではないかと感じる。