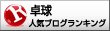落語家の三遊亭金翁さん(4代目金馬さん)が93歳で亡くなった旨のニュースが流れていた。名前を聞いただけでははじめは誰のことかよくわからなかったが、NHKの「お笑い三人組」で活躍していた小金馬さん(当時)のことであることがわかり、寂しい思いが込み上げた。「お笑い三人組」は、調べて見たら、1956年から1966年までテレビ放送されていたようで、まさにテレビっ子としては、最盛期の流行った番組の一つであった。生放送の公開バラエティ番組であったことも今では驚きである。
毎週火曜日夜だったと思うが、ほとんど毎回見ていたので、三遊亭小金馬、一龍齋貞鳳、江戸家猫八の三人組と楠トシエ、桜京美、音羽美子等の共演者も今でも鮮明に覚えている。今では、ほとんどの出演者が亡くなっているので、時代の流れを感じざるを得ない。「お笑い三人組」については、2019年に当時90歳でもまだ現役で活躍していた金馬さんのことを知り、下記の通り、ブログ(2019年12月6日)にも書いていた。お笑いを「ありがとう」と伝えるとともに、ご冥福をお祈りする次第である。
「12月5日、BS朝日のお笑い演芸館~10代から90代まで人気芸人集合SP~というタイトルを見て90代の芸人って誰だろうと思い、ずうっと見ていたら、何と三遊亭金馬師匠が90代の芸人として出ていてビックリ。風貌は昔とあまり変わっておらず、とても90才には見えないほど若く矍鑠としており、創作ものの落語をやっていたが、大変面白かった。いまだに現役でやっていることに敬服するばかりである。
今の金馬師匠は長らく三遊亭小金馬としてよく知られていたが、一番馴染みのあったテレビ番組がNHKの「お笑い三人組」であった。調べてみたら、1956年~1966年まで放送されていたようであるが、当時は、毎週火曜日欠かさず見ていた。三人組として、三遊亭小金馬、一龍齋貞鳳、江戸家猫八に、楠トシエ、音羽美子、桜京美がからんでの面白い公開バラエティ番組であった。貞鳳さんと猫八さんと桜京美さんはすでに亡くなられているようであるが、舞台のシーンが目に浮かぶほど懐かしい番組であった。とくに、「八ちゃん、おたまちゃん、うー」というギャグが懐かしく思い出される。もう60年も前のことなのに、鮮明に覚えているからビックリする。
当時は、テレビ創成期でこのようなバラエティ番組が流行っていたが、よく見ていたのは、「シャボン玉ホリデー」「てなもんや三度笠」「夢であいましょう」「光子の窓」等懐かしいものばかり。テレビが白黒からカラーに移っていく頃なので、我々は、まさにテレビとともに大人になっていった感じである。すでにザ・ピーナッツ、藤田まこと、クレージーキャッツはじめすでに亡くなっている人も多く、年月の経過を痛感するが、青春プレイバック、あの時代に戻りたい気がする。」
お笑い三人組の懐かしい映像: https://youtu.be/rBIxxYs9Uvg
訃報のNHKニュース(8/27): https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220827/k10013790101000.html