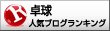最近、マスコミでもコンプライアンスという言葉が出てくることがある。コンプライアンス(compliance)とは、「法令遵守」を指し、企業や個人が法令や社会的ルールを守ることを意味する。コンプライアンスに求められるのは「法令を守れば良い」というわけではなく、企業倫理や社会規範などに従い、公正・公平に業務を行うという意味も含まれるという。個人的には、40年以上も前、本社でインターラインの国際関係の仕事を担当していた時、よく使っていた言葉なので、この言葉を耳にすると大変懐かしい思いになる。
我々が業務上よく使っていたのは、PCCC、LMCC、 OAAという用語である。何の省略か確実ではないが、PCCCは、太平洋線運航エアライン Pacific Carriers Compliance Committee、LMCCは、欧州線運航エアラインLocal Managers Compliance Committee、OAAは、Orient Airlines Associationの略で、東南アジア線運航エアラインで構成される委員会のことである。当時、航空運賃の値下げ競争が激化していて、各社の収益を圧迫する事態が発生していたため、各社の話し合いを通じて、コンプライアンス活動を通じ法定の運賃を遵守し、利益を確保しようという集まりである。自分は、PCCCとOAAを担当していて、各社との話し合いを頻繁に行っていたが、PCCCの会議はすべて英語だったので、苦労したことを覚えている。印象に残っていることは、いっぱいあるが、PCCCでは、米国には談合を禁じる厳しい独占禁止法があり、当時、パンナム、ノースウエスト等米国社がそれを理由に会議場から席を立つということもよくあった。新聞に掲載された安売りのツアー広告を取り締まったり、エアオンという格安航空券のテストバイ(試買)を行って摘発したりもしていたが、今や、安売りも市民権を得るような時代になっているので、時の流れを感じる。
また、OAAに参加していたのは、日本の他に、大韓航空、中華航空、フィリピン航空、キャセイ航空、シンガポール航空、マレーシア航空、タイ国際航空等であった。OAAでは、安売り防止のためには、本音での話合いができるように、懇親活動に力を入れていた。仲良くなれば、人を裏切るような抜けがけの安売りはできなくなるであろうという日本的というかアジア的な発想からであった。各社の営業担当者との会議や飲み会も頻繁に行われ、オフショア・ミーティングとして、札幌や韓国のプサンや済州島(懇親ゴルフ)への懇親ツアーに出かけたこともあった。皆、仲良くなって、変な安売りもなくなり、販売業務もスムーズに運んでいたと記憶する。その時キャセイの販売トップの英国人は、その後、英国航空の社長にもなったほどの優秀な人材であった。インターライン関係の仕事は大変面白かったが、3年程度でお役目御免となり、ドイツのフランクフルトに異動することになった。振り返ると古き良き時代であった。