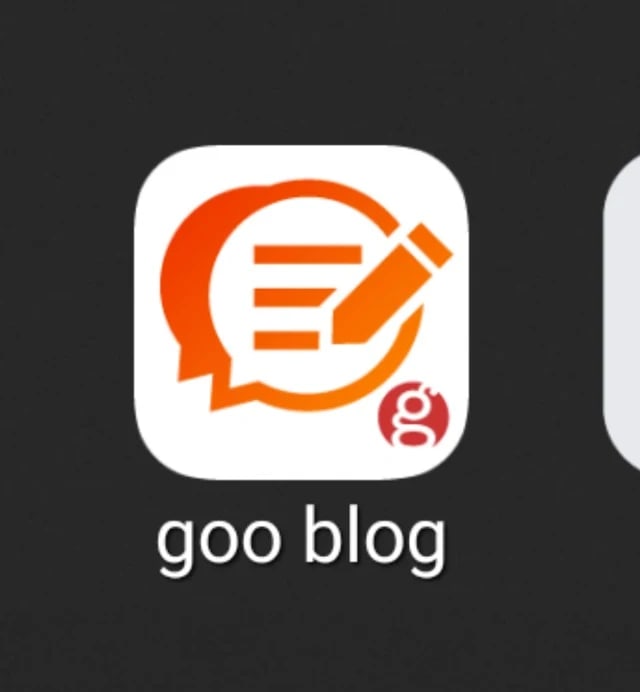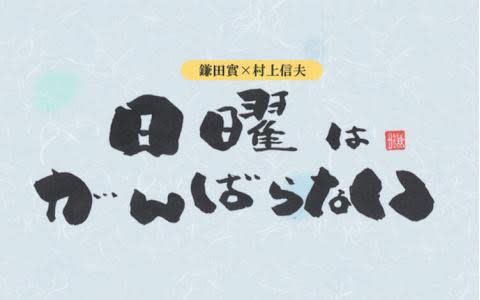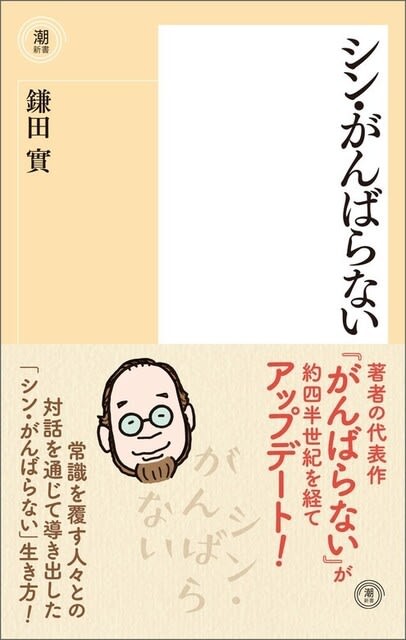日曜の朝は、6時20分から文化放送の鎌田實×村上信夫「 日曜はがんばらない」を聴いているが、21日の放送で、幸運にも3回目となるが自分の投稿が取り上げられた。最初は、2022年6月19日に「定年にまつわる投稿」で、2回目は、2022年12月25日に「この1年を振り返って」というテーマで読み上げられたのに次いで、今回は「健康に関する相談」というテーマで投稿したものである。これで、今までに投稿したものがすべてオンエアされたことになり、嬉しい思いである。
今回は、テーマに従い、自分が抱えている不整脈・心房細動のカテーテル・アブレーション手術について相談したもので、鎌田先生も経験しているので、何かアドバイスがいただけるかなと思い投稿したものである。事前の連絡などは勿論なく、寝坊したりすると聴けない時もあるので、たまたま番組を聴いていてよかった。相談は、手術を受けるべきかどうかの内容であったが、きちんと相談に答えてくれた。
過去2度の放送については、記念と思い、radikoのタイムフリー機能を使って、その音声をパソコンにダウンロ-ドし、YouTubeを作成したが、先日、自分の部分の1分だけなのに、YouTubeから意外にも著作権違反の通告を受け、あと2度同じ違反を犯した場合は、アカウントを凍結するとの強い警告を受けた。たった1分でもラジオ番組の内容をそのままYouTubeにアップすることは、著作権違反と判定されるようである。アップしてから1年以上も経った後なので、無作為チェックでも行っているものと思われ、注意を要する。従って、今回はMP4として自分のパソコンに保存することにとどめることにした。
精神科医である和田秀樹著の「60代からの見た目の壁」を図書館で借りることができた。最近この手の本を読むことが多いが、一度読んだら十分なので、図書館で借りることが多い。人気がある本は、数ヶ月待つことはよくあることなので、順番が来るのを気楽に待っている。今までに和田氏の本は、「80歳の壁」「ぼけの壁」はじめ何冊か読んでいるが、高齢者の生き方について彼の考え方は自分の思いに近いので、共感することが多い。
「60代からの見た目の壁」は、60代は「見た目老化の分かれ道」で、60代なのに40代に見られる人と80代に見られる人の違いはどこか?がテーマである。
筆者は、60代からは「見た目が10割」でおしゃれを推奨する。
・見た目は寿命の長さにも影響する
・粗食は見た目年齢を上げ、健康も損なう
・65歳過ぎたら「健康至上主義」と決別せよ
・知性こそ見た目を引き立てる妙薬
と強調する。
個人的には、がっかりしたくないので、ほとんど鏡を見ることがないが、写真に写った自分の姿をみて、愕然とすることが多い。禿げ上がって、肌に張りがなく、シミが目立ち、覇気がないとひしと感じる。テレビに出てくるお年寄りを見て、その年齢が自分の同じということを知って、ショックを受けることも多々ある。年齢を偽ることなく、堂々と実年齢で勝負し、年齢バイアスを捨てる必要がありそうである。最近は、着る機会もあまりないからといって、新しい洋服を買うのを控えているが、それではいけないのかも知れない。見た目の年齢を高めるには笑いが重要であるともいう。女性の見た目が若いのもよく笑うからかもしれない。
年齢感覚からみると、「サザエさん」に出てくるお爺さんの磯野波平さんの年齢は54歳という設定というからビックリであるが、井上陽水の「人生が二度あれば」では、年老いた父の年齢は65歳、母の年齢は64歳である。今や、歌手の石川さゆりは66歳、山本リンダは72歳、アグネスチャンは68歳と皆お婆さんという印象とはほど遠い。テレビで歌う今の姿を見ても、それぞれ年齢に関係なく生き生きしていて、年齢を感じさせない。
和田先生のアドバイスに従って、もっと見た目に気とお金を使ったほうがいいかも知れない。どうせあと数十年しか生きられないのだから、おしゃれして、お化粧して、人生をいっぱい楽しまないと損!その意欲こそが、見た目年齢の壁を打ち破る秘訣というから、そうしたいものである。また、若さを保つには年を取っても異性にもっと関心を持つ必要もありそうである。
ちなみに、本の目次は下記のようになっている。
■目次
1章 見た目年齢の格差はなぜ起こるのか
2章 見た目年齢若返りはおしゃれから
3章 見た目年齢が若返る食べもの
4章 知性がないと見た目は若返らない
5章 見た目をかっこよくする生き方
年をとったら、人目を気にせず、おしゃれし、知的関心を持つことが若さを保つ源かも知れない。気になる人は一読することをお薦めする。
人生が二度あれば(井上陽水 今聴くとジーンと来る): https://www.youtube.com/watch?v=1HCtX5bohVc
日曜朝の文化放送「日曜はがんばらない」のプレゼント応募で、鎌田實さんの「シン・がんばらない」という新書(潮出版社)が運よく当選し、早速読み始めてみた。著者の代表作『がんばらない』が20年の時を経てアップデートされたものという。筆者によると、「シン」というのは、狭義には「新」「深」「心」、広義には「真」「浸」「慎」「神」「信」というようないろいろな意味を込めているという。ラジオ番組は毎週聴いて元気をもらっているが、そのタイトルは、この本から来ているようである。
第1章 シン・生き方では、ソロ活のことが触れられていた。最近、「孤独のグルメ」とか「ぼっちキャンプ」とかソロを楽しむアクティビティ(ソロ活)が注目されている。一人で温泉旅行に出かけたり、外食したり、カロオケに行ったり、ソロ活の楽しみが支持されつつある。ソロ活は独身者が一人で楽しむための活動ということではなく、既婚者にも当てはまるという。旅先までは一緒に行くし、宿も同じ、でも現地に着いたら基本は別行動でそれぞれが行きたい場所にソロで行くといった謂わばパートタイムソロ旅も珍しくないと紹介されているが、我が家の場合も全くその通りで実践している。旅行に行く時は、必ず旅行スケジュール表を作成しているが、そこには、午前中-自由行動などと書くこともよくある。ゆっくりしたい妻といろいろ見たい夫との折衷案である。いつも同じ行動を取る必要はないとの提案に大賛成である。
本の中で、朝井麻由美さんというフリーライターのソロ活を紹介している。彼女は「ソロ活女子のススメ」という本を2019年に書き、2021年には、テレビ東京で江口のり子さん主演でドラマ化され、人気を博したようである。まさに積極的にひとり時間を楽しむことを意味する「ソロ活」を扱った人生応援ドラマで何回か見た記憶があるが、まさに我々にも適用されることに妙に納得するものである。主役の女性は、好きな時に好きな場所で、ひとりでしか味わえない贅 沢な時間を過ごすため、今日も新たな“ソロ活”を探し求めるという...人気ドラマのようで、今年4月から、毎週水曜深夜1時からシーズン4が放送され、台湾もドラマの舞台になるようで興味津々である。深夜なので、録画してちょっと覗いてみようと思う。
今年も師走を迎え、あと1週間となったが、2023年の出来事を振り返る「今年の十大ニュース」が話題となる時期が来た。ロシアによるウクライナ侵略が今年も相変わらず続いている中、イスラエルとハマスとの悲惨な戦闘が新たに始まり、日本でも暗いニュースばかりが目立つ。明るいニュースは、WBCで日本が世界一になったことや大谷選手がホームラン王や満票のMVPを獲得したこと位で、後は、物価高騰・円安・増税問題、防衛費倍増問題、統一教会問題、ジャニーズ問題、マイナ保険証問題、大阪万博問題、自民党パーティ券裏金問題、木原事件等々ネガティブな話題ばかりで、支持率もどん底で失政続きの岸田政権もまもなく終焉を迎えようとしている。また、同年代で親しみのあった歌手や著名人がお先にと多数旅立って行ってしまった。
我が家では、毎年、その年の出来事を振り返り、「我が家の十大ニュース」として記録を残しているが、すでに37年も続けている。十大ニュースを振り返るだけで、我が家の出来事が鮮明にタイムスリップする。今年は、海外旅行に出かけることもなく、総じて、大きな出来事はなかったが、何もないことがいいことだともいえる。この十大ニュースについては、自分史の1ページにもなっているが、1年前に文化放送ラジオ番組「日曜はがんばらない」への投稿が紹介されたこともあった。来年はどんな年になるであろうか?海外旅行にも行きたいが、103カ国目は夢のまた夢か。。。
今年の十大ニュースは、
1 パート卒業 12月
2 北陸旅行~墓じまい/納骨 8月/11月
3 伊豆大島旅行 11月
4 熱海旅行 6月
5 不整脈診断 2月
6 コロナ感染 8月
7 フランスから外人ゲストCARE 10月
8 古希ゴルフ旅行 2月
9 次男家族帰国 12月
10 親族の死去 5月
「日曜はがんばらない」: https://youtu.be/oVUDINQei0s?si=hsdkcBnAKJtXEeUC
妻が20年続けていたパートの仕事を12月をもって卒業することになった。貯めていた年休があるので、11月30日が最後の日となった。会社では有志から花束をいただき、我が家でも花束で出迎えた。自分自身は、すでに自由人生活を15年も続けているが、妻もやっと仲間入りすることになったので、来年からは、二人そろって自由人となれそうである。人、皆いつかは卒業することになるが、どのタイミングかがポイントとなる。 今、このタイミングかというと、二人とも最近感じる下記思いが強くなってきたからである。
・親鸞聖人が9才で仏門に入る得度の式の際に詠まれた無常を謳った「明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかは」の通り、親鸞が自分の命を桜の花に喩え、「明日自分の命があるかどうか分からない、だからこそ今を精一杯大事に生きていきたい」との思いを共有する。お釈迦様の【四門出遊】ではないが、老病死が迫ってくる現実に向き合う必要がある。
・ダ・カーポが歌う「今日がいちばん若い日」の歌詞にある通り、今を精一杯生きたいという思いを共有する。
・吉永小百合・天海祐希の映画【最高の人生の見つけ方】ではないが、「やりたいことリスト」を作り、精一杯遊びたいという思いを共有する。
・“DIE WITH ZERO”(ビル・パーキンス著)という「ゼロで死ね」の思いを共有する。喜びを先送りにしてはいけない。今大事なことはお金を貯めることではなく、お金を使うことであり、やりたいこともやらずに、無駄にお金を残す意味はない。
今後の理想の生活パターンは、3~5月(桜と新緑)、9~11月(紅葉)は、過ごしやすい日本、12~2月は、暖かいマレーシアやタイかオーストラリア、6~8月は、涼しいカナダかドイツでの海外ロングステイが夢である。その実現には、少し年を取りすぎた感は否めないが、今からでも遅くないとの思いもある。夜は近くのお寿司屋さんでささやかな慰労の夕食で労った。長い間お疲れ様でした。
「今日がいちばん若い日!」:https://youtu.be/vBzpfj8K25w?si
「旅のつづき」(最高の人生の見つけ方主題歌):https://youtu.be/CGxUsboDKzc?si
9月26日の日テレの「カズレーザーと学ぶ」の中で、令和マネー新常識の一つのテーマとして、ビル・パーキンス著の“DIE WITH ZERO”(ゼロで死ね)という本に書かれた「人生が豊かになりすぎる究極のルール」が紹介されていて、物凄く興味が惹かれた。この番組は、なかなかタメになる内容が多く、今回も大変勉強になった。この本のことは初めて知ったが、2020年に発売された人気本であることがわかり、ネットでいろいろ調べてみた。
ネットで紹介されている本書の要点は、
- 喜びを先送りにしてはいけない。限られた時間の中で幸福を最大化するためには、人生の早いうちに良質な経験をすることが大切である。
- どんな金持ちも、あの世にお金は持っていけない。だからこそ死を意識し、「ゼロで死ぬ」を実践すべきだ。
- 人生をよりよいものにするには、お金、健康、時間という人生の3大要素のバランスをいかに取るかが重要になる。
- 物事には賞味期限がある。そのチャンスを逃さないためにも大胆に行動すべきだ。リスクを取らないリスクを過小評価してはならない。
となっていた。また、下記のような要約が紹介されていた。
『日ごろから、自らの死を意識して生活している人は少ない。人は人生が永遠に続くかのように日々を生きている。だからこそ未来に希望を抱き、老後に備えて貯金をするのだ。これは一見すると合理的な行動である。だがその結果、喜びを先送りにし、やりたいことを我慢してはいないだろうか。何人たりとも時間には抗えない。だからこそ、限られた時間の中で幸福を最大化するために行動すべきだ。そしてそのタイミングは「今」である。お金を無駄にするのを恐れ、チャンスを逃しては本末転倒だ。大切なのは、どうすれば幸せになれるかを考え、そのために惜しまずお金を使うことである。そして適切なタイミングで、ふさわしい経験をすることで、人生は豊かになる。老後のために貯金するのも決して悪いことではない。だがそれに固執していては、貴重な時間を浪費しかねない。
お金はライフエネルギーだ。ライフエネルギーとは、何かをするために費やすエネルギーのことを指す。たとえば仕事は、「ライフエネルギーを消費する代わりに、お金を手にする活動」と言い換えられる。収入と時間、カロリーと運動などは、トレードオフの関係にある。このライフエネルギーを意識すると、衝動買いや悪い生活習慣を見直すことができる。「30万円の時計は何時間分の労働に値するのか」、「目の前のクッキーのカロリーを消費するために、どれくらい走らなければいけないのか」など、ライフエネルギーとして計算できるようになるからだ。とはいえ、節約ばかりしているのも考えものだ。その時しかできない経験の機会を失ってしまうと、世界が必要以上に小さな場所になってしまう。そうならないためにも著者が提唱するのは、本書のタイトルでもある「ゼロで死ぬ」ということだ。必要以上にため込むのではなく、今しか味わえない経験に時間と金を費やす。これを突き詰めると「ゼロで死ぬ」というところに行きつく。
《思い出はあなたに配当を与える》
著者が20代の頃、ルームメイトが旅行資金を工面するために多額の借金をした。当時の著者には、その行動がはなはだ理解できなかった。そのルームメイトはこれといった予定を決めず、単身ヨーロッパへ旅立った。数カ月後、戻ってきたその彼は、体験談を聞かせたり、写真を見せたりして、旅によって人生がいかに豊かになったかを著者に説き、「返済は大変だったが、旅で得た経験に比べれば安いものだ。だれもあの経験を僕からは奪えない」と語った。
このエピソードからわかるのは、「経験がいかに大切か」ということだ。人生は経験の総量によって決まる。私たちは小さい頃から、「いざという時のためにお金を貯めよう」と聞かされて育つ。しかし勤勉に働き、喜びを先送りすることだけが美徳ではない。人生に最後に残るのは思い出だけだ。だからこそ、早いうちに様々な経験をすることが重要なのだ。思い出は金融投資と同様、私たちに配当を与えてくれる。その瞬間の喜びだけでなく、あとから振り返ることで、当時の風景や感情を追体験できる。これはかけがえのない宝物だ。そして人生の早い段階で最良の経験を積めば、思い出の配当をより多く得られるのである。』
旅行の思い出作りにお金を使ってきた自分にとって、普段感じていた思いを後押ししてくれる内容に勇気づけられるとともに今後も実践していきたいという思いが込み上げてきた。なかなか「ゼロで死ぬ」境地に入るには不安が伴うが、その意識を持って人生を過ごすことは大事だと思う。この本を読んだら、人生の景色がガラリと変わるものと確信する。