きのう、佐倉の国立歴史民俗博物館(歴博)に出かけてきました。
考えてみれば、2週間も帰省したこともあって、クルマを3週間近く動かしていません。ヘタしたらバッテリーが上がってしまう
どこかにドライブしよ
ということで、約10年ぶりになる歴博(前回の探訪記)に行ってきた次第です。
戸田東ICから外環道に乗って、初めて 三郷以西まで行き、高谷JCTから東関東自動車道に入り、途中、
三郷以西まで行き、高谷JCTから東関東自動車道に入り、途中、

火災現場の近くを通り過ぎ、四街道ICで一般道に降り、トータル約77kmを1時間10分 で走りきって、歴博に到着
で走りきって、歴博に到着 (写真は帰り際に撮ったもの)
(写真は帰り際に撮ったもの)
入館前に、一応、閉館時刻を確認すると、冬期間ということで「16:30 」だそうで、約7時間もあります。
」だそうで、約7時間もあります。
これなら余裕 ですな…
ですな…
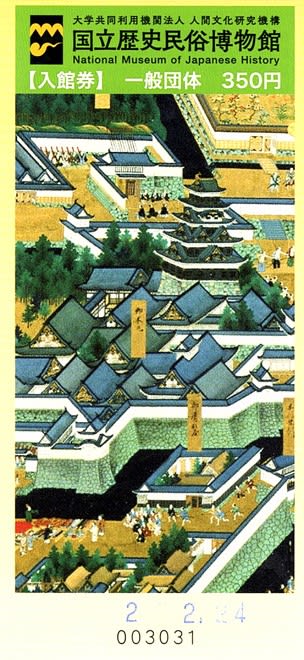 そして、観覧券を買おうとすると、おっと、JAF会員割引があるじゃございませんか
そして、観覧券を買おうとすると、おっと、JAF会員割引があるじゃございませんか 団体料金で観られる
団体料金で観られる
スマホアプリで電子会員証を窓口の職員さん に見せると、
に見せると、
「350円になります」
って、え"  一般料金600円が350円ですって
一般料金600円が350円ですって
こんなに団体料金の割引率の大きな施設ってほかにありますか
もちろん、Lucky でございます。
でございます。

さて、歴博の展示物は複製 が多くて、美術鑑賞
が多くて、美術鑑賞 には不向きですが、日本史と日本各地の風習を勉強
には不向きですが、日本史と日本各地の風習を勉強 するには、とにかく情報が多くて、日本史の史料集
するには、とにかく情報が多くて、日本史の史料集 が3Dで目の前に展開される感じです。
が3Dで目の前に展開される感じです。
そんなわけで、この記事では、歴博でしか見られない巨大かつ精巧なジオラマたちを中心に据えたいと思います。
 まずは沖ノ島。
まずは沖ノ島。
10年前にも観て感嘆し、その後(2017年)、沖ノ島が世界文化遺産に指定されてからは、マスコミにも取り上げられることが増えて、TV番組や宗像大社(記事はこちら)や九州国立博物館(記事はこちら)で紹介ビデオを観ては、このジオラマの写真を改めてじっくり観たりしておりました。
沖ノ島は、Wikipediaから引用すれば、
島は全域が宗像大社の私有地であるため、まず大前提として宗像大社の許可が無ければ(公権力の行使を除いては)島に上陸、立ち入ることはできない。(中略)
特別な立入許可に関しては、地元青年団(玄海未来塾など)による清掃奉仕、宗像系神社(厳島神社や弁財天)の神主・禰宜引率による正式参拝、政財界の有力者が代表を務める参詣団、灯台と携帯電話アンテナの保守点検や文化財・自然保全状況の確認作業員など、必要な場合の工事関係者等が事前に許可を得て上陸が認められる。(中略)
以上の場合いずれも女人禁制と禊は守られている。
と、おいそれと上陸できない正真正銘の聖地ですから、このジオラマを眺めて想像を膨らますしかありませんが、土地鑑があったり、実際に行ったことのある地域・場所のジオラマを観ると、別の意味で萌え上がり ます。
ます。
例えば、多賀城の復元ジオラマとか、
中世の海路を示した瀬戸内海のジオラマとか、
あぁ、行ったなぁ、ここ…
なんて思ったりして。
そして、2014年の「Misia Candle Night」さぬき公演(記事)の会場となった大串自然公園の
場所をジオラマ上で探してみました。

地図で見るのと、ジオラマで見るのはかなり様相が違っていて、どうして道がこの地点を通っているのかがよくわかります。
こちらは平安京で、
どちらも三方を山に囲まれていますけれど、都市としての広さは比べようもありませんな。
鎌倉が、150年間という短い間ながら、日本の政治の中心だったというのが、ちょっと信じがたい感じです。
どう考えても、発展性のない場所ですものね…
そうそう、「ジオラマ」というよりも、城の縄張りを示した展示で、こちらがありました。
沖縄の中城城です。
ここにも2014年の「Misia Candle Night at Okinawa」(訪問記)で行きました…
風邪っぴきで大変だったなぁ…

ここまで、「マクロ」的なジオラマを書いてきましたが、「ミクロ」的なジオラマも楽しかった
歴博が所蔵する「洛中洛外図屏風(歴博甲本)」を元にしたという、1525~1535年頃の京の様子が再現されています。
また、江戸のジオラマといえば、江戸東京博物館のものが見事 ですが、歴博のジオラマも眼
ですが、歴博のジオラマも眼 を見張るものでした。
を見張るものでした。
 江戸橋広小路の様子(東から西を眺める)で、右手前に江戸橋があって、川(日本橋川)をさかのぼると日本橋がチラ見えしています。
江戸橋広小路の様子(東から西を眺める)で、右手前に江戸橋があって、川(日本橋川)をさかのぼると日本橋がチラ見えしています。
角度を変えて南西から北東を眺めると、
今はなき紅葉川沿いに、舟が何艘も係留されています。
この付近の現在の地図を見ると、
日本橋川と紅葉川が合流する地点には、首都高速の江戸橋JCTが作られて、かつての川の流れは、クルマの流れに変わってしまっています。

お次は、
なんのへんてつもないけれど、どことなく懐かしさを覚える風景です。
説明板によると、滋賀県長浜市高月町西物部という集落の「昭和50年代後半の初夏のある日を再現したもの」だそうで、私が幼いころ遊びに行った祖母の実家辺りもこんな感じだったような気がします
こんどは、なくなってしまった村。
「田子倉ダムとかつての集落」と題されたこのジオラマ、
福島県の只見川上流の田子倉ダムは、1959年(昭和34)年に一部運転が開始され、集落は水底に沈んだ。急峻な山々に囲まれた田子倉では、11月には雪が降りはじめ、山々の雪は5月まで残る。その豊富な雪解け水と、岩盤を主として砂がダムに積もることが少ないという地質がダムの建設に適していた。
そうです。このジオラマを見ると、ダムが貯える水の量の巨大さ に圧倒
に圧倒 されます。
されます。
去年、どこかのダムで、降雨量が少なくて貯水量が減って 、水底に沈んだ集落が姿を見せたというニュースを見ましたが、ダム建設のため故郷を捨てるのも辛いでしょうけれど、再び姿を現した故郷を見るのもまた切ないのだろうな…
、水底に沈んだ集落が姿を見せたというニュースを見ましたが、ダム建設のため故郷を捨てるのも辛いでしょうけれど、再び姿を現した故郷を見るのもまた切ないのだろうな…
というところで、歴博探訪記の「ジオラマ編」はおしまいです。





























