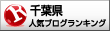今日は東北(方角であって、地方ではありません)を目指します。行くところは昨日のうちに決めていました。根木内(ねぎうち)城址です。
暦の上では立夏ですが、天気は下り坂で、庵に籠もっていると少し肌寒く感じる陽気でした。
北小金の駅入口を通り過ぎて、国道6号線とぶつかったところが根木内城址です。
ゆっくりとした下り坂が左にカーブを描きながら、上りに変わります。こんもりとした丘が見えたので、そこであろうと見当はつきましたが、「根木内歴史公園」と称しているのに、付近には案内らしきものは何もありません。
※後日、たまたま開園当時 ― 三年前、2006年の四月 ― に訪問した人のブログを見つけたましたが、案内板がないのは最初からのようです。
入口も私道を思わせるような急坂で、ここにも案内板はありません。不動産会社の脇なので、工事用車両の出入り口かと思ってしまいます。
プリントして持ってきた地図に記された道は一筋あるだけです。少し先まで歩いてみましたが、ほかに道はありません。坂の入口に戻って、おっかなびっくり坂を上ると、土塁らしきものの向こうに草地が開けているのが見えたので、やっとそれとわかるという感じです。
この城は寛正三年(1462年)に高城胤忠が築いたとも、永正三年(1506年)、胤忠の曾孫・高城胤吉によって築かれたともいわれていて、確定していないそうです。高城胤吉といえば、前に訪ねた小金城(大谷口城)を築いた人です。
城址といっても、時代は信長が登場する直前ですから、後世のような城ではなく館です。水を湛えた濠はなく、すべて空堀です。
ただ、この城の特徴は東北部に自然の湿地帯があって、水濠の役割を果たし、敵の侵入を困難にさせただろうということです。湿地帯は現在もそのまま遺されています。
じつに久しぶりに木賊(トクサ)を見たので、思わずシャッターを切りました。
私の先考が庭に植えていました。私が幼いころ、子供心にも変わった樹(草)だと感じて、訊ねたことがあったのでしょう。鑢(やすり)がなかった昔、ものを磨くのに使われた植物だと教わりました。
私の実家の木賊が植えられていたところは、雨の日には池から溢れ出る水の通り道になっていました。
雨が降ると、私はいつも庭に出て行って、そこに泥を積み上げて、堰をつくるのが楽しみでした。晴れた日は油断がなりませんが、雨だと先考が部屋から出てこないので、堰を崩して洪水だと騒いでみたりしながら、思う存分遊ぶことができたのです。
もう五十年以上も前の話です。ふと思い出したので、シャッターを切ってしまいました。
根木内城址を歩いているころから、幽雨になりました。傘は持ってきていませんでしたが、まだ一時間も歩いていません。雲を見ると、それほど厚くもないので、本降りになるとしても、間がありそうに見えました。
地図を見ると、少し距離がありそうですが、了源寺というお寺があるので、行ってみることにしました。
開基は寛文年間(1661年-72年)という日蓮宗のお寺です。たびたび火災に遭って、史料が遺されていないので、お寺の歴史ははっきりしないのだそうです。
路地の奥にあって、うっかりすると見過ごしてしまいそうです。私も偶然通用口を見つけ、お寺のようだと感じて入らせてもらって見つけました。
こじんまりとしたいいお寺でした。
周辺は住宅地と畑です。連休中だからか、雨戸やカーテンを閉めて留守にしているらしい家がたくさんありました。
了源寺に向かう間道に折れてから、再び元の道に戻るまで、行き交う人は一人もおりませんでした。原野や沙漠だとこんな悠長なことはいっていられませんが、人がいても不思議でないところで、まったき無人というのはじつにいいものです。時折ポツポツと落ちてくる雨もいい。
了源寺をあとにしたところで、ポケットに忍ばせていた万歩計は六千歩に迫り、臑(すね)のあたりが痛くなってきました。
新松戸周辺は結構台地が多く、道は上ったり下ったりします。
このところ、歩き始めてしばらくするころ、上り坂に差しかかっていると、胸焼けなのか心臓の痛みなのか、はっきりしない胸苦しさに襲われるようになりました。
今日も北小金に向かう途中、緩いけれども長い上り坂がつづくので、息切れしそうになりました。
しばらく歩きつづけていると、やがて治まるのですが、そのころには足裏が痛くなってきます。今日のように、足裏の痛みより先に、臑が痛くなることもあります。履いている靴にもよるみたいです。
今日はデザートブーツを履いていました。軽くて佳いのですが、ソールが飴ゴムなので、地面にピッタリと着き過ぎるのが欠点といえば欠点です。長い距離を歩くと疲れやすいのです。
今日は昨日よりちょっと長く歩いて、所要二時間弱。途中、喫煙二本。
明日は北の方角に当たる廣徳寺と松戸近辺では一番著名な本土寺を訪ねようと思っていますが、どうやら雨のようです。