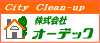出費敬遠 設置進まず
今週月曜日の新聞に、住宅用火災警報器についての記事が出ていました。
7月20日のブログでも
既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化についてお知らせしましたが、
新聞記事によると、1個5千円前後の自己負担を伴うほか、
罰則がないことなどから設置が進んでいない、との内容でした。
新築住宅では、2006年6月から設置が義務付けられています。
既存住宅では、県内18市町村で設置義務が適用され、
残り26市町村でも2011年6月までに順次義務化されます。
既存住宅では市町村により義務化開始日が違います。
ひたちなか市 平成20年6月1日より既に義務化
那珂市 〃
水戸市 平成23年6月1日より適用
城里町 〃
茨城町 〃
住宅用火災警報器は原則として、
寝室と寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、
必ず設置しなければなりません。
住宅火災による死亡原因でもっとも多いのが‘逃げ遅れ’です。
火災を時間帯別にみると、22時から翌朝6時の就寝中です。
やはり、これらを考えると火災警報器の役割は大きいと思われます。
中古住宅をご検討中の方は、是非お忘れなく、
「住宅用火災警報器」を取り付けましょう!
住宅用火災警報器等に関するQ&A(どこに設置?など)
ひたちなか市・水戸市不動産売買物件情報
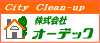
今週月曜日の新聞に、住宅用火災警報器についての記事が出ていました。
7月20日のブログでも
既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化についてお知らせしましたが、
新聞記事によると、1個5千円前後の自己負担を伴うほか、
罰則がないことなどから設置が進んでいない、との内容でした。
新築住宅では、2006年6月から設置が義務付けられています。
既存住宅では、県内18市町村で設置義務が適用され、
残り26市町村でも2011年6月までに順次義務化されます。
既存住宅では市町村により義務化開始日が違います。
ひたちなか市 平成20年6月1日より既に義務化
那珂市 〃
水戸市 平成23年6月1日より適用
城里町 〃
茨城町 〃
住宅用火災警報器は原則として、
寝室と寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、
必ず設置しなければなりません。
住宅火災による死亡原因でもっとも多いのが‘逃げ遅れ’です。
火災を時間帯別にみると、22時から翌朝6時の就寝中です。
やはり、これらを考えると火災警報器の役割は大きいと思われます。
中古住宅をご検討中の方は、是非お忘れなく、
「住宅用火災警報器」を取り付けましょう!
住宅用火災警報器等に関するQ&A(どこに設置?など)
ひたちなか市・水戸市不動産売買物件情報