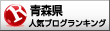鉢に植えたミニニンジンです。
こちらもそろそろ収穫が近づいてきました。
ニンジンはきれいなオレンジ色をしていますが
その色素はポリフェノールのひとつであるカロテノイドです。
最近はアントシアニンを含んだ二十日大根のように赤いものも誕生しています。
このところ、ニンジンやビーツのような色を持つ植物の色素を
お菓子や飲料、さらに漬物の着色料として利用するようになってきました。
まさしく天然由来の着色料です。
フローラ時代からの悪い?癖で、ポリフェノールと聞くと
ついついLEDを照射したくなる環境班。
もしかしたらLEDを上手に利用すると
ポリフェノール量が増え、機能性の高いニンジンになったり
天然色素を多く抽出できるかもしれないと実験を始めました。
しかし今まで成功してきたのは食用菊や山菜、葉菜など
利用部分が全て地上にあるものばかり。
ところがニンジンの根は完全に地下の中にあります。
果たして葉に照射したら直接光の当たっていない根の
ポリフェノール量に影響を与えられるのでしょうか。
答えは「やってみなければわからない」。
遊びのような実験ですが、
そろそろ土の中から答えが出てきそうです。
こちらもそろそろ収穫が近づいてきました。
ニンジンはきれいなオレンジ色をしていますが
その色素はポリフェノールのひとつであるカロテノイドです。
最近はアントシアニンを含んだ二十日大根のように赤いものも誕生しています。
このところ、ニンジンやビーツのような色を持つ植物の色素を
お菓子や飲料、さらに漬物の着色料として利用するようになってきました。
まさしく天然由来の着色料です。
フローラ時代からの悪い?癖で、ポリフェノールと聞くと
ついついLEDを照射したくなる環境班。
もしかしたらLEDを上手に利用すると
ポリフェノール量が増え、機能性の高いニンジンになったり
天然色素を多く抽出できるかもしれないと実験を始めました。
しかし今まで成功してきたのは食用菊や山菜、葉菜など
利用部分が全て地上にあるものばかり。
ところがニンジンの根は完全に地下の中にあります。
果たして葉に照射したら直接光の当たっていない根の
ポリフェノール量に影響を与えられるのでしょうか。
答えは「やってみなければわからない」。
遊びのような実験ですが、
そろそろ土の中から答えが出てきそうです。