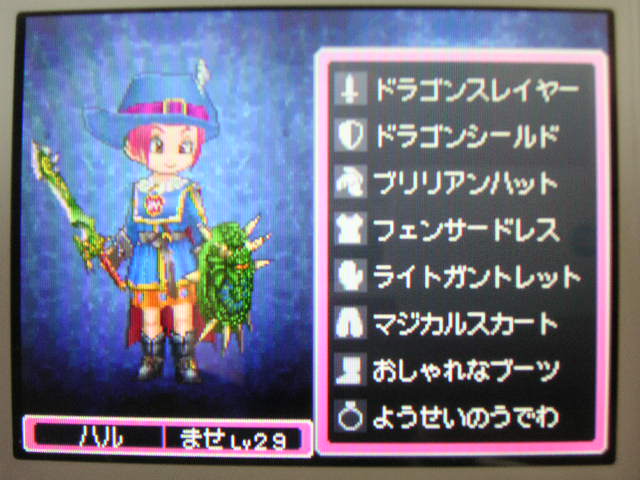今日の記事は虫が嫌いな人は読まないほうがいいかもしれません。
ミツバチの呪い
数ヶ月前、ミツバチが激減して養蜂業が困っているというニュースがあった。ちょうどその頃、川辺をサイクリングしていてミツバチに刺されるという事件(?)に遭った。気分よく走っていたところ、頭に木の葉か何かが乗っかった感覚に襲われた。ふつうに手で髪を払う仕草をしたら、左手の薬指に激痛が走る。どうやらハチがとまっていたようだ。
指をみると、針が刺さっている。あああ。。素早く抜いて、口で傷口を吸う。ちょうどいいところに公園があって、水道で洗い流す。散歩する犬に見つめられる。こっちみんな。筋肉がひきつるような痛みなのだが、とりあえず、この処置でおさまってきた。後で調べると、カギ状の針が身体に残るのはミツバチ、応急処置は水で流すということで、適切だったようだ。
これで終わりという感じだったのだが、1週間程経って朝起きると、何だか同じ指がかゆい。夕方になって改めて見ると、左手薬指全体が蕁麻疹のような発疹で覆われていた。こわー。ちょっと焦って皮膚科に行く。結局原因はよく分からなかったが塗り薬をもらう。これを1週間くらいつけていたら、それも無事治った。
そして最近感じるのだが、虫に刺された部分が大きい。つい先日寝てる間に足のくるぶしのところを虫に刺されてしまったのだが、いま直径3センチの円くらい赤くなってる。温泉行ったら治るかなと思ったのだが、かわらない。勝手な推測なのだが、ミツバチに刺されて他の虫に刺されたときも過剰反応するようになってしまったのではないか。自分はあまりアレルギーとかないのだけど、もしそうだったら嫌だな。
蜘蛛取山(くもとりやま)
ずーっと前の記事でも書いたように、自分の家はクモが出る。小型のクモで、名前はたぶんアダンソンハエトリグモ。黒白のやつと茶色のやつがいてオスとメスらしい。クモは別に人間に害をもたらすわけではないので、処置に困る。クモがずっと生きているということはエサとなる他の虫が実は潜んでいるということで、それを退治してくれているならむしろありがたい。ということで、一時期見つけても殺さずに放っておいた。ところが暫くすると、大掃除でクモの卵の集団を見つけてしまったり、子供のクモがひょこっと出てくるのを見つけてしまったり、ということがあって、さすがにこれはマズイな…ということになった。
そこでふと思いついたのが、殺さずに住み分けを進めていく人道的撃退法。用意するのは、紙コップ(プラスチックコップのほうが中がわかってよい)と厚紙(使い終わったメモ用紙の台紙を使っている)。使い方は簡単、クモを見つけたら上からコップをかぶせる。コップにはそれなりの面積があるので逃げられることは滅多にない。かぶせたらコップを少し接地面と平行に動かしてみると、クモはコップの中に入っていく。そうしたらコップを離して厚紙をかぶせる。これで隔離成功。そしたらベランダか家の外に出て外の世界へ放つ。完璧だね!
今では机の脇にコップが置いてあり、クモ獲り名人の名をほしいままににしている(笑)。他には応用できないかというと、飛ぶ虫はよく壁や天井にとまる小さい虫ならいいが、そうでないものはなかなか難しい。蚊なんぞが入ってきた日には仇敵として叩き潰さなければならない。
【8月5日追記】虫刺されの原因がわかりました。体質のせいではないようです。

にほんブログ村
ミツバチの呪い
数ヶ月前、ミツバチが激減して養蜂業が困っているというニュースがあった。ちょうどその頃、川辺をサイクリングしていてミツバチに刺されるという事件(?)に遭った。気分よく走っていたところ、頭に木の葉か何かが乗っかった感覚に襲われた。ふつうに手で髪を払う仕草をしたら、左手の薬指に激痛が走る。どうやらハチがとまっていたようだ。
指をみると、針が刺さっている。あああ。。素早く抜いて、口で傷口を吸う。ちょうどいいところに公園があって、水道で洗い流す。散歩する犬に見つめられる。こっちみんな。筋肉がひきつるような痛みなのだが、とりあえず、この処置でおさまってきた。後で調べると、カギ状の針が身体に残るのはミツバチ、応急処置は水で流すということで、適切だったようだ。
これで終わりという感じだったのだが、1週間程経って朝起きると、何だか同じ指がかゆい。夕方になって改めて見ると、左手薬指全体が蕁麻疹のような発疹で覆われていた。こわー。ちょっと焦って皮膚科に行く。結局原因はよく分からなかったが塗り薬をもらう。これを1週間くらいつけていたら、それも無事治った。
そして最近感じるのだが、虫に刺された部分が大きい。つい先日寝てる間に足のくるぶしのところを虫に刺されてしまったのだが、いま直径3センチの円くらい赤くなってる。温泉行ったら治るかなと思ったのだが、かわらない。勝手な推測なのだが、ミツバチに刺されて他の虫に刺されたときも過剰反応するようになってしまったのではないか。自分はあまりアレルギーとかないのだけど、もしそうだったら嫌だな。
蜘蛛取山(くもとりやま)
ずーっと前の記事でも書いたように、自分の家はクモが出る。小型のクモで、名前はたぶんアダンソンハエトリグモ。黒白のやつと茶色のやつがいてオスとメスらしい。クモは別に人間に害をもたらすわけではないので、処置に困る。クモがずっと生きているということはエサとなる他の虫が実は潜んでいるということで、それを退治してくれているならむしろありがたい。ということで、一時期見つけても殺さずに放っておいた。ところが暫くすると、大掃除でクモの卵の集団を見つけてしまったり、子供のクモがひょこっと出てくるのを見つけてしまったり、ということがあって、さすがにこれはマズイな…ということになった。
そこでふと思いついたのが、殺さずに住み分けを進めていく人道的撃退法。用意するのは、紙コップ(プラスチックコップのほうが中がわかってよい)と厚紙(使い終わったメモ用紙の台紙を使っている)。使い方は簡単、クモを見つけたら上からコップをかぶせる。コップにはそれなりの面積があるので逃げられることは滅多にない。かぶせたらコップを少し接地面と平行に動かしてみると、クモはコップの中に入っていく。そうしたらコップを離して厚紙をかぶせる。これで隔離成功。そしたらベランダか家の外に出て外の世界へ放つ。完璧だね!
今では机の脇にコップが置いてあり、クモ獲り名人の名をほしいままににしている(笑)。他には応用できないかというと、飛ぶ虫はよく壁や天井にとまる小さい虫ならいいが、そうでないものはなかなか難しい。蚊なんぞが入ってきた日には仇敵として叩き潰さなければならない。
【8月5日追記】虫刺されの原因がわかりました。体質のせいではないようです。
にほんブログ村