茶坊主さん…コメントありがとう!
コメントのお返事が長くなりそうなので、コチラに書きます。
茶坊主さんへ…スポーツ指導者の方へ…スポーツを愛している人へ…
最近、陸上・野球・サッカー・バレーボールなど様々なスポーツで、スペシフィックトレーニング(専門的トレーニング=競技パフォーマンス向上を直接図る事を目的としたトレーニング)の方法を紹介した書物が増えてきて、大変興味深く勉強させていただいています。
スポーツを行ううえで、技術練習と一般的トレーニング(基礎体力づくり)と専門的トレーニングの関係は切っても切り離せない間柄です。
しかし、私自身が経験したスポーツ(バレーボール)では その3つの割合は 技術練習が99%と言ってよいほど…。
先日も6年間、汗を流した母校に立って、トレーナーとなった今、当時を思い返せば、寒い冬に少しのウエイトトレーニングや走り込みをした事、雨で練習コートが使えないとき、マット運動ぐらいしかやっていなかったな~などと振り返っていました。
今なら…故障箇所を持っている選手には こんな一般的トレーニングをさせてあげたい。
レシーブが苦手な子には、こんな専門的トレーニングをすれば、早道で上手くなれる…。
スパイクのこの部分が上手くできない子には こんな専門的トレーニングをさせたら、もっと強力なスパイクを打つことができる!
などなど…思いを馳せていました。
バレーボールを実際に体験していたこと、機能解剖学などの理論や一般的トレーニングを体験したことで、連続した動作や細かい感覚的な部分をよく分析できるようになりました。
あれから20年ほど経過し、スポーツ医科学は発展し、様々なエクササイズの情報も豊富であるはずなのに…
スポーツの現場を見てみると、さほど20年前と変わっていないんですね~!?
フィットネスクラブの中では 一般の人々が様々な新しいエクササイズを行っているというのに!!
しかしトップアスリートを見ると、必ずといってよいほど、スポーツ医科学を取り入れ、トレーニングを積極的に取り入れています。
トレーニングを取り入れた選手自身が トレーナーと同等の体の知識やエクササイズ理論を吸収し、それをコンディショニングだけでなく、競技力の向上にも役立てているようです。
(一般の方でも熱心にトレーニングをされた方は “あるある事件”のように振り回されることはなく、健康管理をされていることでしょう。)
コーチや監督さんが現役時代に自分が経験しなかったトレーニングを 自ら勉強されたり、トレーナーを信頼し任せて、積極的にトレーニングを行っているチームは 怪我も少なく、成績にも繋がっています。
(茶坊主さんのように、スポーツ指導者・選手自身が治療家やトレーナーを目指す人も多いですね)
選手・スポーツ専門指導者・トレーナーとの共通理解や協同作業が必要となるわけです。
(全てを経験すれば、鬼に金棒!?)
それでもって、その三者の共通理解のレベルが高いほど、目指し到達するところのレベルも高くなるでしょう。
アメリカでは トレーナーの認知度も高く(日本では “トレーナー”って着るトレーナーしか思いつかない人も多いです!?)、スポーツ医科学を学ぶトレーナー志望の大学生・大学院生が高校スポーツチームに配属され、インターンでトレーナー活動を行っているそうです。
プロ・社会人チームはもちろんですが、高校のクラブ活動にさえも、トレーナーが存在するのだそうです。
ところが 日本の場合…ウォーミングアップもク-ルダウンも まともにしない、、もちろんトレーニングも…
体を…機能解剖学を知っていれば、もっと的確に動くことができるのに…
体を痛めなくてすむのに…
なんて遠回りな事をしてるんだろう??
と、スポーツの指導風景を見ながら感じます。
スポーツ指導者の方々…是非、トレーニング理論をご理解いただき、練習の一環として取り入れてみてください。
きっと、あなたの選手や生徒さんにとっても、あなたの健康のためにも、すごく役に立つと思います。
また、トレーナーと選手の架け橋となってください。
トレーナーに期待していただき、発破をかけていただくことで、トレーナーのレベルも向上します。
そこで!! 毎月勉強会を行っています。スポーツ指導者、トレーナー、治療家、セラピスト、学生さん…スポーツや健康管理に携わる方たちが集まり、情報・意見交換、トレーニングに関する勉強を行っています。
どなたでも、お~気軽にぃ☆
*2月の勉強会*
2月18日日曜日14:00~16:30
魚崎西町会館(阪神魚崎駅より徒歩5分)
コメントのお返事が長くなりそうなので、コチラに書きます。
茶坊主さんへ…スポーツ指導者の方へ…スポーツを愛している人へ…
最近、陸上・野球・サッカー・バレーボールなど様々なスポーツで、スペシフィックトレーニング(専門的トレーニング=競技パフォーマンス向上を直接図る事を目的としたトレーニング)の方法を紹介した書物が増えてきて、大変興味深く勉強させていただいています。
スポーツを行ううえで、技術練習と一般的トレーニング(基礎体力づくり)と専門的トレーニングの関係は切っても切り離せない間柄です。
しかし、私自身が経験したスポーツ(バレーボール)では その3つの割合は 技術練習が99%と言ってよいほど…。
先日も6年間、汗を流した母校に立って、トレーナーとなった今、当時を思い返せば、寒い冬に少しのウエイトトレーニングや走り込みをした事、雨で練習コートが使えないとき、マット運動ぐらいしかやっていなかったな~などと振り返っていました。
今なら…故障箇所を持っている選手には こんな一般的トレーニングをさせてあげたい。
レシーブが苦手な子には、こんな専門的トレーニングをすれば、早道で上手くなれる…。
スパイクのこの部分が上手くできない子には こんな専門的トレーニングをさせたら、もっと強力なスパイクを打つことができる!
などなど…思いを馳せていました。
バレーボールを実際に体験していたこと、機能解剖学などの理論や一般的トレーニングを体験したことで、連続した動作や細かい感覚的な部分をよく分析できるようになりました。
あれから20年ほど経過し、スポーツ医科学は発展し、様々なエクササイズの情報も豊富であるはずなのに…
スポーツの現場を見てみると、さほど20年前と変わっていないんですね~!?
フィットネスクラブの中では 一般の人々が様々な新しいエクササイズを行っているというのに!!
しかしトップアスリートを見ると、必ずといってよいほど、スポーツ医科学を取り入れ、トレーニングを積極的に取り入れています。
トレーニングを取り入れた選手自身が トレーナーと同等の体の知識やエクササイズ理論を吸収し、それをコンディショニングだけでなく、競技力の向上にも役立てているようです。
(一般の方でも熱心にトレーニングをされた方は “あるある事件”のように振り回されることはなく、健康管理をされていることでしょう。)
コーチや監督さんが現役時代に自分が経験しなかったトレーニングを 自ら勉強されたり、トレーナーを信頼し任せて、積極的にトレーニングを行っているチームは 怪我も少なく、成績にも繋がっています。
(茶坊主さんのように、スポーツ指導者・選手自身が治療家やトレーナーを目指す人も多いですね)
選手・スポーツ専門指導者・トレーナーとの共通理解や協同作業が必要となるわけです。
(全てを経験すれば、鬼に金棒!?)
それでもって、その三者の共通理解のレベルが高いほど、目指し到達するところのレベルも高くなるでしょう。
アメリカでは トレーナーの認知度も高く(日本では “トレーナー”って着るトレーナーしか思いつかない人も多いです!?)、スポーツ医科学を学ぶトレーナー志望の大学生・大学院生が高校スポーツチームに配属され、インターンでトレーナー活動を行っているそうです。
プロ・社会人チームはもちろんですが、高校のクラブ活動にさえも、トレーナーが存在するのだそうです。
ところが 日本の場合…ウォーミングアップもク-ルダウンも まともにしない、、もちろんトレーニングも…
体を…機能解剖学を知っていれば、もっと的確に動くことができるのに…
体を痛めなくてすむのに…
なんて遠回りな事をしてるんだろう??
と、スポーツの指導風景を見ながら感じます。
スポーツ指導者の方々…是非、トレーニング理論をご理解いただき、練習の一環として取り入れてみてください。
きっと、あなたの選手や生徒さんにとっても、あなたの健康のためにも、すごく役に立つと思います。
また、トレーナーと選手の架け橋となってください。
トレーナーに期待していただき、発破をかけていただくことで、トレーナーのレベルも向上します。
そこで!! 毎月勉強会を行っています。スポーツ指導者、トレーナー、治療家、セラピスト、学生さん…スポーツや健康管理に携わる方たちが集まり、情報・意見交換、トレーニングに関する勉強を行っています。
どなたでも、お~気軽にぃ☆
*2月の勉強会*
2月18日日曜日14:00~16:30
魚崎西町会館(阪神魚崎駅より徒歩5分)











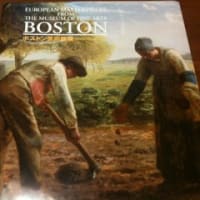







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます