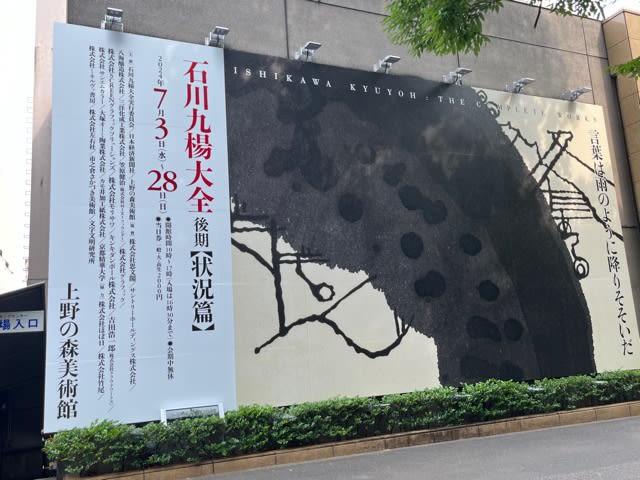東京都現代美術館にて、坂本龍一 音を視る 時を聴くを鑑賞。
土曜日の午前ということもあり、会場はとても混雑しており、客層も多国籍であり、年齢層も幅広かった。
坂本龍一といえば、YMO(Yellow Magic Orchestra)の楽曲や「戦場のメリークリスマス」、「ラストエンペラー」などの映画音楽が思い浮かぶ。
この展覧会では、時間と空間と音の連関を表現した作品が並ぶ。
時間に対する人間の感覚が一定ではなく、人間の主観によって100年が長く感じたり短く感じたりといった「主観時間」に芸術性を見出していたのではないか。
その時間に対して、音がどう関わってくるのか、音も一定ではなく、空間と絡み合いながら変化していく。
時間、空間、音の三要素を再現する手段として、映像を捉えていたのだろう。
結局、巡り巡って、人間の日常生活を自由に過ごすことに返ってきているのかなとも感じた。

霧の彫刻

土曜日の午前ということもあり、会場はとても混雑しており、客層も多国籍であり、年齢層も幅広かった。
坂本龍一といえば、YMO(Yellow Magic Orchestra)の楽曲や「戦場のメリークリスマス」、「ラストエンペラー」などの映画音楽が思い浮かぶ。
この展覧会では、時間と空間と音の連関を表現した作品が並ぶ。
時間に対する人間の感覚が一定ではなく、人間の主観によって100年が長く感じたり短く感じたりといった「主観時間」に芸術性を見出していたのではないか。
その時間に対して、音がどう関わってくるのか、音も一定ではなく、空間と絡み合いながら変化していく。
時間、空間、音の三要素を再現する手段として、映像を捉えていたのだろう。
結局、巡り巡って、人間の日常生活を自由に過ごすことに返ってきているのかなとも感じた。

霧の彫刻