家の近所でよく、蒲の穂を見かけます。道端に白い綿のような塊が落ちていることもありますが、小さなタンポポの綿毛のように飛んでいくものもあります。
今日は風に乗って飛んでいく綿毛がありましたのでしばらく狙ってみましたが、タイミングとピントを合わせるのが難しく、無理でした。

【ツルウメモドキ】
ところで、蒲の穂の”蒲”という字が色々な言葉(名前)に使われていることに気づき、調べてみました。但し、調べたと言ってもネットでの検索ですので、”そうなんだ”という程度に読んでください。

「蒲団」乾燥させた蒲の葉を編んで敷物にしたことから蒲団になったとか、この蒲の穂(綿毛)を集めて布団の中綿にしたから蒲団になった。

「蒲鉾」カマボコを作り始めた頃は、今の竹輪の形をしたものであり、その形が蒲の穂に似ていることから蒲鉾となった。

「蒲焼き」ウナギの蒲焼きですが、以前は開かずにまるごと竹串に差して焼いていた(?)ため、やはりその形が蒲の穂ににていたことから蒲焼きになった。
などなど、私は”ふ~ん”と納得してしまいました。



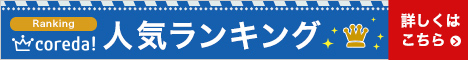

今日は風に乗って飛んでいく綿毛がありましたのでしばらく狙ってみましたが、タイミングとピントを合わせるのが難しく、無理でした。

【ツルウメモドキ】
ところで、蒲の穂の”蒲”という字が色々な言葉(名前)に使われていることに気づき、調べてみました。但し、調べたと言ってもネットでの検索ですので、”そうなんだ”という程度に読んでください。

「蒲団」乾燥させた蒲の葉を編んで敷物にしたことから蒲団になったとか、この蒲の穂(綿毛)を集めて布団の中綿にしたから蒲団になった。

「蒲鉾」カマボコを作り始めた頃は、今の竹輪の形をしたものであり、その形が蒲の穂に似ていることから蒲鉾となった。

「蒲焼き」ウナギの蒲焼きですが、以前は開かずにまるごと竹串に差して焼いていた(?)ため、やはりその形が蒲の穂ににていたことから蒲焼きになった。
などなど、私は”ふ~ん”と納得してしまいました。


今朝も良い天気となりましたので、未明に清滝寺に登りました。
今日の日の出時刻は高知市で7時9分とのこと、家を出たのが6時40分でしたが、未だ薄暗い道を急ぎました。



普段だったら途中でも写真を撮ったりするのでもっと時間が掛かりますが、今日はとにかく日の出までに境内にまで行き着きたいので急ぎました。何とか7時を少し過ぎたころ、およそ25分弱で登り切りましたが、さすがに一気に登ると息が切れます。カメラを覗いても、ファインダーが息で曇ってしまいます。
息を整えながら日の出を待つこと数分、今日もまた雲の間から朝日が顔を出しました。



この頃になると清滝寺も人の動きがあり、朝の散歩や参拝に訪れる人も増えてきました。私は持参したお茶を飲みながらしばらく朝日を楽しんだあとに山を下りました。上空の雲の動きは早く、飛行機雲もあっという間に移動していき、様々に形を変えていく模様も面白いものでした。



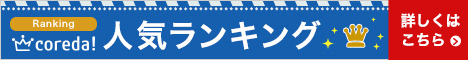

今日の日の出時刻は高知市で7時9分とのこと、家を出たのが6時40分でしたが、未だ薄暗い道を急ぎました。



普段だったら途中でも写真を撮ったりするのでもっと時間が掛かりますが、今日はとにかく日の出までに境内にまで行き着きたいので急ぎました。何とか7時を少し過ぎたころ、およそ25分弱で登り切りましたが、さすがに一気に登ると息が切れます。カメラを覗いても、ファインダーが息で曇ってしまいます。
息を整えながら日の出を待つこと数分、今日もまた雲の間から朝日が顔を出しました。



この頃になると清滝寺も人の動きがあり、朝の散歩や参拝に訪れる人も増えてきました。私は持参したお茶を飲みながらしばらく朝日を楽しんだあとに山を下りました。上空の雲の動きは早く、飛行機雲もあっという間に移動していき、様々に形を変えていく模様も面白いものでした。


クリスマスの今日、所属している団体の理事会と忘年会があっておいしいお酒を飲んできました。今日はまた、夕方に別の定例会もあり、午後早くに歩いて家を出ました。自宅から土佐市の中心付近まで徒歩でおよそ30分の距離ですが、風が強く、手袋に帽子も被って行きました。

その会が終わったあとは、高知市内での忘年会に出席するためバスに乗らなければなりません。土佐市から高知市内に向かうバスルートはいくつかありますが、たまたまやって来たのが横浜経由便。高知市内で下車する場合はどのルートでも同じなのでそれに乗りました。

乗り込んでみると、新しい低床バスでした。床は低く、運転席とタイヤのあるところだけ50cmくらい高くなっています。
そして、バス停に止まると車体が5cmくらい(多分)下がって、ステップが更に低くなります。お客さんが乗り終わるとドアを締めますが、それに伴って今度は、車体が5cm上昇します。話には聞いていましたが、なかなか面白いと思いました。

さて、高知市内に入ってから、会場が高知駅近くにあるため路面電車に乗り換えました。こちらはかつて、車掌さんが乗車していた名残りがあるような旧型車両。今にもチンチンというベルの音が聞こえてくるようでした。
忘年会が終われば二次会はパス。今度はJRで高知駅から伊野駅まで乗車、伊野駅には家人が迎えに来てくれました。

ところで、今日の列車は駅での停車時、自動ではドアが開かず、乗降する人が手動で開閉するようになっていました。寒冷地では当たり前ですが、南国高知でもエコを考えた、そして乗客の居住性を考慮した処置であり、いいことだと思いました。ただ、意外にドアが重いので、力のない人には辛いかも知れませんね。
ということで今日は、徒歩、郊外バス(高知県交通)、路面電車(土佐電鉄)、列車(JR)、そして自家用車と、いくつかの交通機関を乗り継ぐことができた一日でした。






その会が終わったあとは、高知市内での忘年会に出席するためバスに乗らなければなりません。土佐市から高知市内に向かうバスルートはいくつかありますが、たまたまやって来たのが横浜経由便。高知市内で下車する場合はどのルートでも同じなのでそれに乗りました。

乗り込んでみると、新しい低床バスでした。床は低く、運転席とタイヤのあるところだけ50cmくらい高くなっています。
そして、バス停に止まると車体が5cmくらい(多分)下がって、ステップが更に低くなります。お客さんが乗り終わるとドアを締めますが、それに伴って今度は、車体が5cm上昇します。話には聞いていましたが、なかなか面白いと思いました。

さて、高知市内に入ってから、会場が高知駅近くにあるため路面電車に乗り換えました。こちらはかつて、車掌さんが乗車していた名残りがあるような旧型車両。今にもチンチンというベルの音が聞こえてくるようでした。
忘年会が終われば二次会はパス。今度はJRで高知駅から伊野駅まで乗車、伊野駅には家人が迎えに来てくれました。

ところで、今日の列車は駅での停車時、自動ではドアが開かず、乗降する人が手動で開閉するようになっていました。寒冷地では当たり前ですが、南国高知でもエコを考えた、そして乗客の居住性を考慮した処置であり、いいことだと思いました。ただ、意外にドアが重いので、力のない人には辛いかも知れませんね。
ということで今日は、徒歩、郊外バス(高知県交通)、路面電車(土佐電鉄)、列車(JR)、そして自家用車と、いくつかの交通機関を乗り継ぐことができた一日でした。



昨夜、NHK・BS2で放送された「ブラザーズ・フォア2008東京コンサート」を見ました。

【クズの実】
残念ながら全編ではなく、途中からでしたが、久し振りに彼らの歌声を聞いて懐かしさで一杯になりました。その一方で、このコンサートは彼らのグループ結成50年記念とのこと、そんなに年月が過ぎてしまったのだということもある意味、ショックでした。

それでも「七つの水仙」「グリーンフィールズ」「500マイル」「漕げよマイケル」など、思わず一緒に口ずさんでしまいました。
彼らが活動した1960年代、いわゆるフォークソング全盛であり、フォークギターを抱えた若者ばかりでした。かくいう私も、ガットギターながら3人でグループを組み、PPMの曲を歌ったものでした。

【タナバラと蔦】
時の流れは元に戻るわけでもなく、フォークソングも懐かしさのなかに埋もれようとしています。ハーモニーの美しさと何かを訴える力は変わりありません。
しかし、彼らもそれなりの年を取りました。楽器の音は昔と変わりませんが、自分のことはさておき、声はやはり若者ではありませんでした・・・・





【クズの実】
残念ながら全編ではなく、途中からでしたが、久し振りに彼らの歌声を聞いて懐かしさで一杯になりました。その一方で、このコンサートは彼らのグループ結成50年記念とのこと、そんなに年月が過ぎてしまったのだということもある意味、ショックでした。

それでも「七つの水仙」「グリーンフィールズ」「500マイル」「漕げよマイケル」など、思わず一緒に口ずさんでしまいました。
彼らが活動した1960年代、いわゆるフォークソング全盛であり、フォークギターを抱えた若者ばかりでした。かくいう私も、ガットギターながら3人でグループを組み、PPMの曲を歌ったものでした。

【タナバラと蔦】
時の流れは元に戻るわけでもなく、フォークソングも懐かしさのなかに埋もれようとしています。ハーモニーの美しさと何かを訴える力は変わりありません。
しかし、彼らもそれなりの年を取りました。楽器の音は昔と変わりませんが、自分のことはさておき、声はやはり若者ではありませんでした・・・・


私はカメラ(デジタル)雑誌を定期購読していますが先日、2009年1月号が届きました。早速開封してみましたが、これまでにない厚さに驚きました。
今月号は通巻100号特別記念特大号とのことで、写真集との合冊になっており、厚さを測ってみると21mmもありました。
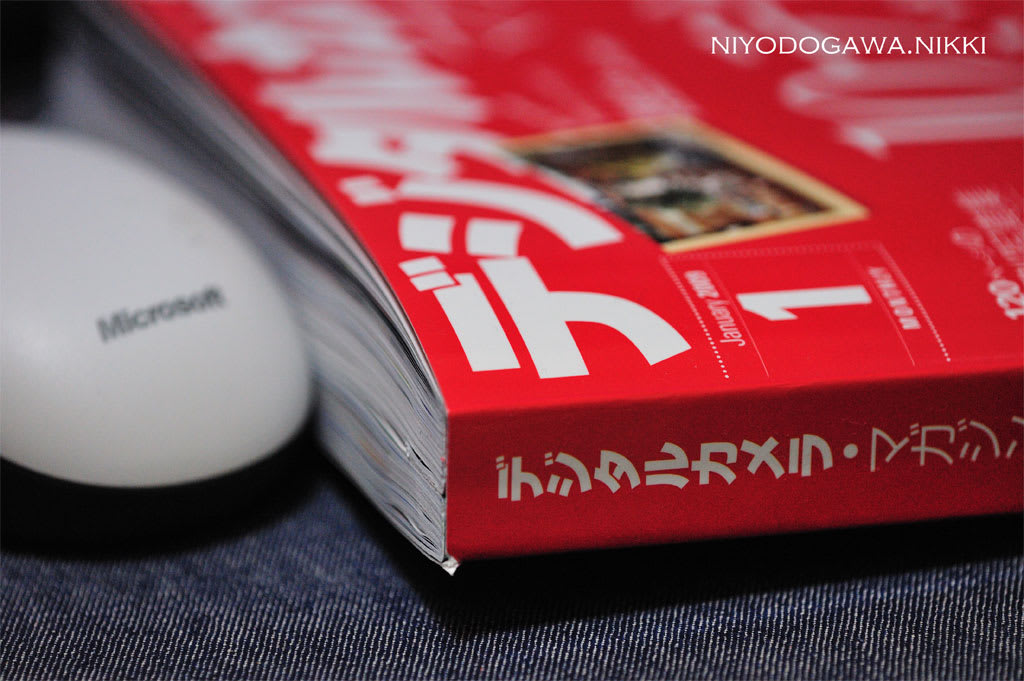
内容も、デジタル一眼レフ10年の歩みを特集したものであり、1999年に登場した一般向けデジタル一眼レフカメラ「ニコンD1」から今日までの進化の模様が詳しく紹介されています。
デジタルの世界は本当に日進月歩であり、カメラも同様です。とにかく、価格と性能、機能の進歩には驚くことばかりです。

私の趣味としての写真の歴史はだいぶん長くなりましたが、本格的にデジタルに移行したのは2004年です。一応、銀塩(フィルム)カメラも残してはあるのですがまず、使うことはありません。

それにしても、デジタルは”データ”管理が大変です。一瞬の誤った操作や機器のトラブルで全てが消失します。HDDとDVDの両方に保存するようにしていますが、最近はDVDに焼くのが億劫でHDDだけになっています。きっとまた、痛い目に遇う日がくると思います・・・・




今月号は通巻100号特別記念特大号とのことで、写真集との合冊になっており、厚さを測ってみると21mmもありました。
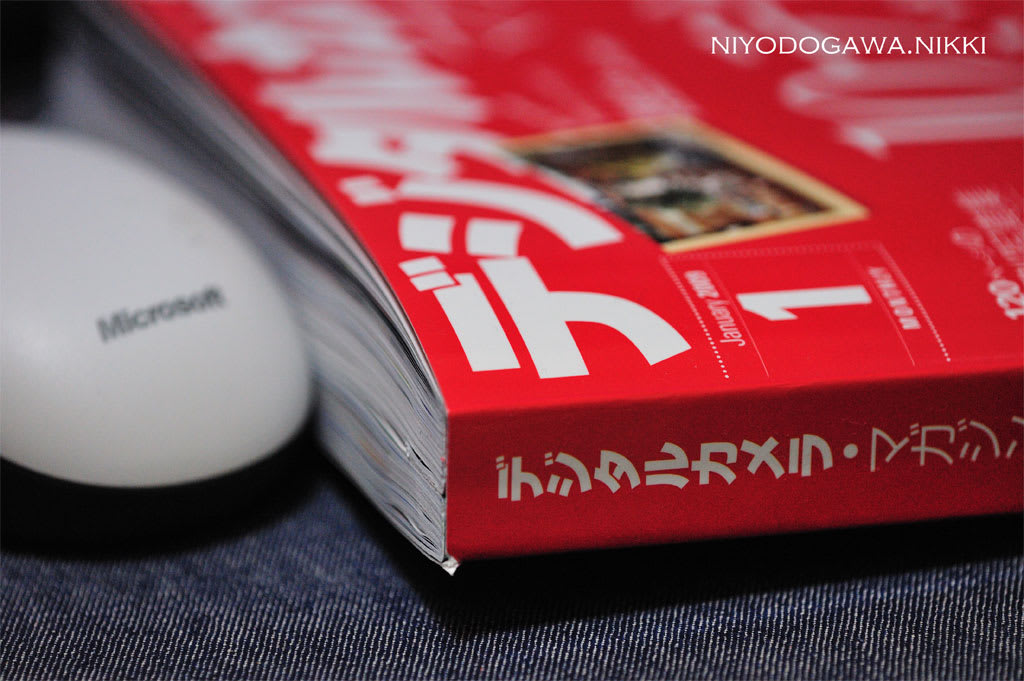
内容も、デジタル一眼レフ10年の歩みを特集したものであり、1999年に登場した一般向けデジタル一眼レフカメラ「ニコンD1」から今日までの進化の模様が詳しく紹介されています。
デジタルの世界は本当に日進月歩であり、カメラも同様です。とにかく、価格と性能、機能の進歩には驚くことばかりです。

私の趣味としての写真の歴史はだいぶん長くなりましたが、本格的にデジタルに移行したのは2004年です。一応、銀塩(フィルム)カメラも残してはあるのですがまず、使うことはありません。

それにしても、デジタルは”データ”管理が大変です。一瞬の誤った操作や機器のトラブルで全てが消失します。HDDとDVDの両方に保存するようにしていますが、最近はDVDに焼くのが億劫でHDDだけになっています。きっとまた、痛い目に遇う日がくると思います・・・・


この一週間、朝日が昇る頃に所用で出かけていましたが、カメラを持って行くことはありませんでした。

冷え込みはあまり強くなかったのですが、空気が澄んでおり、雲も無い東の空から真っ赤に燃えながら昇ってくる太陽を見るのが楽しみでした。

今日はやっと、カメラを持って清滝寺に登ってみましたが、残念ながら少し雲が流れており、まん丸な日の出を拝むことはできませんでした。それでも、徐々に色を変えながら東の空が明るんでいき、山を越えた雲の間から太陽が顔を見せてくれました。

こちらの日の出は今頃、午前7時10分頃ですが、早いお遍路さんはその時刻にはもう、車や徒歩で上がって来られます。

家を出る頃はしっかりと着込んできましたが、早足で昇ってくるとやはり汗をかくくらい暖かくなりました。
しばらく日の出を楽しんだ後、境内の自販機で温かい缶コーヒーを買って飲みましたが美味でした。

土佐もハウス園芸が盛んですが、この時期は南国でも加温が必要です。さっきまでは何も見えなかったハウスの煙突からも煙(湯気)が立ち登り、夜明けの寒さに備えているようです。



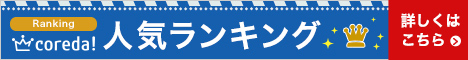


冷え込みはあまり強くなかったのですが、空気が澄んでおり、雲も無い東の空から真っ赤に燃えながら昇ってくる太陽を見るのが楽しみでした。

今日はやっと、カメラを持って清滝寺に登ってみましたが、残念ながら少し雲が流れており、まん丸な日の出を拝むことはできませんでした。それでも、徐々に色を変えながら東の空が明るんでいき、山を越えた雲の間から太陽が顔を見せてくれました。

こちらの日の出は今頃、午前7時10分頃ですが、早いお遍路さんはその時刻にはもう、車や徒歩で上がって来られます。

家を出る頃はしっかりと着込んできましたが、早足で昇ってくるとやはり汗をかくくらい暖かくなりました。
しばらく日の出を楽しんだ後、境内の自販機で温かい缶コーヒーを買って飲みましたが美味でした。

土佐もハウス園芸が盛んですが、この時期は南国でも加温が必要です。さっきまでは何も見えなかったハウスの煙突からも煙(湯気)が立ち登り、夜明けの寒さに備えているようです。






























