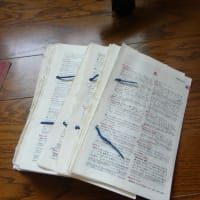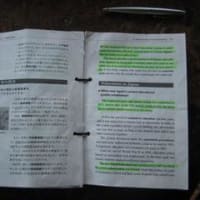今日は新聞が休みです。で、標題のことで一言。何となく難しげに感じられる標題になりました。 が、これは実際私が最近まで抱えていた疑問点です。
英語を読んでいて解らないものに出会うことがありました。何が、どのようにわからないかがわかると、大体解けたようなものです。しかしそれでも、疑問点の所在がわかっても、それへの回答ですが、それが又難しい。その答えに答えてくれる人も、資料もなかなか近くにない、というのが、サラリーマンしながら勉強している自分を取り巻く現状でした。だから理解するまでに結構時間がかかったのです。だから逆によく覚えている。
わからなかったことの原因は、今から分類すると、以下のとおりです。
①構造がわからないーSVOCの関係がわからない。
②何かが省略されているようだが元の形が想像できない
③倒置があるみたいだが元の形がわからない
④順番が変わっているらしい。(気まぐれで順番を変えるのだろうか、いい加減な気まぐれには付きあいたくはないが。もしルールがあるなら、それはどのようなものか?)
などと共に、
⑤どこまでの複雑な文章構造に対処できたら、自分は英文が解る人だと自己認識できるのだろうか、という気持ちがあました。
これは一種の恐怖感でした。自分に自信がないのですから、長い文章が来るとやや怖かったのです。それで標題のような言葉になったわけです。
けれども、答えは、意外と、簡単なものであると、わかりました。つまり、
文章構造的には、次の三つしかなく、せいぜい、複雑だ、長いといったって、複文が一番長くて、複雑なのだと、わかりました。これで、大きな安心感をもいつことができました。
①単文
②重文(単文をand またはor 等の等位接続詞で結ぶ)
③複文(主節と従属節がある。従属節は各種の接続詞ーbecause, as, for, when,while , although 等々ーで始まる。)
以上の形式で表現できなければ、文章を分割するなどによって対処せざるを得ない。これは、日本語でも、ほぼ同じ原理と思われます。
つまり、言葉は書き手だけではなく読み手にもわかってもらわなくては意味がありません。その意味では、複文の形式が、その限界なのだろうと、おもわれます。
ところで、ここで、付言したいことがあります。複文形式の中でまれに、従属節の中に更に、従属節がある形式を見かけます。つまり、接続詞+S1+V1(接続詞+S2+V2)、主節のS3+V3・・・、の形式の文章を見かけます。たとえば、「ずーと外出していなかったのでその日は外へ行くつもりfだったが、ある事情があっていけなくなってしまった」等の場合です。Although I had thought I would go out that day because I bad not been out for a long time, I finally had to stay home that day also for some reason.(注:実際の例文を集めていないので、ここに上げた例文はいま私が勝手につくっているものですので、少しおかしいとこがあるかも知れません。)
上の例は、従属節の中に、また従属節がある形式でしたが、もうひとつの形としては、従属節の中に副詞句が入る場合があります。たとえばdespiteを使って副詞句を作れます。despite the fac t that ・・・・となりますと、that以下にs,vがきてやたらに長い文章になることがあります。
けれども、そこまでが、せい一杯である。それ以上長いものは、私は見たことがありません。もしあれば、それは、悪文に違いありません。
これが構造上の長さの問題です。
構造上の問題ではなくて、長くなることがあります。たとえば、名詞を関係代名詞の継続用法で、あとから修飾する場合などです。だけどこれは意外とハッキリしているので、長くてもそれほど頭が混乱することはないのではないでしょうか。
何が言いたかったのかと言えば、常識的な英語の構造としては、どこまで、複雑になりえるのかということが、わかったことで、安心ができた、ということがいいたかったわけです。
語順は違うが、日本語とほぼ同じ感覚だと、私は思います。
英語を読んでいて解らないものに出会うことがありました。何が、どのようにわからないかがわかると、大体解けたようなものです。しかしそれでも、疑問点の所在がわかっても、それへの回答ですが、それが又難しい。その答えに答えてくれる人も、資料もなかなか近くにない、というのが、サラリーマンしながら勉強している自分を取り巻く現状でした。だから理解するまでに結構時間がかかったのです。だから逆によく覚えている。
わからなかったことの原因は、今から分類すると、以下のとおりです。
①構造がわからないーSVOCの関係がわからない。
②何かが省略されているようだが元の形が想像できない
③倒置があるみたいだが元の形がわからない
④順番が変わっているらしい。(気まぐれで順番を変えるのだろうか、いい加減な気まぐれには付きあいたくはないが。もしルールがあるなら、それはどのようなものか?)
などと共に、
⑤どこまでの複雑な文章構造に対処できたら、自分は英文が解る人だと自己認識できるのだろうか、という気持ちがあました。
これは一種の恐怖感でした。自分に自信がないのですから、長い文章が来るとやや怖かったのです。それで標題のような言葉になったわけです。
けれども、答えは、意外と、簡単なものであると、わかりました。つまり、
文章構造的には、次の三つしかなく、せいぜい、複雑だ、長いといったって、複文が一番長くて、複雑なのだと、わかりました。これで、大きな安心感をもいつことができました。
①単文
②重文(単文をand またはor 等の等位接続詞で結ぶ)
③複文(主節と従属節がある。従属節は各種の接続詞ーbecause, as, for, when,while , although 等々ーで始まる。)
以上の形式で表現できなければ、文章を分割するなどによって対処せざるを得ない。これは、日本語でも、ほぼ同じ原理と思われます。
つまり、言葉は書き手だけではなく読み手にもわかってもらわなくては意味がありません。その意味では、複文の形式が、その限界なのだろうと、おもわれます。
ところで、ここで、付言したいことがあります。複文形式の中でまれに、従属節の中に更に、従属節がある形式を見かけます。つまり、接続詞+S1+V1(接続詞+S2+V2)、主節のS3+V3・・・、の形式の文章を見かけます。たとえば、「ずーと外出していなかったのでその日は外へ行くつもりfだったが、ある事情があっていけなくなってしまった」等の場合です。Although I had thought I would go out that day because I bad not been out for a long time, I finally had to stay home that day also for some reason.(注:実際の例文を集めていないので、ここに上げた例文はいま私が勝手につくっているものですので、少しおかしいとこがあるかも知れません。)
上の例は、従属節の中に、また従属節がある形式でしたが、もうひとつの形としては、従属節の中に副詞句が入る場合があります。たとえばdespiteを使って副詞句を作れます。despite the fac t that ・・・・となりますと、that以下にs,vがきてやたらに長い文章になることがあります。
けれども、そこまでが、せい一杯である。それ以上長いものは、私は見たことがありません。もしあれば、それは、悪文に違いありません。
これが構造上の長さの問題です。
構造上の問題ではなくて、長くなることがあります。たとえば、名詞を関係代名詞の継続用法で、あとから修飾する場合などです。だけどこれは意外とハッキリしているので、長くてもそれほど頭が混乱することはないのではないでしょうか。
何が言いたかったのかと言えば、常識的な英語の構造としては、どこまで、複雑になりえるのかということが、わかったことで、安心ができた、ということがいいたかったわけです。
語順は違うが、日本語とほぼ同じ感覚だと、私は思います。