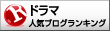2018年秋、東京・新国立劇場にて鑑賞。記念すべきタベリストツアー第1回目で観た『サロメ』と同じ劇場です。(ただしサロメは中劇場、今回は小劇場)
参加メンバーはヤマリン王&パープリン王子に私という、前回の『オーランドー』と同じ。ゴンベ王の復帰を酒をご用意してお待ちしております。
演目は哲学者ジャン=ポール・サルトルによる戯曲を小川絵梨子さんが翻訳・演出された『出口なし』。登場人物が大竹しのぶさん、多部未華子さん、段田安則さんの3人プラス1人に限定された、上演時間約80分のワンシチュエーション劇です。
謎の案内人により謎の部屋に連れて来られた女2人と男1人。互いを知れば知るほど相容れない、相性の悪さを実感するにつれ、その部屋に閉じ込められた意味を三人は悟ることになります。
(以下、ネタバレです)
劇中でも早い段階で明かされますから伏せる必要も無いんだけど、三人はそれぞれ罪を背負って現世を去った死者。つまりこの部屋は地獄という事になります。
なるほど、針山や血の池に放り込まれるよりも、全く理解し合えない人間と一緒に密室で過ごす事の方がよっぽど地獄ってワケです。
私もかねてから、そういうシチュエーションに勝る苦痛は無いって思ってましたから、この設定にはすんなり乗って行けました。
加えて、若い女には興味がない段田さんが大竹さんに惹かれ、男嫌いの大竹さんが多部ちゃんに惹かれ、男に依存して生きる術を本能的に身につけた多部ちゃんが段田さんにひたすら迫るという、永遠に一方通行の三角関係。
変な話だけどウチの家族がそういう構図になってるんですよね。もちろん恋愛感情とかじゃないんだけど、一番自分を見て欲しい相手に全く見てもらえない無限地獄。よく解ります。
さらに、これが作者の一番描きたかった事みたいだけど、他者の眼を通してしか自分の存在価値を計れない地獄。鏡はもちろん窓ガラスすら無い部屋で、自分の化粧をチェック出来ない多部ちゃんがその苦しみを最も体現することになります。
つまりは他者にどう思われてるのかが全く読み取れない恐怖。私が単独行動を好むのも、常に「他人は他人」「自分は自分」と口にするのも、実は人一倍それを恐れてることの裏返しなんだろうなと、以前から自覚してたりします。
他にもっと深くて複雑なテーマがあるのかも知れないけど、比較的に分かり易い以上3種の地獄だけで、この物語を自分自身に置き換えることがすんなり出来ました。これまでタベリストツアーで観てきた6本の舞台の中で、本作が一番感情移入し易かったです。
でも、それが演劇として面白いのかどうかは別問題で、映画に例えるとハリウッド大作みたいに大掛かりだった『サロメ』や『わたしを離さないで』で味わったスペクタクル感は皆無で、日本映画が最も地味だった頃のATG作品を観てるような感覚w
私が観た6本の中で最も小規模な、言わばインディーズに近い舞台に超一流のキャストが出演してる不思議な感じは、多部ちゃんが主演した短編映画『真夜中からとびうつれ』を彷彿させるものがありました。
だから、もし出演してるのが無名で華のない役者さんだったら、果たしてこの舞台を楽しめただろうか?なんて思ったりもします。
逆に、純粋に役者さんの演技を堪能するにはこういう舞台が一番良いのかも知れないし、いろんな形があっていいんだと言うほか無いですよね。
タベリスト的には何と言っても、おそらく多部ちゃん史上初であろう「男に依存して生きるズルい女」の役を演じる多部ちゃんが見所です。
芯が強くて他者に媚びないキャラクターが持ち味であり最大の魅力なのに、それを封印して段田さんに甘えまくる多部ちゃんが見られたのは新鮮でした。「いるいる、こういう女」って、特に女性が眉をしかめるようなタイプのキャラです。私の職場にもいましたよ、ああいう女性w
それはともかく、ストーリーのまとめとしては、他者による自分の評価を気にしながら、いろんな他者と関わって生きていくのは地獄のようにツラい事だけど、一歩引いて客観的に見ればこんなに滑稽なんだよと。いくら悩んだって出口はどうせ見つからないんだから、開き直って気楽にやって行こうよと。多分そういう事なんでしょう。私もそうありたいと常々思ってます。
私としては自己投影しやすくて面白かったけど、尺が短くスペクタクルが無いぶん、物足りなさは否めませんでした。今回はお色気サービスも無かったし、良くも悪くも至極まともな演劇を観たなぁという印象です。
分かりやすく、しっかりした内容で、なおかつ安心して観てられる超プロフェッショナルな出演陣で本当に素晴らしい反面、何もかも整いすぎて退屈と言えなくもない。
すっかりナマ多部ちゃんに対する免疫も出来てしまった今、『サロメ』の時と同等の高揚感が味わえるのは、もはや多部ちゃんが脱いだ時だけかも?なんて言ったらマトモなファンに叱られそうだけど、それが私の偽らざる感想です。