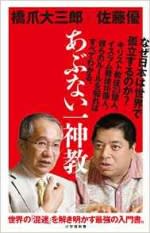(承前)
(7)働くことは罰なのか
イスラム世界には、カトリック文化圏や正教文化圏のような消費への強迫観念はない。
大金持ちでも大金を出したがらない。クアルーン(コーラン)にはイスラムの「五行」のひとつとして、収入の一部を貧しい人に施す制度的な喜捨「ザカート」が定められている。あとは自由意志で行う喜捨「バクシーシ」があるが、貧しい人が近寄ってきても、金持ちは何もないからといって追い払っている。
ムスリムは、シャリーアさえ守っていれば、富の蓄積は悪いことではないと考えている。だからイスラム世界では、大金持ちになっても責められることはない。そこが貯蓄をしないカトリック世界との違いだ。
強いてイスラム世界の消費活動を挙げれば、ラマダン月の日没後にはじめて食べる「イフタール」だ。あれは豪勢だ。実はラマダン月は断食しているはずなのに食料消費量が倍近くになる。
富が集中して拡大した不平等を解消するためにラマダンがある、金持ちも貧しい人と同じように腹が減る、飢えるという身体的現象により食べ物がない苦しさがどんな金持ちにもわかる仕組みになっている、ラマダンは同胞愛を実践する精神がある・・・・というのは理想だ。
実際には、ラマダン月になると、金持ちは睡眠誘導剤を使って昼夜逆転の生活をはじめる。日の出に寝て、日没が近づくと起き出す。イスラム世界では、ラマダン月は日没に鐘が鳴る。すると「おお、イフタールだ」と豪華な食事をする。「ラマダンは太ってしょうがねえな」なんて平気でいっているのが現実だ。
とはいえ、ラマダンを守りイスラム法を守っていればいいという態度がイスラム世界の基本だ。教会が威張っているカトリックや正教の社会のように、蓄積した富をむしり取られる心配はない。
一方、プロテスタントでは教会の脅しはない。ただし、プロテスタントの初期は、国家と教会が一体となっているから強制的に教会税をとられた。そういう国でプロテスタント教会の牧師は、全員国家公務員。現在もドイツ、オーストリア、スイスなどでは教会税という制度を設けている。
税金の特徴は税率が決まっていること。課税されて納税した残りは正当な私有財産として認められる。だからプロテスタントの国では脱税はきわめつきの犯罪、大きな社会問題となる。
米国では脱税犯は、悪魔と契約したような扱いで追及される。脱税しなければ豪邸に住もうがおかまいなし。むしろ多額の納税をしたわけだから社会に貢献しているということで、周囲は尊敬を示すし、本人にとって誇りだ。この感覚はカトリックの消費感覚と違っている。
つまりプロテスタントでは、経済活動から富を得た場合、「法律に従っている」「納税している」に加え、「正当に獲得した」ことの証明が要る。
正当に獲得するには、まず自分が働く。他者と契約して所有権を譲り受ける。自分が所有する原材料や土地をもとに商品を製造したり、付加価値をつけて販売するなど、正当な労働が必要だ。
正当な労働は労働価値説という表現をとり、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ世界に広まって定着した。労働価値説とは、商品の価値はその生産で働いた量によって決まるという説だ。これは世俗化したキリスト教の信念の一つだ。
しかし、労働が正当な所有権を得るための行為という考えは、もともとのキリスト教にはなかった。それは「マタイ福音書」にある「ブドウ園の労働者」のたとえ話からも明らかだ。
天国のあるブドウ園の主人が、早朝に1デナリを支払うと約束して労働者を雇った。しばらくして暇そうな人を見つけて「金を払うから手伝ってくれ」と頼んだ。夕方になると仕事にあぶれた労働者も雇った。
やがて仕事が終わると、主人は夕方から働いた労働者から順番に銀貨を渡していった。しかも朝から働いた労働者も夕方に来た人も一律1デナリを渡した。
労働価値説に立つならば、労働時間や労働量で、支払われる賃金は変わる。「俺は朝から働いているのに、なんでみんなと同じ扱いなんだ」と抗議した労働者に対して、「私はおまえに1デナリ払うと約束しただろう。私の金をどう使おうが私の勝手だ」と強弁する。この話からは、労働価値説につながる論理は出てこない。
もうひとつ印象的なのは、「創世記」の冒頭、楽園追放のくだり。アダムとイブが楽園で暮らしていた頃、労働しなくてよかった。ところが、神の命にそむいて智慧の実を食べた結果、楽園を追放された。追放するとき神は、額に汗して働かないと生きる糧が手に入らない、という罰を与えた。労働は罰なのだ。
ただし、労働は男に対する罰であって、出産が女に対する罰だ。
罰ではあっても、労働を命じられた。労働することは間違っていない。
ただし、労働は罰なので、労働しないほうが偉いことになる。罪深い人間だけが働けばよい、という身分制につながる。田畑で額に汗して働く農奴が社会の最底辺となり、政治や軍事に携わり、労働をしない人びとがセレブの地位を確保し、共同体の間を行き来し、モノを動かしてお金を儲ける商人はその中間、こういうヒエラルキーが生まれた。
このヒエラルキーは1,500年も続いた。
キリスト教のこの伝統をみると、正当な所有権の源泉は労働であるというアイデアは出てきそうにもない。相当変わった考え方だ。
どこから出てきた考えなのか、難しいが、労働価値説は労働量を数値化しなければ出てこない考え方だ。そして、労働の数値として計るには、貨幣経済と賃労働が成立していなければならない。
当時は、身分制度のトップの王や貴族が莫大な土地を所有していた。農民は土地を彼らから使わせてもらわなければならない。そして、教会は農民から教会税をとる。
領主に対して、そして教会に対しての二重課税でしわ寄せがくるのは、身分制度が下の人たちだ。しかも王様や貴族には特権がある。彼らと結託した商人は、商工業も独占できるお墨付き「特許状」をもらい、不当の高く物を売ったり、権益を独り占めした。
そこで不当に虐げられているのは真面目な勤労者たちだった。彼らは自分が真面目に働いているのに、身分制度のせいでキリスト教の教え、隣人愛が実践できないと感じる。そして彼らは、教会と封建制度を問題にし始める。
封建的な身分制度の崩壊が始まった。同時に、貨幣経済と賃労働の方が徐々に見えてきた。
□佐藤優『あぶない一神教』(小学館新書、2015)/共著:橋爪大三郎
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
●第3章 キリスト教の限界
「【佐藤優】イエス・キリストは「神の子」か ~ キリスト教の限界(1)~」
「【佐藤優】ユニテリアンとは何か ~ キリスト教の限界(2)~」
「【佐藤優】ハーバード大学にユニテリアンが多い理由 ~ キリスト教の限界(3)~」
「【佐藤優】サクラメントとは何か ~ キリスト教の限界(4)~」
「【佐藤優】何がキリスト教信仰を守るのか ~ キリスト教の限界(5)~」
「【佐藤優】第一次世界大戦という衝撃 ~ キリスト教の限界(6)~」
「【佐藤優】なぜバルトはナチズムに勝ったのか ~ キリスト教の限界(7)~」
「【佐藤優】皇国史観はバルト神学がモデル? ~ キリスト教の限界(8)~」
「【佐藤優】米国が選ぶのは実証主義か霊感説か ~ キリスト教の限界(9)~」
「【佐藤優】無関心の共存は可能か ~ キリスト教の限界(10)~」
●第4章 一神教と資本主義
「【佐藤優】資本主義は偶然生まれたのか ~一神教と資本主義(1)~」
「【佐藤優】なぜ人間の論理は発展したのか ~一神教と資本主義(2)~」
「【佐藤優】最後の審判を待つ人の心境はビジネスに近い ~一神教と資本主義(3)~」
「【佐藤優】15世紀の教会はまるで暴力団 ~一神教と資本主義(4)~」
「【佐藤優】隣人が攻撃されたら暴力は許されるのか ~一神教と資本主義(5)~」
「【佐藤優】自然は神がつくった秩序か ~一神教と資本主義(6)~」
「【佐藤優】働くことは罰なのか ~一神教と資本主義(7)~」
「【佐藤優】市場経済が成り立つ条件 ~一神教と資本主義(8)~」
「【佐藤優】神の「視えざる手」とは何か ~一神教と資本主義(9)~」
「【佐藤優】なぜイスラムは、経済がだめか ~一神教と資本主義(10)~」
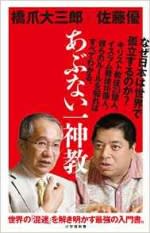
(7)働くことは罰なのか
イスラム世界には、カトリック文化圏や正教文化圏のような消費への強迫観念はない。
大金持ちでも大金を出したがらない。クアルーン(コーラン)にはイスラムの「五行」のひとつとして、収入の一部を貧しい人に施す制度的な喜捨「ザカート」が定められている。あとは自由意志で行う喜捨「バクシーシ」があるが、貧しい人が近寄ってきても、金持ちは何もないからといって追い払っている。
ムスリムは、シャリーアさえ守っていれば、富の蓄積は悪いことではないと考えている。だからイスラム世界では、大金持ちになっても責められることはない。そこが貯蓄をしないカトリック世界との違いだ。
強いてイスラム世界の消費活動を挙げれば、ラマダン月の日没後にはじめて食べる「イフタール」だ。あれは豪勢だ。実はラマダン月は断食しているはずなのに食料消費量が倍近くになる。
富が集中して拡大した不平等を解消するためにラマダンがある、金持ちも貧しい人と同じように腹が減る、飢えるという身体的現象により食べ物がない苦しさがどんな金持ちにもわかる仕組みになっている、ラマダンは同胞愛を実践する精神がある・・・・というのは理想だ。
実際には、ラマダン月になると、金持ちは睡眠誘導剤を使って昼夜逆転の生活をはじめる。日の出に寝て、日没が近づくと起き出す。イスラム世界では、ラマダン月は日没に鐘が鳴る。すると「おお、イフタールだ」と豪華な食事をする。「ラマダンは太ってしょうがねえな」なんて平気でいっているのが現実だ。
とはいえ、ラマダンを守りイスラム法を守っていればいいという態度がイスラム世界の基本だ。教会が威張っているカトリックや正教の社会のように、蓄積した富をむしり取られる心配はない。
一方、プロテスタントでは教会の脅しはない。ただし、プロテスタントの初期は、国家と教会が一体となっているから強制的に教会税をとられた。そういう国でプロテスタント教会の牧師は、全員国家公務員。現在もドイツ、オーストリア、スイスなどでは教会税という制度を設けている。
税金の特徴は税率が決まっていること。課税されて納税した残りは正当な私有財産として認められる。だからプロテスタントの国では脱税はきわめつきの犯罪、大きな社会問題となる。
米国では脱税犯は、悪魔と契約したような扱いで追及される。脱税しなければ豪邸に住もうがおかまいなし。むしろ多額の納税をしたわけだから社会に貢献しているということで、周囲は尊敬を示すし、本人にとって誇りだ。この感覚はカトリックの消費感覚と違っている。
つまりプロテスタントでは、経済活動から富を得た場合、「法律に従っている」「納税している」に加え、「正当に獲得した」ことの証明が要る。
正当に獲得するには、まず自分が働く。他者と契約して所有権を譲り受ける。自分が所有する原材料や土地をもとに商品を製造したり、付加価値をつけて販売するなど、正当な労働が必要だ。
正当な労働は労働価値説という表現をとり、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ世界に広まって定着した。労働価値説とは、商品の価値はその生産で働いた量によって決まるという説だ。これは世俗化したキリスト教の信念の一つだ。
しかし、労働が正当な所有権を得るための行為という考えは、もともとのキリスト教にはなかった。それは「マタイ福音書」にある「ブドウ園の労働者」のたとえ話からも明らかだ。
天国のあるブドウ園の主人が、早朝に1デナリを支払うと約束して労働者を雇った。しばらくして暇そうな人を見つけて「金を払うから手伝ってくれ」と頼んだ。夕方になると仕事にあぶれた労働者も雇った。
やがて仕事が終わると、主人は夕方から働いた労働者から順番に銀貨を渡していった。しかも朝から働いた労働者も夕方に来た人も一律1デナリを渡した。
労働価値説に立つならば、労働時間や労働量で、支払われる賃金は変わる。「俺は朝から働いているのに、なんでみんなと同じ扱いなんだ」と抗議した労働者に対して、「私はおまえに1デナリ払うと約束しただろう。私の金をどう使おうが私の勝手だ」と強弁する。この話からは、労働価値説につながる論理は出てこない。
もうひとつ印象的なのは、「創世記」の冒頭、楽園追放のくだり。アダムとイブが楽園で暮らしていた頃、労働しなくてよかった。ところが、神の命にそむいて智慧の実を食べた結果、楽園を追放された。追放するとき神は、額に汗して働かないと生きる糧が手に入らない、という罰を与えた。労働は罰なのだ。
ただし、労働は男に対する罰であって、出産が女に対する罰だ。
罰ではあっても、労働を命じられた。労働することは間違っていない。
ただし、労働は罰なので、労働しないほうが偉いことになる。罪深い人間だけが働けばよい、という身分制につながる。田畑で額に汗して働く農奴が社会の最底辺となり、政治や軍事に携わり、労働をしない人びとがセレブの地位を確保し、共同体の間を行き来し、モノを動かしてお金を儲ける商人はその中間、こういうヒエラルキーが生まれた。
このヒエラルキーは1,500年も続いた。
キリスト教のこの伝統をみると、正当な所有権の源泉は労働であるというアイデアは出てきそうにもない。相当変わった考え方だ。
どこから出てきた考えなのか、難しいが、労働価値説は労働量を数値化しなければ出てこない考え方だ。そして、労働の数値として計るには、貨幣経済と賃労働が成立していなければならない。
当時は、身分制度のトップの王や貴族が莫大な土地を所有していた。農民は土地を彼らから使わせてもらわなければならない。そして、教会は農民から教会税をとる。
領主に対して、そして教会に対しての二重課税でしわ寄せがくるのは、身分制度が下の人たちだ。しかも王様や貴族には特権がある。彼らと結託した商人は、商工業も独占できるお墨付き「特許状」をもらい、不当の高く物を売ったり、権益を独り占めした。
そこで不当に虐げられているのは真面目な勤労者たちだった。彼らは自分が真面目に働いているのに、身分制度のせいでキリスト教の教え、隣人愛が実践できないと感じる。そして彼らは、教会と封建制度を問題にし始める。
封建的な身分制度の崩壊が始まった。同時に、貨幣経済と賃労働の方が徐々に見えてきた。
□佐藤優『あぶない一神教』(小学館新書、2015)/共著:橋爪大三郎
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
●第3章 キリスト教の限界
「【佐藤優】イエス・キリストは「神の子」か ~ キリスト教の限界(1)~」
「【佐藤優】ユニテリアンとは何か ~ キリスト教の限界(2)~」
「【佐藤優】ハーバード大学にユニテリアンが多い理由 ~ キリスト教の限界(3)~」
「【佐藤優】サクラメントとは何か ~ キリスト教の限界(4)~」
「【佐藤優】何がキリスト教信仰を守るのか ~ キリスト教の限界(5)~」
「【佐藤優】第一次世界大戦という衝撃 ~ キリスト教の限界(6)~」
「【佐藤優】なぜバルトはナチズムに勝ったのか ~ キリスト教の限界(7)~」
「【佐藤優】皇国史観はバルト神学がモデル? ~ キリスト教の限界(8)~」
「【佐藤優】米国が選ぶのは実証主義か霊感説か ~ キリスト教の限界(9)~」
「【佐藤優】無関心の共存は可能か ~ キリスト教の限界(10)~」
●第4章 一神教と資本主義
「【佐藤優】資本主義は偶然生まれたのか ~一神教と資本主義(1)~」
「【佐藤優】なぜ人間の論理は発展したのか ~一神教と資本主義(2)~」
「【佐藤優】最後の審判を待つ人の心境はビジネスに近い ~一神教と資本主義(3)~」
「【佐藤優】15世紀の教会はまるで暴力団 ~一神教と資本主義(4)~」
「【佐藤優】隣人が攻撃されたら暴力は許されるのか ~一神教と資本主義(5)~」
「【佐藤優】自然は神がつくった秩序か ~一神教と資本主義(6)~」
「【佐藤優】働くことは罰なのか ~一神教と資本主義(7)~」
「【佐藤優】市場経済が成り立つ条件 ~一神教と資本主義(8)~」
「【佐藤優】神の「視えざる手」とは何か ~一神教と資本主義(9)~」
「【佐藤優】なぜイスラムは、経済がだめか ~一神教と資本主義(10)~」