音楽は好きだけど学問(「音楽学」)となるとあまり好きになれないなあ・・、しかし「音楽学」っていったい何?
音楽とはそもそも言葉では表現できないから、(言葉の代わりに)音符という記号を使っているのに、そういう学問がいったい成り立つのだろうか。
そういう疑問のきっかけはこの新聞記事だった。
いつも新刊書は図書館でたまたま目に触れたもののうち興味のある本だけ借りてくるのだが、この本ばかりは興味を惹かれて在庫の有無をググってみたところ、「在庫有り」の表示なのでさっそく図書館に駆け付けて借りてきた。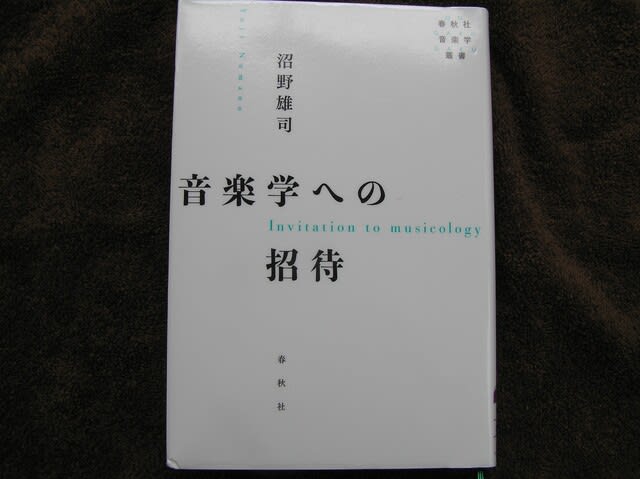
さっそく読み始めたところ、とても気軽に読める本ではなかった。
とはいえ、ブログのネタにする以上何とか粘ってみないと~(笑)。
本書の冒頭にこうある。(要旨)
「音楽学という学問分野をご存知だろうか。読んで字のごとく、音楽についての学問の総称が音楽学である。実はほとんどの日本の音楽大学には音楽学の専攻課程があるし一般大学の場合ならば美学専攻などの課程において音楽学の研究ができる。
筆者は大学と大学院で音楽学を専攻し、現在は音楽大学で音楽学を教えている。つまりは「音楽学者」だ。
講義でよく学生に話すのだがもしも生まれ変わることができたら、また音楽学者になりたいと強く願っている。
なぜなら対象に触れること自体に喜びがある。演奏会に行ったり、CDを聴いたりピアノやギターをつま弾いたりするのがすべて「仕事・研究」の一部なのだといったら、お分かりいただけようか。
まず対象に触れる圧倒的な楽しさがあり、さらにそれについて調べたり論じたりする楽しさがあるから、一粒で二度おいしい学問なのである。
そしてもうひとつ、学問としての枠組みが形成されたのが19世紀半ばと比較的遅いせいもあって、音楽あるいは音とどこかで関連していればどんな研究でも簡単に音楽学になってしまうという融通無碍(ゆうずうむげ)な性格を持っていることだ。つまり、対象と方法論が強度に自由なのである。
たとえば「哲学」「史学」「物理学」「教育学」の前に「音楽哲学」「音楽史学」「音楽物理学」「音楽教育学」といった具合に音楽という言葉を付けるだけで学問として成立してしまう」
とまあ、以上のような内容で「音楽学」についておぼろげながらお分かりいただけたかな~。
で、一番興味を惹かれたのが第二章の「モーツァルト効果狂騒曲」についてだった。
「音楽心理学」の分野において、モーツァルト効果を検証した内容である。
たとえばモーツァルトを聴くだけでなぜか頭が良くなったり、身体の調子が良くなったり、はたまたお酒や味噌が美味しくなったりもするという不思議な効果についての検証である。
大のモーツァルトファンを自負しているので、舌なめずりをしながら読ませてもらった(笑)。
まず、論争のきっかけになったのは1993年に国際的な科学誌「ネイチャー」365号に「音楽と空間認識能力」という実験報告が掲載されたこと。
モーツァルトの「二台のピアノのためのソナタ ニ長調 K448」を36人の大学生に対して10分間聴かせた後で「空間認識テスト」を行ったところ、有意に成績が上がったという実験結果が出たというもの。
この実験が大きな論争を呼び次々に追試がなされて侃々諤々(かんかんがくがく)の世界的な論争が巻き起こった。
はたしてモーツァルトの音楽に人間の知能の向上、あるいは認知症を予防する効果があるのかどうか・・、もったいぶるわけではないがこの解答は本書を読んだ人だけの特権ということにしておきましょう(笑)。
ちなみに、筆者は最後にこう結んでいる。
「このモーツァルト効果騒動は、神童、天才、長・短調、古典派、クラシック音楽といった概念そのものや、それらが流通するメカニズムの再検討をゆるやかに促すとともに、モーツァルトという稀有な作曲家の表象/現象の持つ広がりを改めて我々に示すものであるように思う。
モーツァルトを聴くだけで知能が向上したり、病気が治ったりするという話は時として奇妙な商売に結びついたりするから、こうした研究が結果として社会に有害な場合もあるだろう。
だが、幸いにしてひとつだけいえるのはとりあえずモーツァルトに副作用はないことだ。薬品や食品の場合と異なり、毎日浴びるようにモーツァルトを聴いても健康被害が生じることはないはずで(モーツァルトマニアになるという副作用はあるかもしれないが)、つまりはこのことがこの少々怪しげな効果が比較的大らかに受け入れられている最大の理由ということになるのだろう。」
この内容に共感された方は積極的にクリック → 

















