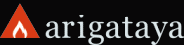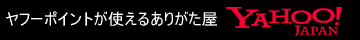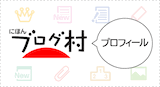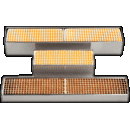薪ストーブ暮らしが大好きでブログ書いてます。
燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!
薪ストーブ|薪焚亭
アッパーファイヤーバック

バックパネルのガスケット化 のつづきです。
ダンパーハンドルのスペーサーとワッシャーリングは、アッパーファイヤーバックのアッセンブリーに含んでないので古いものを流用です。

ワッシャーリングがサイドパネルにぴったり密着するまで、外側に押し出さなければならない。 右下の写真に見えるスペーサーが更に押し出されて、サイドパネル面よりも少し出っ張るようになるのが正しい位置です。

左写真はバックプレート左側の収まり具合で、ヒートデフレクターも置いた状態です。
右の写真は二次燃焼空気の流路ですね。
バックパネルの空気取り入れ口から入った空気は、二次燃焼室の下を通ってロアーファイヤーバックとの隙間を上って未燃焼ガスと出会う訳です。


右側は矢印の先に見えるボルトだけでの固定なので、バックパネルを抑えながらの結構ハード作業だし、このボルト一本でアッパーファイヤーバック半分の重さを支えていることになるので、少々心細いような気もする。

熱収縮を頻繁に繰り返す場所なんだから、折れることを前提にボルトとナットで固定する方法にして欲しいところです。

簡単に出来る対策としては、耐熱グリスを塗って組んでおけば、ボルト折れの確率が減ります。

最初にアッパーファイヤーバックを外した時、崩れ落ちた大量のセメントはこの部分のセメントだと思う。
つづく
※この記事は2006年の7月に書いたものを基に、今の感覚で加筆したものです。
11月19日~30日まで 薪ストーブカレンダープレゼント2013 実施中!
まきたきてー発電所 毎日の発電実績
コメント ( 4 ) | Trackback ( )