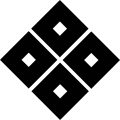伊庭貞剛邸の案内板、背後の竹林が西宿城
伊庭貞剛邸の案内板、背後の竹林が西宿城
旧中山道の西宿地区のほぼ中央部辺りに大きな楠の木の下に「伊庭貞剛邸」の案内板が(西宿城のことはまったく触れられていないが)建てられている。近江鉄道の武佐駅のすぐ西側にある若宮神社周辺が西宿城跡である。若宮神社の両側にある竹藪に土塁が残っている、
この伊庭邸は西宿城の跡地に建てられたもので、伊庭邸の背後の竹林の中に1m程度の低土塁を巡らせた30m×40mの曲輪が残されている。

 土塁は東~北~西と廻らせ、曲輪は南側の旧中山道側に開いている。若宮神社の西側に土塁・空堀も確認、回遊式に整備されいる(公園の一部としてか)。【西宿城の駒札がなく残念】
土塁は東~北~西と廻らせ、曲輪は南側の旧中山道側に開いている。若宮神社の西側に土塁・空堀も確認、回遊式に整備されいる(公園の一部としてか)。【西宿城の駒札がなく残念】









 若宮神社の東側にも竹林にも、土塁は確認できる、【タケノコ採取竹林】に改変されているが
若宮神社の東側にも竹林にも、土塁は確認できる、【タケノコ採取竹林】に改変されているが

 ここから、、【タケノコ採取竹林】へ、地主ヵ、地権者カ・・・竹林は仕切られている!
ここから、、【タケノコ採取竹林】へ、地主ヵ、地権者カ・・・竹林は仕切られている!








土塁は東~北~西と廻らせ、曲輪は南側の旧中山道側に開いている。なお、西側土塁の外側には空堀も確認できる。
 R8側の近江鉄道の陸橋下の森
R8側の近江鉄道の陸橋下の森
 近江鉄道 武佐駅から近江八幡方面すぐ線路脇の竹藪
近江鉄道 武佐駅から近江八幡方面すぐ線路脇の竹藪
 東に・・・観音寺城が、国道武佐の交差点・信号の上に!
東に・・・観音寺城が、国道武佐の交差点・信号の上に!
 伊庭貞剛氏は、佐々木(伊庭氏)の末裔である。
伊庭貞剛氏は、佐々木(伊庭氏)の末裔である。
案内板によれば、伊庭貞剛は弘化4年(1841)に旧伊庭邸で生まれ、文久2年(1861)15歳の時に八幡町児島一郎の道場に通って剣を習い、21歳で免許皆伝を許されたとされ、明治元年(1868)に京都御所警備隊士となり、その後明治33年には住友家総理事になった人物とある。
伊庭貞剛
「別子銅山中興の祖」といわれ、明治時代に「東の足尾、西の別子」と言われた、住友新居浜精錬所の煙害問題の解決にあたり、環境復元にも心血を注ぎ、企業の社会的責任の先駆者と言われている。
近江源氏佐々木氏支流で伊庭氏一族。
総領事引退
1904年(明治37年)に「事業の進歩発展に最も害するものは、青年の過失ではなくして、老人の跋扈である」として総理事を辞し引退(ただし家長の友純の説得により住友家関係の顧問等は続けた)、また「もしその事業が本当に日本の為になるもので、しかも住友のみの資本では到底成し遂げられない大事業であれば、住友はちっぽけな自尊心に囚われないで何時でも進んで住友自体を放下し、日本中の大資本家と合同し、敢然之を造上げようという雄渾なる大気魄を絶えず確りと蓄えて居ねばならない」という言葉も残している。
引退後は、滋賀県石山(大津市)の活機園に住まう。1926年(大正15年)10月22日、石山の自宅にて没す。享年80。滋賀県近江八幡市に墓がある。
伊庭氏
伊庭氏(いばし)は、日本の氏族の1つ。宇多源氏佐々木氏支流
近江源氏佐々木氏の支流であり、佐々木経方の子、行実の四男実高(出羽権守重遠)が、はじめて近江国神崎郡伊庭邑に居住し、伊庭氏を称した。
伊庭城は建久年間(1190年 - 1199年)に実高によって築かれたといわれる。
実高の後、貞資、貞平、貞光、公貞、時高、氏貞、基貞、高貞、貞安、実貞、貞職、貞信、貞勝の14代を経て貞勝は蒲生郡桐原郷に身をよせ、後中小森で慶長12年(1607年)に没した。
貞勝の子の貞家は渡辺吉綱に仕え、伊庭氏は代官として近江における和泉伯太藩の飛び地(西宿、虫生、峰前、竹村等5ヵ村三千石)を代々支配するようになった。 実高が伊庭氏を名乗ってから25代の後裔にあたる貞剛は明治12年(1879年)、裁判官から住友本社に入社、明治33年(1900年)に第2代総理事となり住友財閥の基礎を築いた。
若宮神社
伊庭貞剛宅跡の側道を通り若宮神社(祭神は少彦名命など)を目指す。私は大鳥居前で止まり境内の積雪が10cm近いことを悟った。長靴を履いていないため正式な参拝は断念して頭だけ下げた。
近江中山道を引き返し武佐駅に向かう。晴天で融け出した雪が屋根から落下して大きな音が響き渡った。











≪参考≫
参考サイト/近江の城郭
滋賀県中世城郭分布調査(滋賀県教育委員会)
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。