両性類初、奈良のチ-ム
両生類では初めて、カエルのゲノム(全遺伝情報)の解読に奈良先端科学技術大学院大(奈良県生駒市)の萩野肇特任准教授(発生生物学)らの国際チ-ムが、成功、30日付けの米科学誌サイエンスに発表した。
両生類は、いずれもゲノムが解読されいいる魚類と、鳥類や哺乳類の間に位置する。魚がヒレを手足に変え、肺を発達させ陸上に進出した進化の道筋を解明する大きな手掛かりになりそうだ。チ-ムはアフリカ産のネッタイツメガエルのゲノム配列を解析。魚類、カエル、ヒトは、体内のタンパク質の設計図となる遺伝子の数は2万1千前後で、種類も大差がないことを明らかにした。しかし、遺伝子を働かせるスイッチの役割を果たすと考えられる塩基配列は、カエルとヒトでは多く共通していたが、魚類とは異なる部分が多く、受精卵からの成長過程で働くスイッチの違いが、生物としての違いにつながると考えられた。がんや心臓病などヒトの疾患にかかわる2千余りの遺伝子のうち約8割がカエルにもあったため、安価なカエルを用いた疾患研究のほか、両生類に特徴的な体の再生能力を遺伝子レベルで研究することで、再生医療への応用も期待できる。また、カエルは、内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)や農薬の影響を受けやすいことも知られており、どの遺伝子に作用しやすいかや、ヒトでの環境汚染問題の研究に役立ちそうだという。




















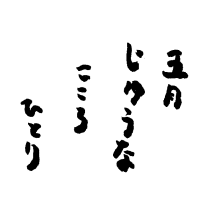
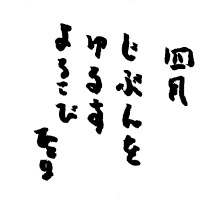







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます