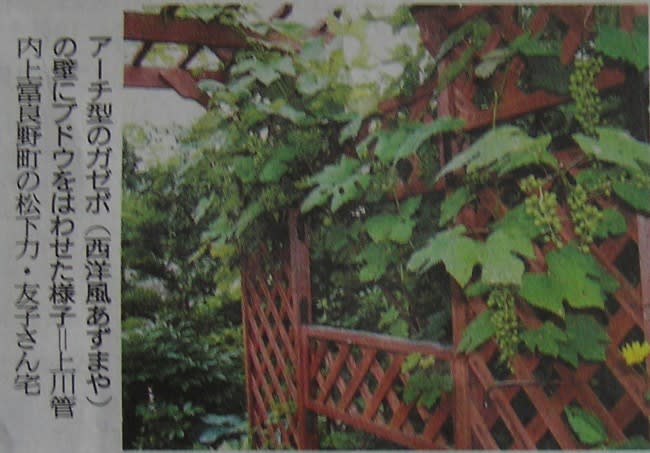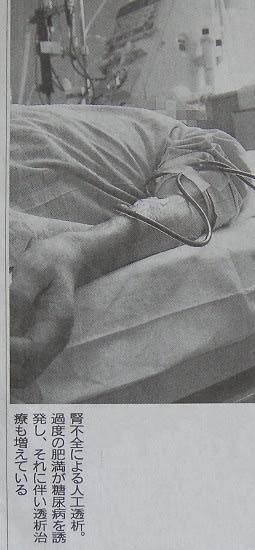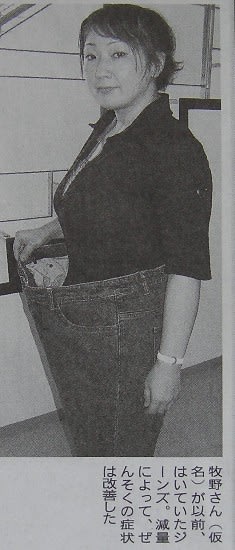実験 小学3~4年で顕著=東北大・川島教授
 ホットケ-キなどのおやつを親子で作ると、子どもの脳の発達に好影響をもたらす-。こんなほのぼのとした研究結果を、東北大加齢医学研究所の川島隆太教授が森永製菓との共同実験で明らかにした。川島教授は、前頭前野と呼ばれる脳の額に近い部分が、思考力や創造性、やる気、集中力、学習能力、コミニュケ-ションなど、人間性の中心的な働きを担っていることに着目。近赤外線の照射で脳の血流量の変化を測定する「光トボグラフィ-」で、親と一緒にホットケ-キやおやつを作る幼稚園から小学校6年までの子ども計43人の前頭前野の活動ぶりを調べた。その結果、「泡たて器で混ぜる」や「めん棒で生地を延ばす」など、さまざまな場面で前頭前野が活性化。特に「卵を割る」「チョコレ-トで飾り付けをする」といったやや複雑な工程で強く反応しているのが確認された。年代別では、3~4年生で最も活性化していた。川島教授は「指先を使ったり、わくわくしたりする場面で最も活性化している。やさしすぎても難しすぎてもいけないが、小学校中学年にとっておやつ作りはほどよい難易度なのではないか」と指摘している。また、20~22歳の大学生約390人を対象にアンケ-トを実施したところ、子ども時代に親子でおやつ作りをした経験がある人は、ない人と比べて、大人になってから「人生に対する前向きな気持ち」や「自信」「近親者の支え」などの幸福感をより強く感じていることも分かった。
ホットケ-キなどのおやつを親子で作ると、子どもの脳の発達に好影響をもたらす-。こんなほのぼのとした研究結果を、東北大加齢医学研究所の川島隆太教授が森永製菓との共同実験で明らかにした。川島教授は、前頭前野と呼ばれる脳の額に近い部分が、思考力や創造性、やる気、集中力、学習能力、コミニュケ-ションなど、人間性の中心的な働きを担っていることに着目。近赤外線の照射で脳の血流量の変化を測定する「光トボグラフィ-」で、親と一緒にホットケ-キやおやつを作る幼稚園から小学校6年までの子ども計43人の前頭前野の活動ぶりを調べた。その結果、「泡たて器で混ぜる」や「めん棒で生地を延ばす」など、さまざまな場面で前頭前野が活性化。特に「卵を割る」「チョコレ-トで飾り付けをする」といったやや複雑な工程で強く反応しているのが確認された。年代別では、3~4年生で最も活性化していた。川島教授は「指先を使ったり、わくわくしたりする場面で最も活性化している。やさしすぎても難しすぎてもいけないが、小学校中学年にとっておやつ作りはほどよい難易度なのではないか」と指摘している。また、20~22歳の大学生約390人を対象にアンケ-トを実施したところ、子ども時代に親子でおやつ作りをした経験がある人は、ない人と比べて、大人になってから「人生に対する前向きな気持ち」や「自信」「近親者の支え」などの幸福感をより強く感じていることも分かった。
前頭前野 大脳の前部に位置する前頭葉のうち、額のすぐ内側の部分。認知、判断や感情の制御など、高次の精神活動を担う。酸素の消費量を測定する機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)や、血流量の変化を調べる近赤外線脳計測装置(光トボグラフィ-)などで活性化の程度を調べることができる。