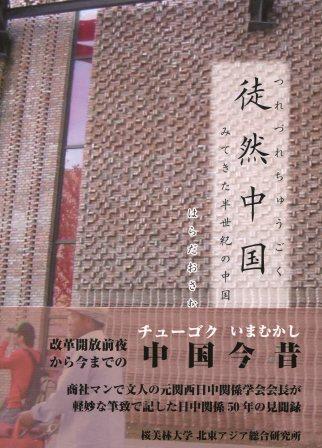三本の映画
― 異なる主題へのアプローチ ―
むかしは、映画制作所もあった宝塚だが、いまは地震のあと再開発された駅前ビルの5Fに、ひとつの独立系シネマがあるのみ。
ときおりネットで上映情報をさぐっては出かけるのだが、見逃すことも多い。
中国映画界の、いまや中堅的存在になったジャ・ジャンク―監督の「罪の手ざわり」は上映から一年余が過ぎた今年の夏に気づいたが、もう後の祭り。近在で上映しているところはなかった。
友人に教えてもらってネットで中国版DVDを見かけたが、十数分ごとにいろんな手順でアプローチを繰り返さねばならず、大枚をはたいて日本語字幕付のものを購入した。まだ一度しか観ていないが、どうまとめればいいか・・・。
先日予見なしに、このシネピピアでベトナムとの合作映画「ベトナムの風に吹かれて」を観た。
ベトナムには1976年、第一回ベトナム経済視察団で出かけている。
南部解放後まだ一年足らずのこのとき、日本はいち早く国交正常化の動きを見せていたが、わたしたちの視察団は、バンコク~ラングーン(当時)~ビエンチャン経由で、ハノイへは東京発五日目で到着した。ハノイは北爆のあとが痛々しく、サイゴン(当時)の港には赤錆びたクルマの残骸が山積みされていた。
90年代初めから半ばにかけての三度の訪越で、その発展ぶりは承知していたが、松坂慶子演じる日本語の教師が痴呆症の母親を日本から呼び寄せて何をしでかすのか・・・。まぁ、こんな感じでチケットを購入した。詳しくはあとで述べるが、これもネタに使えるか・・・という気持ちであった。
もう一本が公開三日目の昨夜に観た、吉永小百合の「母と暮らせば」である。
井上ひさしの広島原爆を題材にした戯曲(のち映画化)「父と暮らせば」の遺志を受け継いで、山田洋二監督が脚本も担当(共同)、映画化に取り組んだ「松竹120周年記念映画」。たまさかに開いた雲の隙間から投じられた原爆による長崎の惨事を、その三年後の「戦後」から振り返る・・・その手法。
昨夜は、午前に購入した予約券を手に、上映30分前シネマに着いた。
ロビーにある映画関係の書棚を眺めながら、『新藤兼人と映画 著作集2』を手にしてページを繰った。「シナリオ 待ちぼうけの女」の序文というか、「思い出」と題する一文は、「八月十五日を私は宝塚海軍航空隊で迎えた」ではじまっていた。そのはなしは耳にしたことはあったが、こうした手記があることは知らなかった。館内ロビーを見廻しても、コピー機はない。
受付に頼んで、事務室の責任者にその2ページばかりの短文を無料でコピーしてもらった、いまそれをとり出して読んでいる。
そのころ、わたしは六甲の北の農村に疎開していたが、当時は米軍機のビラ散布で爆撃予告がなされていたらしい。八月十五日は宝塚地区が「爆撃予定日」で、「特別退避令」により「宝塚の穴という穴は兵隊で塞がってしまっていた」「爆撃は正午の予定であった」が、伝令が来て「班長は直ちに本部へ集合せよ」。「天皇の放送であった・・・B29にやられる予定日に終戦になってしまったのだ」
これはわたしの知らない、「終戦秘話」だ。
映画がはじまった。
長崎医科大の階段教室、まさに授業が始まらんとしたとき、ピカッ!ドン。 それから三年後の8月9日の夕暮れ、長崎の高台で助産婦をして暮らす母・伸子(吉永小百合)の前に、医科大生であった息子・浩二(二宮和也)がひょっこり現れる。一瞬、ゾオッとする、ホラーもどきのシーン。それから大晦日まで、折にふれ、なんども現れては、母と思い出話に打ち興じ、フィアンセの結婚を見届けて、母は息子のもとへ身罷れていくのであった。
戦後七十年を生きてきて、静かな口調で「原爆詩」などを朗読し続ける吉永の、思いのたけをそのままに伝える映画になっている。
「ベトナムの風に吹かれて」主演の松坂慶子には、80年代のはじめ、上海のホテルで遭遇している。わたしは仕事仲間と会食中であったが、食堂の向こうのテーブルで商社の駐在員がひとりの女性のサインをもらおうとしていた。仲間に聞くと、アッ、松坂慶子や、と声をあげたが、だれも側へ行ってサインを求めようともしない。彼女は、わたしたちの側を黙って、通り過ぎていった。あとで耳にすると「上海バンスキング」のロケで滞在中であった由だが、無粋なわたしたちのメンバー、とりわけわたしとは無縁のひとであった。彼女主演の映画を観るのは、今回がはじめて。ハノイで日本語の教師をしているひとの原作にもとづく由だが、映画のキャッチフレーズは「若き日に憧れていたあの国で、今、母と生きていく」とある。
“テンコ盛り”のエピソードのなかで、日本の敗戦後、仏領インドシナでベトナムの解放戦争に参加した日本兵(のち日本へ帰国)と現地女性との間に生まれた男性に会いに行くカメラマンの女性(この日本兵の孫)のはなしもあった。1960年代の、日越友好協会の会合などでは、ディエンビ
エンフーの戦いで活躍したひとたちの話をよく耳にしたが、こんな話がいまでもベトナムで活きているのか・・・。奥田瑛二演じる「ベ平連」OBの、ベトナムへの流浪ばなしが、おもしろい。
上映を見逃して、DVDでみたジャ・ジャンク―監督の「罪の手ざわり」にふれよう。
わたしはこの監督の作品をデビユー当時から観ていて、これまでにもその「長江哀歌」「四川のうた」などを紹介してきているが、実際おこった四つの事件を描いたこの作品をどう評価すればいいのか、いまだ戸惑っている。
この映画のオフィシャルサイトは、つぎのように書いている。
「第66回カンヌ国際映画祭脚本賞受賞!
実在の事件を基に描かれる、パワフルかつセンセーショナルな人間ドラマ村の共同所有だった炭鉱の利益が実業家に独占されたことに怒った山西省の男、妻と子に出稼ぎだと偽って強盗を繰り返す重慶の男、客からセクハラを受ける湖北省の女、ナイトクラブのダンサーとの恋に苦悩する広東省の男―。彼らが起こす驚愕の結末とは?ごく普通の人びとである彼らはなぜ罪に触れてしまったのか?」
来日した監督は、つぎのようにも述べている。
「現在、中国は急速に発展しており、以前よりもずっと裕福に見えます。しかしながら、多くの人びとは、全土に広がる富の不平等、そして大幅な貧富の格差に起因する人格の危機に直面しています」「この映画で私は、自分たちの社会は果たして発展しているのだろうか、という問いを投げかけたいと思います」そして、「四人の登場人物たちの置かれている状況や環境が昔からの武侠の世界によく似ているなと思い、武侠ものの視点で現代を撮るとどうなるかということが今回のアイデアの発端でもあった」と付け加えている。
この映画は中国国内で上映許可
は取れていたが、なぜか公開直前にDVDが市場に出て、上映中止になった由。9月訪中時に友人に頼んで探してもらったが、上海にも北京にもそのDVDは見当たらなかった。北京の友人は、ネットで一時見れたが、いまは見れないという。どうなったのだろうか?
この映画の原題は『天注定』、日本発売のDVDのケース裏面には「この世の定めか、あゝ無常―」と大書されている。
三本の映画、それぞれの視点は異なるが、さて、いかがだったでしょうか。
(2015年12月15日記)