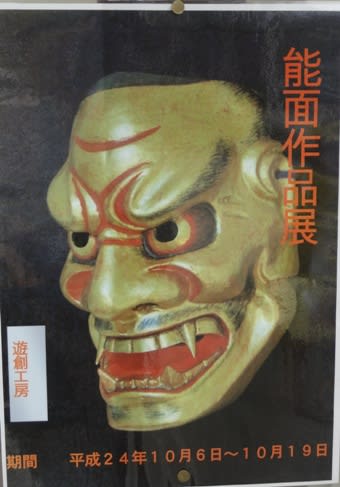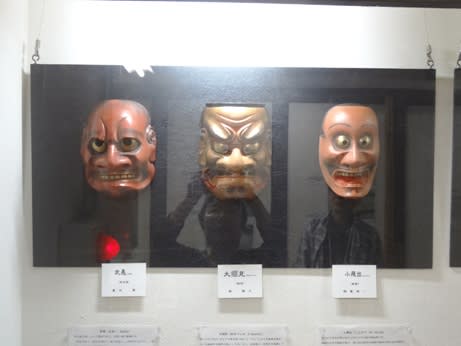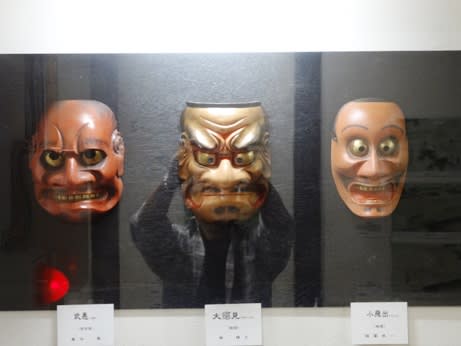猪名川の氾濫(3)
(五)
そのころ、尼崎城の堀に流入する庄下川(武庫川の支流)は濁流で溢れ、堤を崩しはじめていた。城下のいたるところが冠水・「水押」になって来ている。
この時の洪水について、武庫川流域関連の研究レポートは多いが①藻川流域の史料は少ない。
すでに触れた二件の絵図(「宇保 登文書」、「徳永孝哉文書」)はその数少ない貴重な史料である。
前者は旧下食満村(現食満六~七丁目)の、被災当事者の絵図で「元文五年申六月廿八日差上候」と洪水直後の作図であるだけにダイナミックで臨場感があるが、三食満領の堤の決壊とその「水押」状況を中心に描いている。提出先は不明である。
後者は旧上坂部村(現上坂部二~三丁目)に残る絵図。作図時期は不明であるが、添え書きに「八月廿日迄二漸ク水留廿四日二仕立申候」とあるから、水留工事の終わった同年八月末以降であろうと推察する。十枚もある絵図の一枚(文書番号三三九-一八)を別掲する。この絵図は文字の関係で南北が逆さになっているが、川西の小戸、池田の神田、伊丹の中村・下市場の中流から、尼崎城周辺の庄下川に至る川や井筋の決壊状況を測量数字で示し、村々の所領関係まで書き添えている。さらに(四)で触れた猪名川東岸の豊中市域の被害(注5参照)まで明らかにした貴重な文書である。
さらに「貴志隆造文書」は、旧富田村の一部(現園田一丁目)の被害状況を、つぎのように記している。
洪水発生五日後の六月十三日、「当村田畑損し申候」と田畑荒地は凡高〆三拾五石九斗弐合と届け出、さらに同年九月「木綿水押損毛」として米換算〆三石七斗六升五合を申請している(尼崎市史第六巻)。この合計は本高の五八・六%となる。猪名川西岸の富田村堤の決壊がなかっただけに、対岸の庄本村(豊中市)より少ない「水押」被害率で留まっている。
①大国正美「近世後期の武庫川洪水と対策」(「歴史と神戸」通巻217号)ほか。
(六)
「火の玉は飛んだ」との書き出しではじまる新聞記事(毎日新聞、尼崎・伊丹版、昭和57年3月4日)を見つけた。
「流れとともに」と題するこの企画記事は、同年1月5日スタートの第一部
から12月3日の第四部まで合計65本の連載もの、阪神間を中心とするいろいろな河川にまつわる話を取材、レポートしている。
この「火の玉は飛んだ」は第二部「川と生活」の第九話にとりあげられた「元文五年」の洪水に関わる記事である。
「目の前を突然、大きな火の玉が北から南へスーッと流れた」
昭和三十六年の秋祭りの前夜、目撃したのは田能に住む女性であった。
火の玉が飛んだのは猪名川右岸の旧堤防上、竹藪の中には地元の人が「ホウケントウの墓」と呼ぶ供養塔のあるところであった。
元文五年六月九日の夜、猪名川が藻川と分かれて田能の中州をつくり、左へ大きくカーブする川岸に、子供を含めた多くの遺体が揚がったと記事は綴られ、
「大半は逃げ遅れた池田の遊郭の女性だった」と記している。
本レポートの冒頭に記した「・・・北ノ口①京や太右衛門流レ・・・」(伊居太神社日記)とこの記事の「遊郭」が気になり、池田市史で調べ、市関係者にもヒアリングしたが不明であった。
地元では、このとき田能村に漂着した夥しい溺死者をねんごろに葬り、三回忌に地元応徳寺の和尚が発起人となって溺死霊魂の慰霊塔を建立した。その後村人は毎年命日には供養塔(地元では放献塔と呼んでいる)の前で慰霊祭を営んでいる、という(「三ッ俣井組考」)。この慰霊塔は現在田能農業公園内に移設されている。
池田徳誠氏が同書に書き記されている碑文(抄)を以下ご紹介する。
惟元文五年庚申夏六月九日
雷鳴折山俄水裏陸近迫人馬
抱擁厥老幼溺死者不知□幾
千万也・・・(以下略)
トキニ元文五年庚申六月九日、山を裂くような雷が鳴り、
豪雨は猪名川を氾濫させ、濁流は人畜に襲ってきて、
老人や子供が逃げ場を失ない、溺死するものは数えきれません(略)
(福沢邦夫先生現代語訳)
治山・治水は政治(まつりごと)の基本である。
歴史はそのことを教えている。
(了)
尼崎市立地域研究史料館で史料の提供とアドバイスをいただきました。
厚く御礼申し上げます。(伊丹:古文書を読む会会報『遊心』第20号掲載)
(五)
そのころ、尼崎城の堀に流入する庄下川(武庫川の支流)は濁流で溢れ、堤を崩しはじめていた。城下のいたるところが冠水・「水押」になって来ている。
この時の洪水について、武庫川流域関連の研究レポートは多いが①藻川流域の史料は少ない。
すでに触れた二件の絵図(「宇保 登文書」、「徳永孝哉文書」)はその数少ない貴重な史料である。
前者は旧下食満村(現食満六~七丁目)の、被災当事者の絵図で「元文五年申六月廿八日差上候」と洪水直後の作図であるだけにダイナミックで臨場感があるが、三食満領の堤の決壊とその「水押」状況を中心に描いている。提出先は不明である。
後者は旧上坂部村(現上坂部二~三丁目)に残る絵図。作図時期は不明であるが、添え書きに「八月廿日迄二漸ク水留廿四日二仕立申候」とあるから、水留工事の終わった同年八月末以降であろうと推察する。十枚もある絵図の一枚(文書番号三三九-一八)を別掲する。この絵図は文字の関係で南北が逆さになっているが、川西の小戸、池田の神田、伊丹の中村・下市場の中流から、尼崎城周辺の庄下川に至る川や井筋の決壊状況を測量数字で示し、村々の所領関係まで書き添えている。さらに(四)で触れた猪名川東岸の豊中市域の被害(注5参照)まで明らかにした貴重な文書である。
さらに「貴志隆造文書」は、旧富田村の一部(現園田一丁目)の被害状況を、つぎのように記している。
洪水発生五日後の六月十三日、「当村田畑損し申候」と田畑荒地は凡高〆三拾五石九斗弐合と届け出、さらに同年九月「木綿水押損毛」として米換算〆三石七斗六升五合を申請している(尼崎市史第六巻)。この合計は本高の五八・六%となる。猪名川西岸の富田村堤の決壊がなかっただけに、対岸の庄本村(豊中市)より少ない「水押」被害率で留まっている。
①大国正美「近世後期の武庫川洪水と対策」(「歴史と神戸」通巻217号)ほか。
(六)
「火の玉は飛んだ」との書き出しではじまる新聞記事(毎日新聞、尼崎・伊丹版、昭和57年3月4日)を見つけた。
「流れとともに」と題するこの企画記事は、同年1月5日スタートの第一部
から12月3日の第四部まで合計65本の連載もの、阪神間を中心とするいろいろな河川にまつわる話を取材、レポートしている。
この「火の玉は飛んだ」は第二部「川と生活」の第九話にとりあげられた「元文五年」の洪水に関わる記事である。
「目の前を突然、大きな火の玉が北から南へスーッと流れた」
昭和三十六年の秋祭りの前夜、目撃したのは田能に住む女性であった。
火の玉が飛んだのは猪名川右岸の旧堤防上、竹藪の中には地元の人が「ホウケントウの墓」と呼ぶ供養塔のあるところであった。
元文五年六月九日の夜、猪名川が藻川と分かれて田能の中州をつくり、左へ大きくカーブする川岸に、子供を含めた多くの遺体が揚がったと記事は綴られ、
「大半は逃げ遅れた池田の遊郭の女性だった」と記している。
本レポートの冒頭に記した「・・・北ノ口①京や太右衛門流レ・・・」(伊居太神社日記)とこの記事の「遊郭」が気になり、池田市史で調べ、市関係者にもヒアリングしたが不明であった。
地元では、このとき田能村に漂着した夥しい溺死者をねんごろに葬り、三回忌に地元応徳寺の和尚が発起人となって溺死霊魂の慰霊塔を建立した。その後村人は毎年命日には供養塔(地元では放献塔と呼んでいる)の前で慰霊祭を営んでいる、という(「三ッ俣井組考」)。この慰霊塔は現在田能農業公園内に移設されている。
池田徳誠氏が同書に書き記されている碑文(抄)を以下ご紹介する。
惟元文五年庚申夏六月九日
雷鳴折山俄水裏陸近迫人馬
抱擁厥老幼溺死者不知□幾
千万也・・・(以下略)
トキニ元文五年庚申六月九日、山を裂くような雷が鳴り、
豪雨は猪名川を氾濫させ、濁流は人畜に襲ってきて、
老人や子供が逃げ場を失ない、溺死するものは数えきれません(略)
(福沢邦夫先生現代語訳)
治山・治水は政治(まつりごと)の基本である。
歴史はそのことを教えている。
(了)
尼崎市立地域研究史料館で史料の提供とアドバイスをいただきました。
厚く御礼申し上げます。(伊丹:古文書を読む会会報『遊心』第20号掲載)